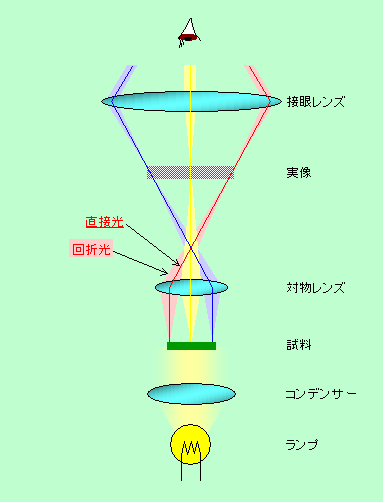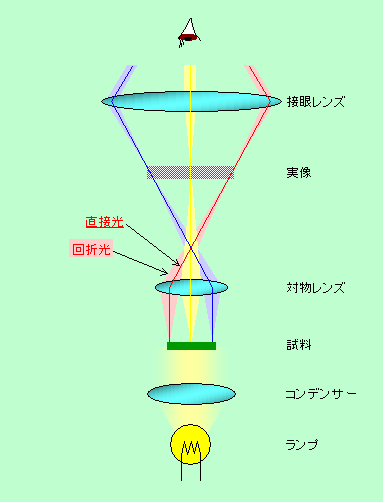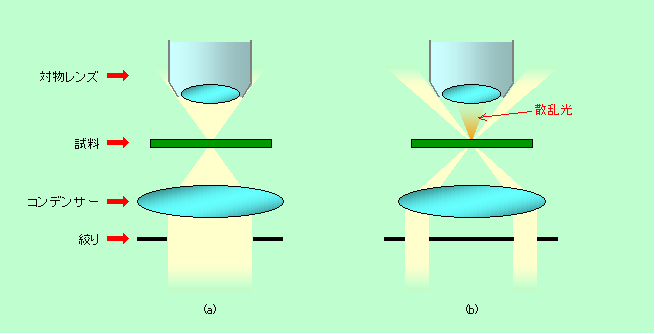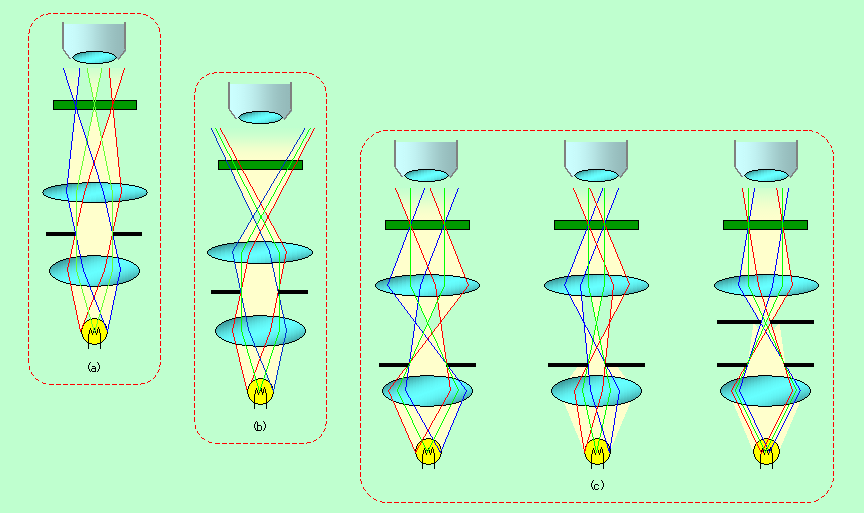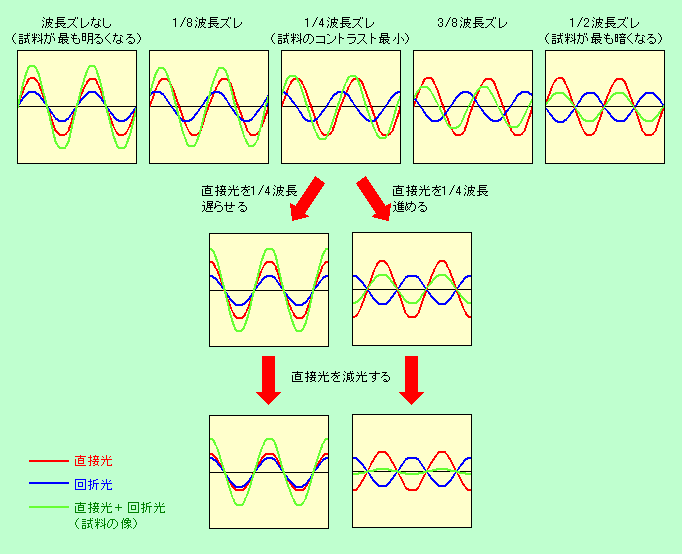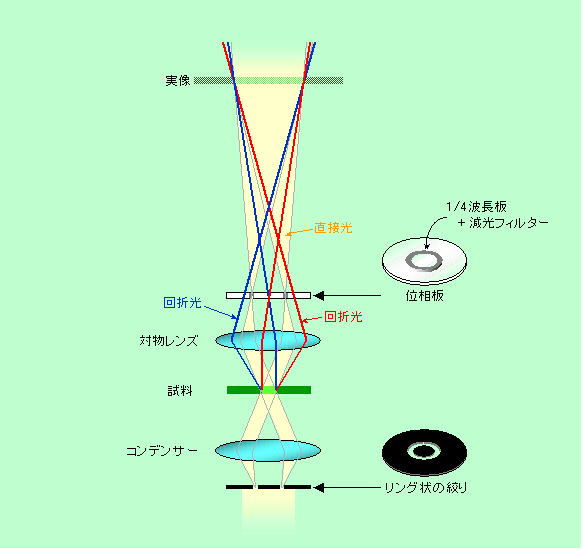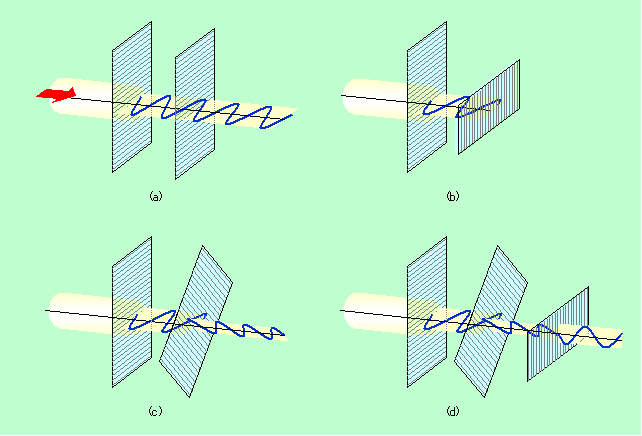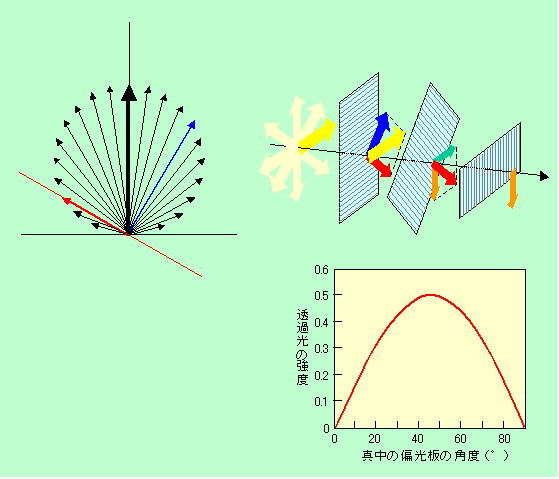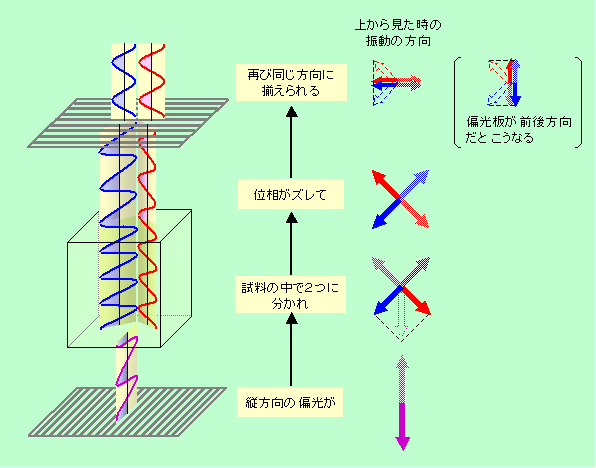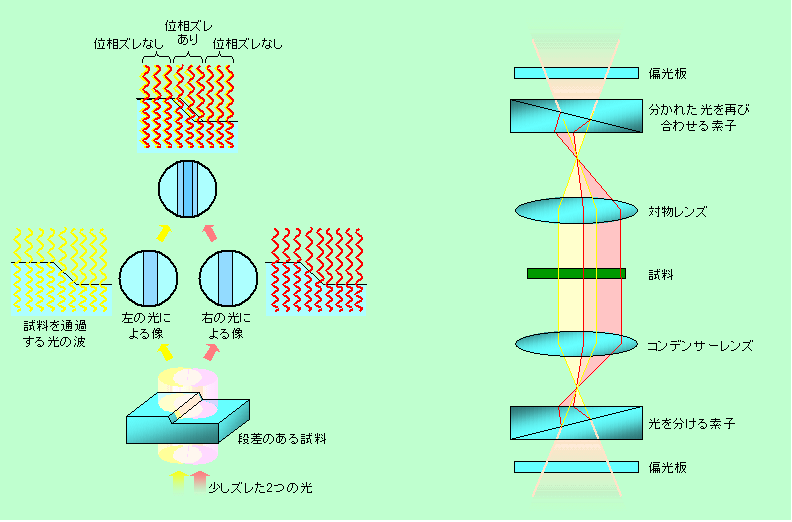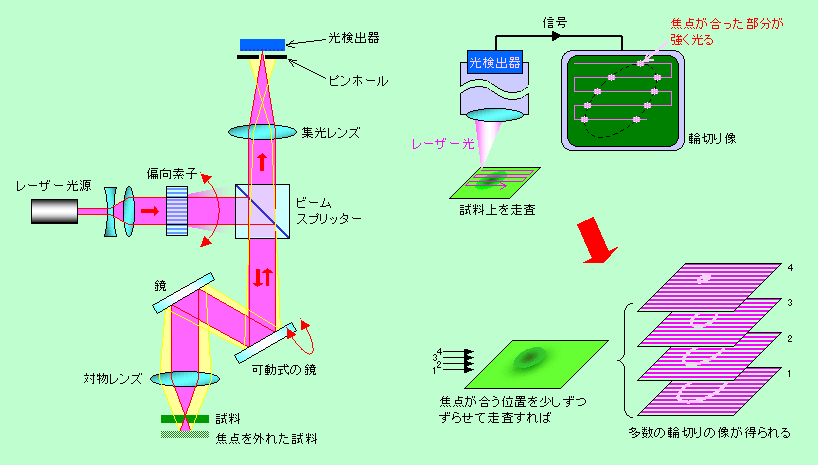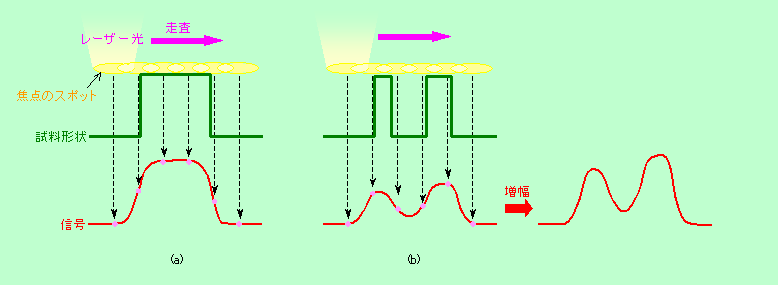雑科学ホーム
hr-inoueホーム
● 顕微鏡の話 ●
「微」なるものを「顕」かにする道具
普通に「顕微鏡」と言えば、大抵の人は理科の実験で使う光学顕微鏡を想像するでしょう。もちろん基本は、この「対物レンズを使って、鏡や電球で照明した試料の実像を作り、これを接眼レンズと呼ばれる虫メガネで拡大する装置」であるわけですが、「微」なるものを「顕(あきら)」かにする方法は、一種類に限ったものではありません。アノ手コノ手で拡大像を見やすくする工夫を施した多くの種類の光学顕微鏡がありますし、同じ光を使ったものでも原理が全く違う「レーザー顕微鏡」もあります。また、光の代わりに電子を使った「
電子顕微鏡」やX線を使った「X線顕微鏡」、さらにこれらとは別に、探針と呼ばれる小さな針を使ったプローブ顕微鏡の仲間も最近ではよく見かけます。
これらの中で、この稿では光を使って物を見るタイプの顕微鏡に絞って話を進めることにします。ただし、普通の光学顕微鏡の構造や原理については
光学機器の話で説明していますのでここでは詳しくは取り上げないことにして、本稿では、そもそも「顕微鏡の像とは何か」「どうやったら像が見えるか」ということを中心に、いろいろな光学顕微鏡について見て行こうと思います。
光学顕微鏡の像はなぜ見える?
普通の光学顕微鏡の構成を図1に示しました。照明装置(簡単なものでは鏡だけ、ちょっと高級なものではランプやコンデンサーレンズが付いています)によって照らされた試料の実像が対物レンズで作られ、これを接眼レンズで拡大します。
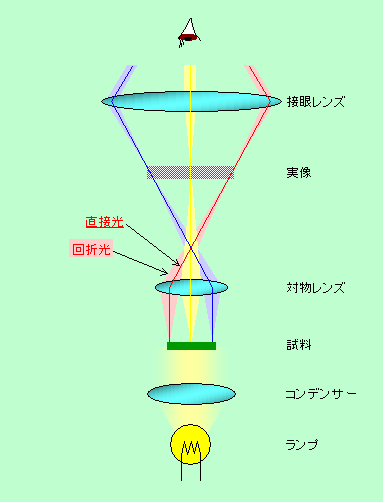
図1 光学顕微鏡の基本的な構成
これを見る限り、光学の原理に従っていて何の不思議もなさそうです。しかし「像が見える」ということには、実は様々な要素が絡んでいます。例えば、照明の光が試料を全く通過しなかったら、試料は単なる真っ黒な影として見えるだけです。逆に光がそのまま素通りしてしまうと、今度は全体がコントラストなしに一様に明るくなるだけで何も見えなくなります。つまり、多少なりとも試料の構造が見えるためには、照明の光が試料を通過する際に「何らかの変化」を受けて、コントラストができなければならないのです。
それでは、像にコントラストをつける「何らかの変化」とは何でしょうか? これにはいろいろなものがありますが、ここで、どのような「変化」を利用するのか、あるいはどのような「変化」を意図的に作るのか、ということによって様々な種類の顕微鏡が考えられるわけです。
光の量の変化を捕まえる
光が試料を通過する時に受ける変化のうち、最も簡単なのはその「量の変化」でしょう。照明装置から来た光が試料を通る時に、その一部が吸収されたり、アサッテの方向に蹴散らされたりすることで、対物レンズに入る光量が減って暗くなるのです。
「光の吸収」については特に説明は不要でしょう。吸収された部分は光が弱くなりますから、他の部分よりも暗くなってコントラストが得られます。吸収の度合いによって明るさが異なるいろいろな部分が区別されるのです。一方「光の蹴散らし」については少し補足しておく必要があるでしょう。これには「散乱」と「回折」という2つの型がありますが、通常の顕微鏡観察でコントラストに効くのは「散乱」の方です。
「散乱」は物に当たった光が四方八方に撒き散らされる現象です。特に光の波長よりも小さい凹凸や粒状物(本当の粒子の場合もありますし、密度などが違う部分が点々と存在している状態の場合もあります)は散乱能力が高く、それこそ360°光を蹴散らします。このようにして大きく方向転換した光は対物レンズに入ることができないので、実像作りには参加できません。その結果、光の散乱を起こした部分は像が暗くなってコントラストができるのです。
これに対して「回折」は、物の端や孔の部分で光が陰の部分に回り込む現象です(
光学機器の話や
立体映像の話に参考記事あり)。例えば図1の場合、試料と何の作用もせずに通過した照明光(直接光と呼びます)は、赤、青、黄の3本の線で示したようなルートで目に届きます(もちろん光はこれだけではありません。わかりやすくするために代表的な3本の光路を示しただけです)。一方、試料に密度差がある部分などがあると、そこで照明光が回折を起こして、淡く着色された部分で示すように少し広がりながら進みます。しかし、回折光の方向は直接光の方向と極端に違うわけではありませんから、散乱の場合と違って、大部分の回折光は対物レンズに入ることができます。そのため、回折現象だけでは明暗のコントラストはほとんど得られない、ということになります。
というわけで、普通の光学顕微鏡で見られる光の量によるコントラスト、つまり明るさの変化の原因は、試料による吸収と散乱です。ただし、散乱による光のロスはそれほど大きくないので、大部分は試料が光を吸収することによる、と考えてよいでしょう。
光の量の他に、光学顕微鏡では色も重要な要素です。「色がついている試料は見やすい」というのは当たり前のことですね。これを「光の変化」という見方で回りくどく言えば、「試料が照明光から特定の波長(つまり色)の光を吸収し、残った光だけを通過させる」ということになるわけです。その意味では、色も「光の吸収」の一種と言うことができるでしょう(
色の話参照)。このように、「明るさ」と「色」という2つの要素の変化を捕まえてコントラストをつけるのが、普通の光学顕微鏡です。
光学顕微鏡には、「落射照明」といって、照明光を下から当てて透過させるのではなく、試料の上から当てて反射させる方式のものもあります。この場合も基本的な原理は変わりません。照射された光は、試料表面で吸収・散乱されたり、表面の微細な凹凸によって違う方向に反射されたりして、対物レンズに入る光量が変化し、明暗のコントラストがつきます。また反射する時に特定の波長の光を吸収することで、それぞれの色が観察できるのです。
捨てる光を利用する ― 暗視野法 ―
普通の光学顕微鏡では、試料を通して照明光を対物レンズに直接入れています。これとは別に、試料を斜めから照射して、わざと照明光を対物レンズに入れないようにする方法があります。このようにすると、試料がない部分からは光が全く来ませんから、顕微鏡の視野の背景は真っ暗になり、その中に散乱光で光った試料が見えることになります。これを暗視野法と言います(これに対して普通の観察法が明視野法です)。図2に、明視野と暗視野の照明法の比較を示しました。
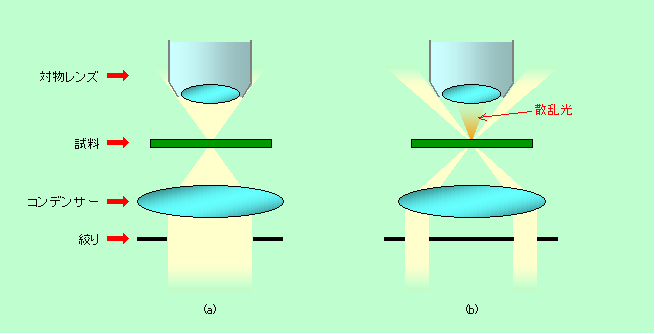
図2 明視野法と暗視野法の違い
(a)が普通の明視野法で、(b)が暗視野法です。明視野法では普通の丸い孔の開いた絞りを使いますが、暗視野法では、明視野では開いていた孔が完全に塞がって、代わりにその周囲がリング状に開いた形の絞りが使われます。このような絞りを入れると、試料を通った照明光が全て対物レンズの周辺に逃げて行ってしまい、対物レンズに入るのは試料で散乱された光(の一部)だけになるのです。
試料の観察に光を使う限り、光の波長よりも小さい構造を見ることは基本的にはできません。光から得られる位置の情報には、必ずその波長程度の「曖昧さ」が含まれているため、光の波長程度のボケが必ず発生するからです。ところが「散乱」という現象に関しては、光の波長レベルか、むしろそれよりも小さい構造の方が効果が大きくなります。光の波長よりも2桁も小さい粒子からも、強い散乱が起こるのです。そのため暗視野法を使うと、明視野法ではぼやけて見えなかった微細な構造、特に微粒子や微細なキズ、欠陥などが観察できるようになるのです。ただし、鮮明に微細構造が見えるというわけではなく、あくまでも「存在が確認できる」レベルです。
身近な例としてよく引き合いに出されるのが、暗い部屋で壁などの小さな孔や隙間から差し込む光の中で細かな塵がキラキラ光って見える、というチンダル現象です。これも、暗い部屋をバックにすることで光の波長よりも小さな塵からの散乱光が見える、という暗視野照明の一種です。
照明法の話が出たついでに、少し余談になりますが、明視野法での照明装置のことにも触れておきましょう。同じ明視野法でも照明のやり方にはいくつかのタイプがあり、主なものは図3に挙げた3種類です。
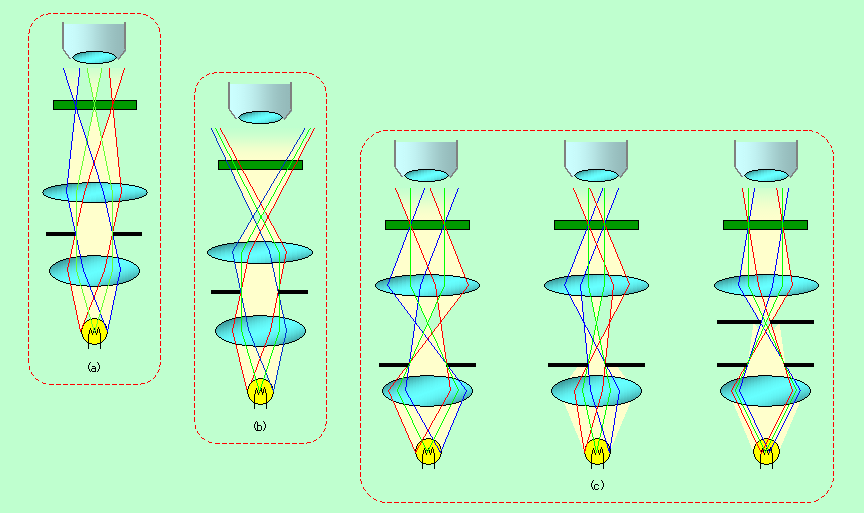
図3 照明法のいろいろ
(a)はランプの実像を試料の位置に作る方式で、効率の良い照明法ですが、ランプのフィラメントの像が見えてしまいますから、どうしてもムラが出ます。これに対して(b)は、ランプの実像をもっと手前に作って、ボワッと広がった光で試料を照明する方式です。広い面積を均一に照射できて(a)のようなムラは出ないのですが、図からもわかるように、光がずいぶんムダになります。このようなムラとムダをなくすように工夫したのが(c)の方式で、下のコンデンサーレンズでランプの実像を作り、その実像からの光を上のコンデンサーレンズで平行光線にするようになっています。このシステムの特徴は、絞りの実像が試料の位置にできるようになっていることです(図3(c)で絞りの端を通った赤、青、緑の3本の光が試料の位置で再び一箇所に集まっていることでわかります)。
平行光線を得るだけならば、下のコンデンサーレンズを省略して、実像ができていた場所に本物のランプを持ってくれば済むのですが(図1の照明装置の形です)、わざわざ図3(c)のような複雑な形にするのには理由があります。絞りの実像が試料面にできるということから、図3(c)の中央の図のように、絞りの孔径を調節することで簡単に照射面積を変えることができるのです。さらに、ランプの実像の位置に別の絞りを追加すると、ここで実像の周辺部をカットすることになりますから、試料に当たる光の量が少なくなります。この時、第一の絞りの実像である試料の照射面積は変化していません(図3(c)右)。つまり図3(c)のシステムを使うと、試料の照射面積と明るさとを別々に制御できるのです。このような利点から、ちょっと高級な顕微鏡の照明装置は、ほとんどがこの方式になっています。
補足:絞りの役割
図3(c)右のタイプの照明法は「ケーラー照明」と呼ばれ、多くの高級な顕微鏡に採用されています。上の説明では省略しましたが、このタイプの照明に付いている2個の絞りの役割について、少し補足しておきましょう。
まず下側の絞りですが、これは「視野絞り」と呼ばれます。この絞りの実像が試料の位置にできますから、文字通り視野(照射範囲)を決める絞りです。この視野絞りの役割は、余分な光をカットして鮮明な像を得ることにあります。視野絞りがないと必要以上に広い範囲に照明の光が当たってしまい、この余分な光が装置の壁などのいろいろな部分で散乱されて像に被さってしまうのです。そのため視野絞りは、観察する視野がギリギリ収まるぐらいの範囲に設定するのが普通です。(当然、高倍率になるほど視野は狭くなりますから、それに合わせて視野絞りを小さくすることになります)
次に2つめの絞り、「開口絞り」です。上の説明では単純に「視野の明るさを変える」と書きましたが、具体的には、光源の実像の位置にある開口絞りを調節することで、光源から実際に光を取り出す範囲を変えるようになっています。例えば視野を明るくする時には、開口絞りを開いて、より広い範囲から光を取り込むことで光の量を増やしているわけです。この時、広い範囲から光を取り込むのですから、試料のところに光が集まる角度は大きくなり、同時に試料を通過した後に光が広がる角度も大きくなります(図3(c)で、左端の開口絞りがない状態と右端の開口絞りがある状態で、試料のところの光の角度が違っているのがわかると思います)。実はこの角度が、顕微鏡観察では非常に重要な意味を持ちます。
光の角度が大きいと、試料にいろいろな角度で光が当たります。その結果、本来は光が通らない影の部分が少し明るくなるなど、試料の明暗の差がボヤけてしまいます。つまり、開口絞りを大きく開けると像のコントラストが落ちるのです。一方、開口絞りを絞って光の角度を小さくすると、今度は対物レンズの中央付近の一部にしか光が入らなくなります。これは対物レンズの直径を小さくしたのと同じですから、光の回折による滲みが大きくなって解像度が低下してしまいます(レンズ径と解像度の関係はカメラの話で詳しく説明しています)。
それでは実際の顕微鏡観察の際に、開口絞りはどのくらいにしたら良いのでしょうか。まず解像度を考えると、対物レンズの径いっぱいに光を取り込むのが理想です(それ以上に広げても、対物レンズからはみ出してしまいますから無意味です)。一方でコントラストの面では少し絞った方が有利になりますから、両者のバランスのよいところを探す必要があります。最適な絞り加減は試料の状態や観察の目的などによっても変わるので、厳密には観察しながら探すしかありませんが、一般的には、光の広がりを対物レンズの直径の80%程度にするのが良いとされているようです。このおよその位置を見つける最も簡単な方法は、顕微鏡をのぞきながら、開口絞りを最大の状態から徐々に絞って行くことです。初めのうちは対物レンズの直径よりも光が広がっていますから視野の明るさは変化しませんが、光の広がりが対物レンズの直径よりも小さくなり始めたところで視野は暗くなり始めます。そのちょっとだけ暗くなったところがちょうど良い状態(に近い)ということになります。また別の方法として、接眼レンズを取り除いて鏡筒を覗き込んだ時に見える丸い光(これは対物レンズの「瞳」と呼ばれるもので、対物レンズが作る光源の像であり、また開口絞りの像でもあります)を利用することもできます。開口絞りを操作するとこの丸い光の径が変化しますから、最大直径の80%ぐらいになるように調整すれば良いのです。
位相の変化を捕まえる ― 位相差顕微鏡 ―
先に、試料を通った光が直接光と回折光に分かれて、実像のところでまた一緒になる、ということを書きました。この回折光は直接光と全く同じ状態の光ではありません。回折の過程で、波の山(谷)の位置が直接光とズレている、つまり位相が違っているのです。ただし位相が違っていても、光の強さや色は変わりませんから、そのままでは違いを感知することはできません。ところが位相の違う波が出会うと、山と山(谷と谷)が重なる場合には強め合い、山と谷が重なる場合には弱め合いますから、位相の違いが明るさの違いになって姿を現します(光の干渉)。この現象を利用して、見えないはずの位相の変化を見えるように変換するのが位相差顕微鏡です。生体試料などには無色透明なものが多く、試料を通過しても光の量や色がほとんど変化しませんから、普通の光学顕微鏡ではよく見えません。しかし、このような試料でも位相が変化した回折光は出ていますから、位相差顕微鏡を使うと観察できるようになるのです。
試料から出た直接光と回折光とが実像のところで一緒になると、この2つの光は位相が違っているのですから、干渉を起こしてもいいはずです。干渉を起こせば明るさが変化するはずですから、普通の顕微鏡でも像が見えそうなものです。ところが実際には、多くの場合、まともな像は見えません。なぜでしょうか? それを以下に説明しましょう。
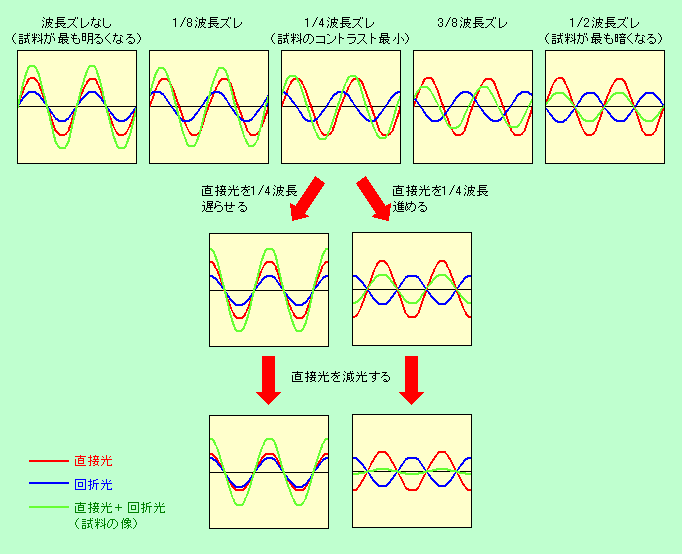
図4 直接光と回折光の干渉
図4は直接光と回折光の干渉の様子を示しています。試料の部分では、赤で示した直接光と青で示した回折光とが一緒になって、緑で示した光が観測されます。上段左端は赤と青の波長ズレが全くない(位相がピッタリ合っている)場合で、山どうし、谷どうしが重なりますから、それらが合さってできる緑の波の振幅は最も大きくなります。つまり、試料は最も明るく見え、回折光の強度変化はそのまま像の明るさに反映される、ということです。回折光の位相が1/8波長だけ遅れたのが左から2番目の図です。緑の波の振幅は、位相ズレがない場合と比べて小さくなっていますから、試料は少し暗く、回折光の強度変化の影響も少し現れにくくなります。回折光の位相遅れがさらに大きくなって1/4波長になると、中央の図のように、緑の波の振幅はもっと小さくなって、直接光だけの時とほとんど変わらないレベルになってしまいます。この状態では、回折が少々変化しても像の明るさにはほとんど影響はありませんので、試料には大きなコントラストは付きません。ここを通り越してさらに回折光の位相が遅れて来ると、今度は緑の波の振幅が元の直接光よりも小さくなります。こうなると、逆に回折光が強いほど試料は背景よりも暗い部分として目立って来ることになり、位相が1/2波長ズレた状態になった時に、最も暗い像として見えることになります(右端の図)。
都合の悪いことに、多くの試料は1/4波長程度の位相ズレを起こします。つまり図4の上段中央の状況に近いわけで、回折光の強度変化、つまり位相ズレの情報を明暗に変換するには最悪の状態、と言うことができます。それではどうしたら位相のズレを目立たせることができるでしょうか。それには、何とかして図の左端か右端の状態にしてやればよいのです。つまり、直接光(赤の波)だけを右か左に1/4波長分だけズラしてやるのです(図4中段)。さらに、直接光をただズラすだけでなく、その強度を回折光と同じぐらいのレベルまで弱めてやると、干渉の効果が強く出て、もっとコントラストが強くなります。例えば直接光の位相を1/4波長遅らせる場合、直接光の強度を弱めると赤と緑の両方の振幅が小さくなりますが、比率で言えば、かえって両者の違いが際立ちます。また直接光の位相を1/4波長進める場合には、直接光の強度を弱めると緑の波は強度がほとんどなくなりますから、試料部分の暗さが一層目立つようになるのです。
さて、どうすれば位相の違いを明暗の違いに変換できるかはわかりました。でも、直接光にだけ操作を加えるというような都合の良いことが本当にできるのでしょうか。実はできるのです。それを実現したのが、図5に示した位相差顕微鏡です。
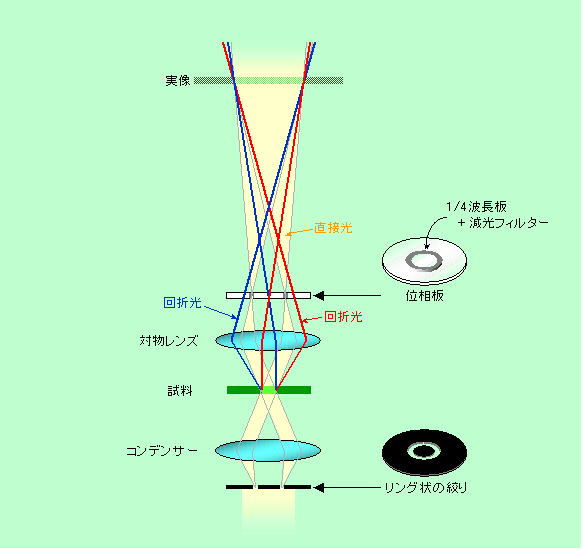
図5 位相差顕微鏡は直接光だけを操作する
照明装置は図3(c)の形のものですが、コンデンサーレンズの下側にリング状の絞りが入っています。ここを通った光は試料を通過した後に対物レンズに入り、ずっと先に試料の実像を作るわけですが、その手前にリング状絞りの実像ができる部分があります。つまり、リング状絞りを出た光が、一旦、元のリングの形に集まる部分があるのです。ところがこのようなルートを辿るのは、試料とは相互作用しない直接光(図の黄色の光)のみです。試料部分で方向が変えられた回折光は、図の赤線や青線で示したように、リング状には集まりません。ということは、リング状絞りの実像ができる部分では、直接光と回折光とがうまく分離しているのです。そこでこの部分に、リング状絞りの像にピッタリ合う特殊な素子を置いておけば、直接光だけを操作することが可能になります。
直接光を操作するのに使う素子を「位相板」と呼びます。位相板は大部分が透明な板ですが、ちょうどリング状絞りの実像のできる部分にだけ、光の位相を1/4波長ズラすことのできる「1/4波長板」と、光量を落とす減光フィルターが取り付けられています。これによって、リング状絞りの実像部分を通る直接光だけが、望みどおりに操作できて、光を吸収しない無色透明の試料でも、位相差による明暗のコントラストを付けて観察することができるのです。。
もっとも、試料を通った回折光の位相が常に1/4波長ズレる、というわけではありませんし、その強度も試料の状況によってまちまちですから、同じ構成の位相差顕微鏡でいつも鮮明なコントラストが得られるとは限りません。回折光の位相ズレが大きい場合には、位相板を入れることでかえってコントラストが悪くなったり、明暗が逆転したり、ということも起こります。実によくできた装置ですが、微妙な調整が必要で、能力を十分に発揮させるのは簡単ではありません。
方向による性質の違いを捕まえる ― 偏光顕微鏡 ―
光というのは電場(と磁場)が振動しながら伝わって行くものですが、普通はいろいろな方向に振動する光が混ざっています。ところが、物質を通過したり反射したりした光では、その振動方向が揃ったり、振動方向がぐるぐると回転しながら進んだりすることがあります。これが偏った光、「偏光」です。そして意図的に偏光を作ることができる素子が「偏光板」であり、偏光板を使って試料の偏光に対する性質を見るのが偏光顕微鏡です。この偏光板にはいろいろなタイプのものがありますが、最も普通に使われているのは、樹脂フィルムの中にヨウ素を並べて埋め込んだものです。ヨウ素分子の列がスリットのようなはたらきをして、その方向に振動する光だけが通過するのです。
偏光板をスリットに見立てて、スリットの隙間方向に振動する光だけが通る、という説明の仕方はわかりやすくてよいのですが、偏光顕微鏡を理解するにはちょっと具合が悪い点があります。そこで予備知識として、偏光について少し詳しく見ておきましょう。
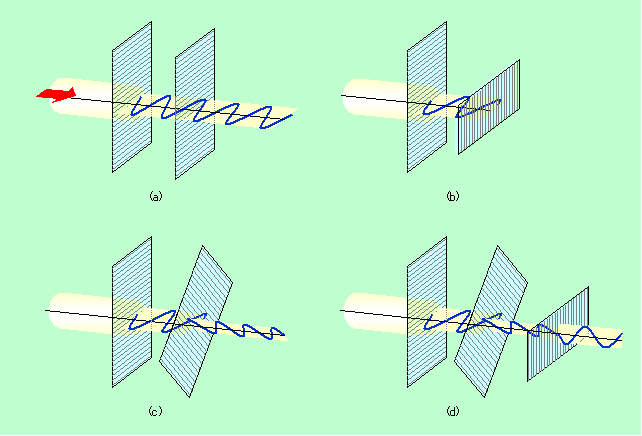
図6 偏光板を重ねてみる
図6のように、2枚の偏光板を重ねてみます。この時、2枚の偏光板の向きが揃っていれば、(a)のように、1枚目の偏光板で作られた偏光は、そのまま2枚目の偏光板を通過します。次に(b)のように、2枚目の偏光板を90°回してみましょう。今度は1枚目の偏光板で作られた偏光は2枚目を通過できませんから、右からのぞくと真っ暗に見えます。ここまでは何の問題もありません。それでは、(c)のように、2枚目の偏光板を45°傾けたらどうなるでしょうか。今までの説目の仕方では、この場合も光は通り抜けて来ないはずです(もし光の一部が通るのであれば、1枚目の偏光板でも同じように、斜めに振動する光が抜けてくるはずですから)。ところが実際には、70%もの光が通るのです。さらに、(d)のように90°傾けた2枚の偏光板の間に45°傾けた3枚目の偏光板を入れたら、(b)では全く通過できなかった光が、何と50%も通るようになるのです。
これを解釈するには、偏光についてもう少し突っ込んだ見方が必要です。実は偏光というのは単純に一方向にだけ振動しているのではなくて、違った方向の振動成分が合さった結果として、一方向の振動だけが現れているのです。図7にその様子を模式的に示しました。
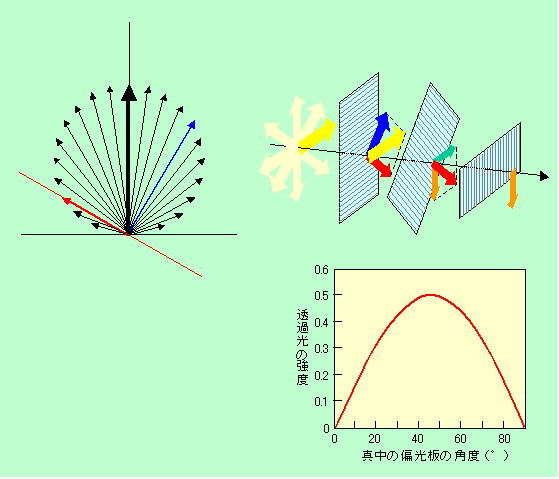
図7 偏光は単純に一方向にだけ振動する光ではない
垂直方向に振動する偏光を考えます(左の図の太い黒矢印)。この偏光には、垂直方向だけではなく、他の方向に振動する成分も含まれています。ただし、それぞれの方向の成分の大きさは図のように左右対称で(前後はもちろん非対象です)、右側と左側の成分は同じタイミング(つまり位相)で振動しているので、結果的には垂直方向の振動しか見えないのです。ところがここに偏光板があると、特定の方向の成分だけが見えて来ます。例えば図の赤線の方向を向いた偏光板をかけると、その方向に振動する赤矢印の成分だけが通過し、それと垂直な青矢印の成分は完全にカットされるわけです。
この考え方に従って、もう一度図6(d)の3枚重ねのケースを見直してみましょう(図7右上)。1枚目の偏光板を通過してきた水平方向に振動する偏光(黄色矢印)のうち、赤矢印で示した成分だけが2枚目の偏光板を通過します。そして3枚目の偏光板では、赤矢印の成分の中のさらに橙色の成分だけが通過するのです。このように、偏光板の重ね合わせでは、2枚重ねよりも3枚重ねの方が光が多く通過する、という不思議な現象が起こるのです(ちゃんと理屈を理解すれば不思議でも何でもありませんが)。図7には参考として、3枚重ねの真中の偏光板の角度と、通過してくる光の量の関係を載せておきました。通過する光の強度は45°の時が最大で、0°と90°では、2枚の時と同様にゼロとなります(厳密に言うと、この図で示しているのは透過する光の振幅で、エネルギーの場合にはグラフの形がちょっと変わりますが、傾向は同じようなものです)。
それでは話を顕微鏡に戻しましょう。偏光顕微鏡では、試料の下側(照明のところ)と対物レンズの上側に偏光板が入っています。2枚の偏光板の方向を直角にした場合、そのままでは真っ暗で何も見えません。ここで、方向によって光に対する性質が違う試料を持って来ましょう。光に対する性質が方向によって違うということは、特定の方向に振動する光、つまり偏光をよく通す、ということにつながりますから、これは偏光板と同じはたらきをします。その結果、偏光板を3枚重ねにした時と同様に、試料がある部分だけ光が通るようになり、明暗のコントラストが得られるわけです。
「光に対する性質が方向によって違う」というと、何か特殊なもののように感じるかもしれませんが、実際には身の回りにいくらでもあります。結晶性の物質は、食塩などの一部のものを除いてこの性質があります(元々結晶には方向性がありますからね)。繊維なども、長く連なった分子が一方向に並んでいますから、長さ方向と幅方向とで光に対する性質が違っています。セロハンテープを初めとする樹脂フィルムも、フィルムを作る時に一方向に引っ張るために分子の向きがある程度揃って、その引っ張った方向とそうでない方向で違う性質を持つ例が多くあります。またプラスチック成型品などの場合には、成型の時に溶かした原料を型に流し込んだりしますから、その流れの方向や、加わった圧力で内部に歪みが残っているのが普通で、これも方向による性質の違いをもたらします。さらに、元々は歪みがなくても、力を加えて歪ませることで一時的に方向による違いが出てくる場合もあります。ガラスやプラスチックではよく見られる現象です。このように、世の中の多くの物質が、偏光顕微鏡の観察対象になるのです。
ところで偏光観察では、明暗の他に無色の試料が色付いて見えるという特徴があります。ステンドグラスのように虹色に輝く顕微鏡写真を見たことがある人も多いでしょう。このような着色が起こるには、試料が偏光板の様に一方向の偏光だけを通すのではなく、互いに垂直な方向に振動する2つの偏光を通すことが必要です。光に対して特別な性質を示す2つの方向を持っている、ということです。先に挙げた結晶や繊維、樹脂フィルムなどはほとんどがこのタイプで、2つの方向で分子の並びや密度が大きく違っていますから、2つの偏光の進む速さも違っています。この性質を「複屈折」と呼びます(物質の中では光の速さが真空中よりも遅くなります。その遅くなる程度が屈折率ですから、複数の屈折が起こるという意味でこう呼ばれるのです)。
複屈折があるとなぜ色が付いて見えるのかを説明したのが図8です。光は下から上に向かっていると考えてください。
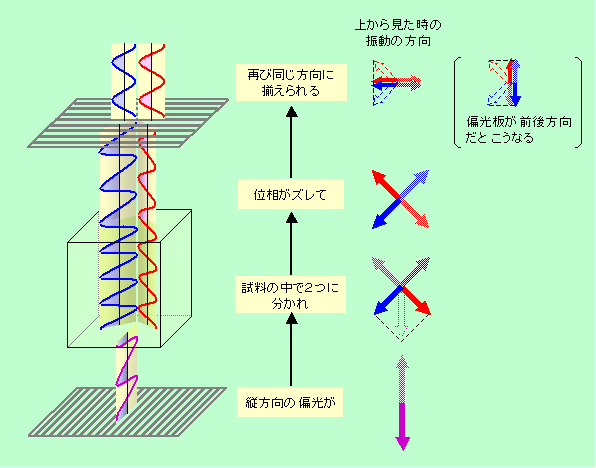
図8 複屈折で起こる光の干渉
下の偏光板を通った光が複屈折の性質を持った試料に入ると、2つの方向の偏光に分かれます。この2つの方向で屈折率が違っている、つまり光の進む速さが違っていますから、例えば図の赤で示した光と比べて、青で示した光は進行が遅く、進行方向にギュッと押し縮められたようになっています。波の数を数えてみてください。青で示した光は試料の中に4波長あるのに対して、赤で示した光は3波長半しかありません。その結果、試料の出口では、2つの光の山の位置にズレができる、つまり位相のズレが起こるのです。図の例で見ると、試料の入口では2つの偏光は前後方向に同じ位相で振動していますが、出口では、青で示した波が手前に振れている場所で、赤で示した波は奥に振れており、全く逆の位相になっているのです。
「位相が違う光」と来れば、次は「干渉」となるところです。ですが、このままでは2つの光は干渉することはできません。振動方向が90°違っているからです。しかし、これをもう一度偏光板に通すと、同じ方向に振動する成分だけが取り出されますから、干渉できるようになります。図の例で言えば、左右方向の振動成分だけが取り出されるわけで、2つの光は前後方向では位相が逆でしたが、左右方向では同じ位相で振動しています(青で示した波が左に振れた時、赤で示した波も左に振れています)から、干渉して強め合うことになります。
図の例のように2つの光が強め合う場合には、当然その波長に相当する色が強く見えます。そして、試料の性質や厚さが違うと位相のズレ方が変わりますので、強め合う光の波長も違って来る、つまり違う色に見えることになります。偏光顕微鏡で観察すると無色の試料に様々な色が付いて見えるのは、このような理由によるのです。
偏光板を回転させると、また面白いことが起こります。例えば上の偏光板を90°回して、前後方向の振動成分を取り出すことを考えましょう。前後方向では、赤で示した波と青で示した波は逆方向に振れていますから、図の右上の括弧内に示すように、今度は2つの光は弱め合うことになります。もしもこの光が赤色の光であるならば、偏光板が左右に向いていた時は赤く見えていた試料が、偏光板を90°回すことで、赤が抜けた色、つまり赤の補色であるシアン(青緑)に変わってしまうのです(
色の話参照)。
また、偏光板の配置はそのままで試料の方を回転させると、図7に示したように角度によって透過する光の量が変わりますから、この場合も違った色合いに見えて来ます。このように偏光顕微鏡による観察では、偏光板や試料を回すことで、虹色に着色された試料の色が次々に変化する様子を見ることができるのです。
偏光顕微鏡はいろいろな場面で使われますが、最も代表的なのは岩石の観察でしょう。岩石はいろいろな種類の鉱物結晶が集まったものですから、光が通るぐらいに薄くスライスした岩石を偏光顕微鏡にかけると、それぞれの鉱物が、それぞれの性質や結晶の向きに応じて、様々な色に着色して見えるのです。また別の特徴的な例として、中心から放射状に結晶が成長した「球晶」があります。高分子の結晶などでよく見られるもので、普通の結晶では同じ性質を持つ面は平行に並びますが、球晶では中心から外に向かって放射状になります。このような結晶を偏光板を直角方向に配置して観察するとどうなるでしょうか。まず、試料の厚さや外面の角度が中心から外に向かって連続的に変わりますから、同心円状の模様が見えます。そして図7のグラフのパターンに従って、偏光板の向きに対して45°になっている部分は明るく、0°または90°(つまりどちらかの偏光板と同じ方向)になっている部分は暗くなりますから、球の中心から4つの方向に、十文字に暗い帯が走るのです。見ている対象が球晶かどうかが一発でわかる、というわけです。
境界を強調する ― 微分干渉顕微鏡 ―
位相差顕微鏡や偏光顕微鏡では、位相のズレた2つの光(位相差顕微鏡では直接光と回折光、偏光顕微鏡では2つに分かれた偏光)が試料によって作られ、それが干渉して明暗を作りました。微分干渉顕微鏡では、試料の側に、光を分ける能力は必要ありません。その代わり、機械の方で光を2つに分けて試料に照射し、それを干渉させます。
基本的な原理を図9に示しました。
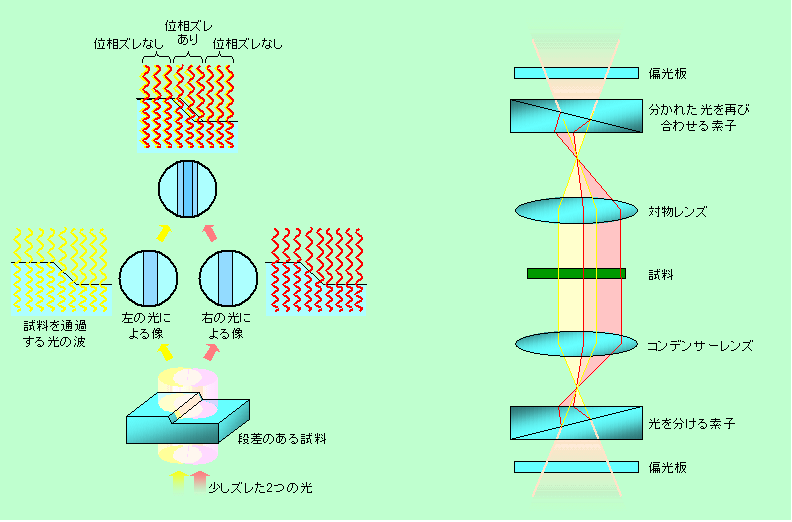
図9 微分干渉顕微鏡は性質が変わる境界を強調する
左の図に示すように、ちょっとだけ位置がズレた2つの光で試料を照射します(図ではかなり大きくズレていますが、実際にはズレているのかどうかわからないぐらいの微妙な差です)。左の光でできる像と右の光でできる像とは、当然、少しズレます(視野の中の段差の位置が違っています)。図には、光の波が試料を通過する様子を真横から見た様子も示しています。光は物質の中では速度が落ちますから、試料中の波は圧縮されて波長が短くなり、抜け出たところで、試料の厚みに応じた位相ズレを起こしています。
この2つの像を重ねてみましょう。試料の平らな部分では、左の像でも右の像でも条件は全く同じですから、互いの波はピッタリ重なります。つまり位相のズレはありません(光学系によるズレは無視)。ところが斜めになった部分では、左の像と右の像とで位置がズレているため、試料の厚さが違う部分が重なってしまいます。厚さが違う部分から出てくる波の位相は当然違っていますから、2つの波は平らな部分とは違うパターンで干渉を起こし、コントラストが付いて見えるのです。
実際の微分干渉顕微鏡では、図9右のような方法で、ズレた光を作っています。照明から出た光を偏光板に通し、特殊な素子で互いに垂直な2つの偏光に分けます。偏光顕微鏡のところで説明した、複屈折のある試料で起こる現象と同じようなものと思ってもらえばよいでしょう。この2つの偏光は進行方向も少しズレますので、光は2方向に分かれて進むことになります。この2つの光をコンデンサーレンズで集めて、少しズレた光として試料に照射します。試料を通過した光は対物レンズで集められ、その先に取り付けたもう一つの素子で再び合わされて、最後に偏光板を通して干渉できるように振動方向を揃えてから接眼レンズに入れるのです。
図9からわかるように、微分干渉顕微鏡で強調されるのは、斜めになった部分や段差の部分、あるいは性質が変化する境界の部分です。これらの部分が強調されることになるので、まるで縁取りしたかのように、あるいは縁取られた部分が大きく浮き上がっているかのように、くっきりと観察できるようになるのです。また、ここでは透過光で説明しましたが、反射光でも同じように、段差の部分や斜面で微分干渉像を観察できます。
光を使う、全く別の顕微鏡 ― レーザー顕微鏡 ―
普通に「レーザー顕微鏡」と言われるのは、「光源にレーザー光線を使った光学顕微鏡」ではありません。これまでに説明してきた光学顕微鏡とは全く別モノ。名前は同じ顕微鏡ですが、原理が全然違う機械です。
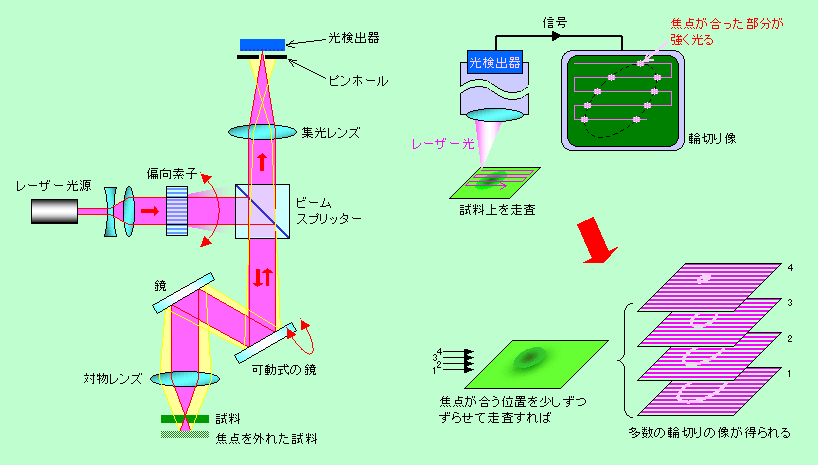
図10 光学顕微鏡とは全く違うレーザー顕微鏡
図10左がレーザー顕微鏡の構造です。レーザー光を下の試料のところへ導き、対物レンズで試料上に焦点を結ばせます。試料から反射して来た光は途中までは同じ経路を戻り、ビームスプリッターで検出器の方へ向けられます。試料上にちょうど対物レンズの焦点が合っている場合には、図の赤で示したように、反射光が集光レンズの焦点に置かれたピンホールをうまく通過して検出器に入ります。しかし焦点が合っていない場合には、黄色で示したようにボケた光が試料に当たり、反射光もピンホールのところで広がってしまって、ほとんど検出器には届きません。そのため、試料にきっちり焦点が合っている場合だけ、強い光が検出されることになります(このように、対物レンズの焦点が合った時に集光レンズの焦点に反射光が集まる、ということから、「共焦点顕微鏡」と呼ばれます)。
ただ、このままでは試料上の一点の情報しか得られませんから、偏向素子と可動鏡を使ってレーザー光の方向を変えられるようになっています。このシステムを使ってレーザー光で試料をくまなく走査し、それと同期させて検出器の信号をディスプレイ上に表示してやれば、焦点が合っている部分だけが明るく光った図が描けるのです(図10右上)。さらにレンズ系を操作して焦点の位置を少しだけずらし、同様の走査を繰り返せば、試料を水平面で輪切りにした像がたくさん得られます。これをコンピューターで処理することによって試料形状の3次元像を作ることができるのです(図10右下)。
先に、光学顕微鏡では光の波長よりも小さいものは観察できない、と書きました。可視光線の波長は0.5μmぐらいですから、0.5μm以下の微細な部分はボケてしまうということです。人が顕微鏡の拡大像で見分けられる最小の大きさを0.3mmとした場合、0.5μmの物を0.3mmに見えるまで拡大する、つまり倍率を600倍以上にすると、像のボケが見えて来るということになります。レーザー顕微鏡でも、この光の波長から来る制約はあります。対物レンズでどのくらい光を小さなスポットに絞り込めるかで観察できる最小面積が決まるのですが、光の波長よりもスポットを小さくすることはできないからです。ただし普通の光学顕微鏡と違って試料からの光で直接に像を形成するわけではありませんから、実際には絞り込んだスポットの径よりも小さい物まで観察できます。
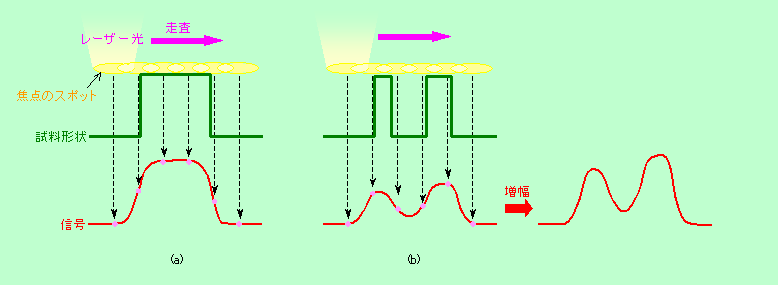
図11 レーザー顕微鏡で光のスポットよりも小さい物を観察する
図11を見てください。緑の線で示したような形状の試料をレーザー光のスポットが走査して行きます。(a)のようにスポット径よりも大きな凸部がある場合、スポット全体が凸部に乗りますから、十分な信号強度で観察できます。これに対して(b)のようにスポット径よりも小さい凹凸がある場合、スポットが凸部からはみ出した分信号強度は弱くなり、凹部に来た時も一部が凸部にかかりますから信号はゼロにはなりません。その結果、赤線で示したように、観察される形状はかなりダレた形になってしまいます。それでも凹凸があることはちゃんと認識できるわけですから、その意味では、光の波長より小さい構造もある程度は見えています。しかも、最終的にはコンピューター処理で画像にするのですから、その時に信号を増幅してやれば(さらにエッジを強調するなどの処理もできます)、かなり鮮明な画像を得ることができます。このような理由から、レーザー顕微鏡では普通の光学顕微鏡よりも一桁上の数千倍の倍率が得られるのです。
雑科学ホーム
hr-inoueホーム