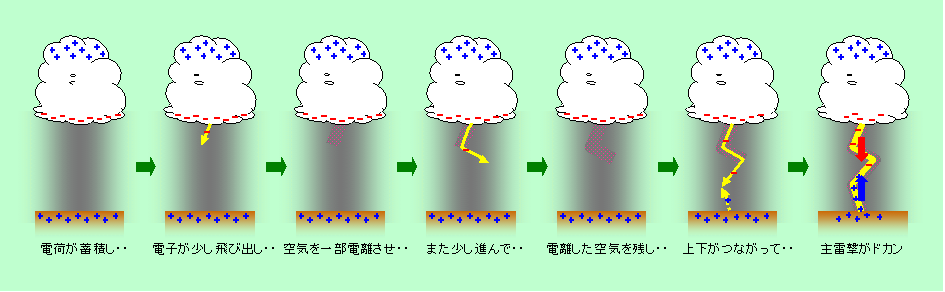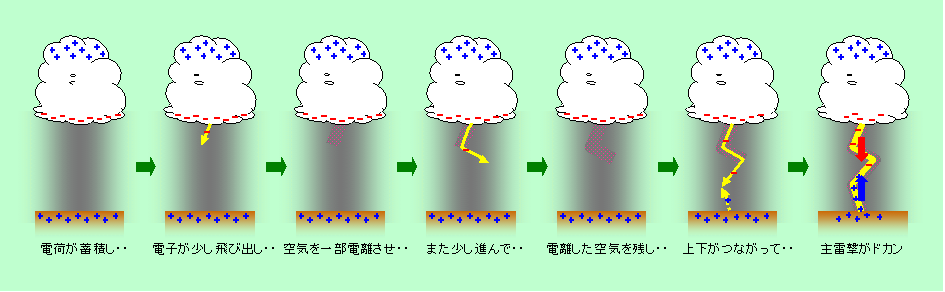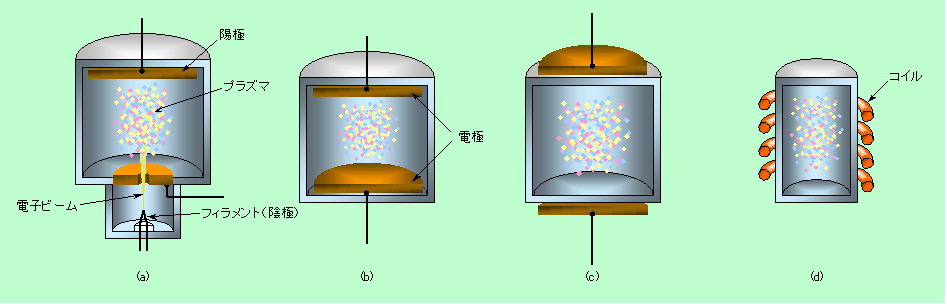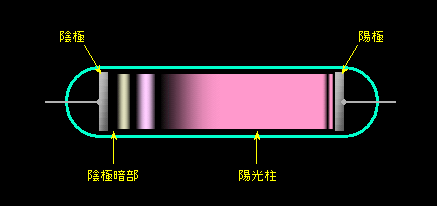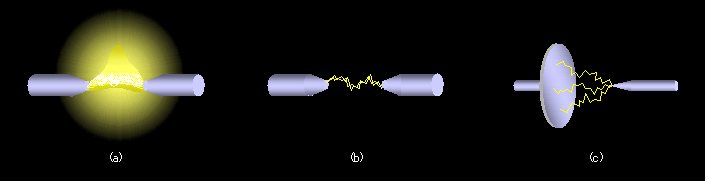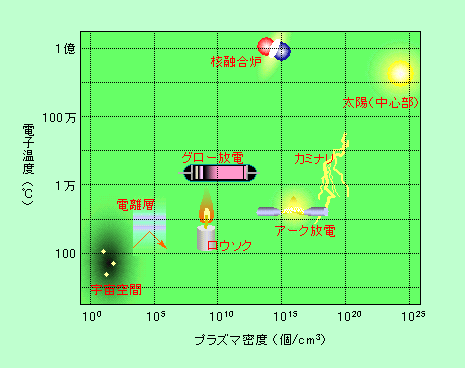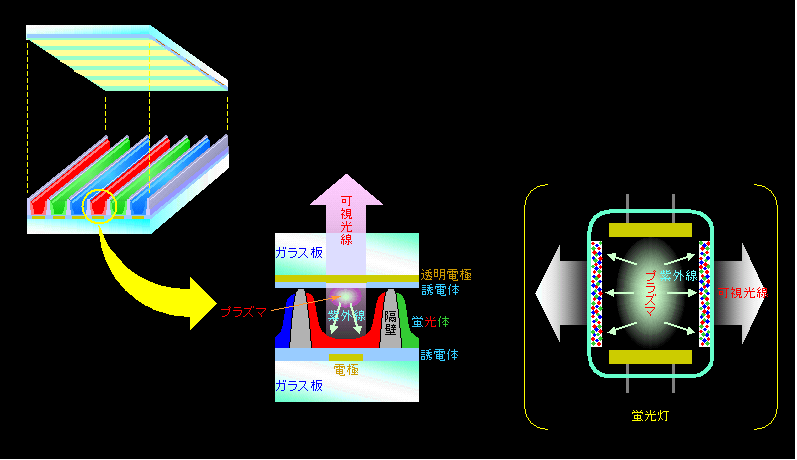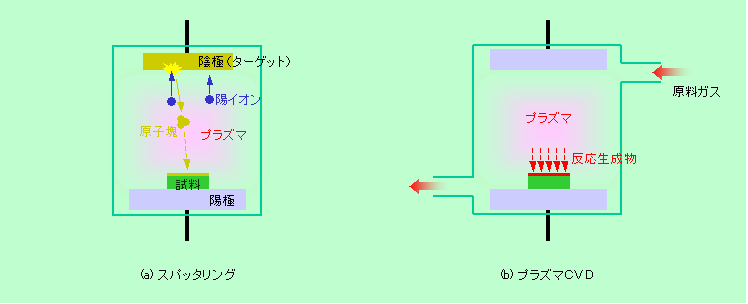雑科学ホーム
hr-inoueホーム
● プラズマの話 ●
第4の状態「プラズマ」
辞書で「プラズマ(Plasma)」という言葉を調べると、いくつかの意味が出て来ます。「ガスが電離して正負に帯電した粒子が混合した状態」、「血漿(血液の中の液体成分)」、「細胞の原形質(細胞を構成する物質)」。その他、心霊現象なんかにもちょくちょく出て来ますが、ここで取り上げるのは一番最初の「ガスが電離して正負に帯電した粒子が混合した状態」です(ただし、必ずしも全部の粒子がイオンや電子である必要はなく、中性の原子や分子が含まれていてもかまいません)。原子が電離してイオンになっている状態と言えば、例えば食塩(塩化ナトリウム)が水に溶けてナトリウムイオンと塩素イオンになっているように、溶液の中でも普通に見られますが、これはプラズマとは呼びません。溶液の場合には、電子は裸でいるのではなくて特定の原子にくっついてマイナスイオンとなっており、そのマイナスイオンやプラスイオンは溶媒分子に取り囲まれておとなしくしていますから、イオンや電子が単独で激しく飛び回っているプラズマとは状態が全く違うのです。
固体を加熱すると溶けて液体になり、液体を加熱すると蒸発して気体になります。そして気体をさらに加熱すると、やがては分子がばらばらになり、電子が剥ぎ取られてプラズマ状態へと変化します。その意味で、プラズマというのは「固体」「液体」「気体」に次ぐ第4の状態と言えるかもしれません(確かにプラズマになる時には「沸点」や「融点」に相当するはっきりした境目はありませんが、それを言うならば
超臨界状態の物質には沸点はないわけですから・・・・・)。
プラズマ中の粒子は電気を帯びていますから、電場や磁場に敏感に反応します。その意味でも、プラズマは他の3つの状態とは大きく違っていると言えます。また、プラズマの中では粒子が激しく動いていますから、そこそこに密度が高ければ互いに衝突して発光する場合が多くなります。と言うよりも、光を放つほどに熱エネルギーや電気エネルギーを注ぎ込んだ気体というのは、だいたい既にプラズマ状態になっているのです。
ネット上で「プラズマ」を検索すると、最近では「プラズマテレビ」関係のヒットが圧倒的に多いようです。世間一般でプラズマと言えば、今は「テレビ」ということになるのでしょうね。しかし、「プラズマ」は何もテレビに限ったものではありませんし、決して特殊なものでもありません。カミナリにもプラズマがからんでいますし、蛍光灯の中にもプラズマはあります。宇宙全体を見渡してみれば、太陽などの恒星はみんなプラズマの塊みたいなものですし、星と星との間の空間にも、薄いながらたくさんのプラズマがありますから、特殊などころか、宇宙のほとんどの物質はプラズマ状態にある、と言ってもいいくらいです。宇宙的に見れば、電子は原子核の束縛を振り切って自由に飛び回っているのが普通なのであって、地球上のような非常に「特殊な」環境でのみ、おとなしく原子の中に収まっている、と言うことができるのです。
自然界のプラズマ
宇宙規模で考えた時に最も目に付くプラズマと言えば、太陽を初めとする恒星でしょう。太陽の温度は中心部で1500万度、表面でも6000度。このような高温の中で水素やヘリウムなどのガスが電離して、巨大なプラズマの塊を作っています。一方で星と星の間の空間は圧力が極端に低い(1気圧の1000兆分の1以下の)世界で、物質はガス状になっていますが、ここに恒星から飛び出して来た粒子や電磁波が衝突するとガスは電離して、やはりプラズマ状態になります。星も星間もプラズマ。宇宙ではどっちを向いてもプラズマだらけなのです。
次に、目を地球に移してみましょう。地球上には太陽や宇宙空間から様々な放射線や電荷を帯びた粒子(これらを宇宙線と呼びます)が降り注いでいますが、これらがぶつかると大気中の分子が電離します。とは言っても、そのせいで地球の大気が全部プラズマになってしまうようなことはありません。地表付近では厚い大気の層を通り抜ける間に宇宙線が大幅に弱くなっていますし、かろうじて電離を起こさせても、ガス分子の数が多い(つまり圧力が高い)ので、すぐにプラスイオンが近くの電子を捕まえて電離前の状態に戻ってしまうからです。しかし上空に行くにつれて宇宙線は強くなって来ますし、大気が薄い分、一旦電離すればプラスイオンと電子は遠くに飛び去ってしまいますから、安定な電離状態が維持できるようになります。つまり、高く昇れば昇るほど、電離する比率は高まるのです。ただし、あまり高く昇ると大気自体が薄くなり過ぎて、トータルのイオンや電子の数は減ってしまいますから、はっきりとしたプラズマが存在する領域は地上80km〜500kmあたり、ということになります。これが電離層です。電離層は電気を通しますので、電磁波を反射する性質があります。このおかげで地球の裏側のラジオ放送が聞ける、ということはご存知でしょう。
もう一つ、地球上で有名なプラズマと言えば「カミナリ」でしょう。雲の中、あるいは雲と地上の間に電気が溜まり、プラスとマイナスの電荷が一気に結合(放電)してドカンと行くのがカミナリですが、その電圧は数億ボルト、電流は数万アンペアもあります。このような強烈な電圧で加速された電子は、恐ろしく激しい勢いで空気の分子に衝突し、温度も瞬間的に数万度に達しますから、もう完全にプラズマ状態。あのピカッと光る稲妻は、このプラズマの中の激しい衝突で分子やイオンが発光したものなのです(
発光の話参照)。
ところで、空気は普通は電気を通しませんから、別々に蓄えられたプラスとマイナスの電荷は、そのままでは一緒になることはできません。一緒になるためには(つまりカミナリが落ちるためには)、途中の空気を電離させて、電気の通り道をつける必要があります。カミナリの場合、蓄えられた電荷が作る強い電場が、空気を電離させる原動力になります。とは言っても、いっぺんに空気を電離させて放電するわけではありません。一瞬に思える短い時間(1/1000秒ぐらい)に、図1のようなけっこう複雑な過程を経ているのです。
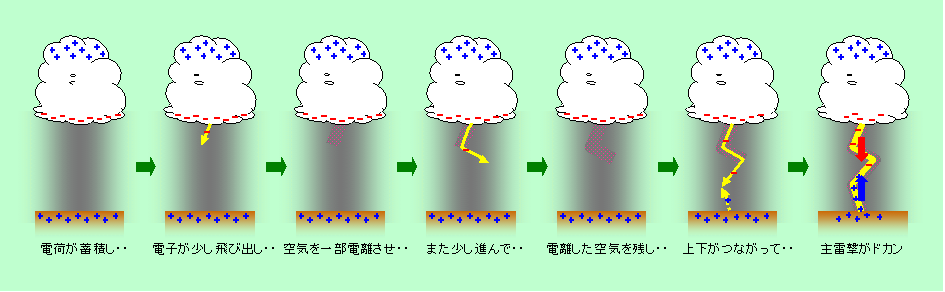
図1 カミナリはちょっとずつ落ちる
まず、雲の中の電子が、空気の中で特に通りやすそうなところを選んでちょこっと進みます。通りやすそうなところというのは、例えば宇宙線の影響で空気がほんのわずか電離した部分などです。この時に電子は途中の空気をさらに電離させますから、一度通過した通り道はプラズマ化して、ますます電気を通しやすい状態になっています。そのため2回目のトライでは、1回目に通ったルートはそのまま利用し、そこから先に進む段階で、また新しいルートを開拓します。こうして何回もトライを繰り返し、そのたびに折れ曲がりながら少しずつルートを伸ばして行くのです。一方地上の方でも、プラスの電荷がルートを探して上に向かいます。そして上からのルートと下からのルートがつながった瞬間、完成された導線を通って大電流が流れ、プラスとマイナスが一気に結合します(主雷撃)。稲妻のあの独特の形は、このようにして作られたものなのです。
プラズマを作る
宇宙ではプラズマ状態が普通、と言っても、穏やかな地球上でプラズマを作るとなれば、それなりの細工が必要です。一番簡単な方法は、気体をどんどん加熱して行くことでしょう。加熱によってエネルギーが与えられて電子が剥ぎ取られるのです。この時、プラスイオンと電子とは互いに引き合ってくっ付こうとしますが、熱エネルギー、つまりイオンや電子の飛び回る勢いが十分にあれば、引力を振り切って電離した状態を保つことができます(厳密に言えば、電離したり元に戻ったりがあちらこちらで繰り返され、全体としてあるバランス状態になっています)。ちょっとしたプラズマを作るだけなら、太陽ほどの高温はもちろん必要ありません。数1000℃もあれば十分で、身近なところではロウソクやガスバーナーの炎があります。これらの炎の中では、燃料の気体が熱せられて酸素と反応し(つまり燃えて)、熱と光を出しているわけですが、ここで一部の成分が電離してプラズマ状態になっているのです。
このように、熱を使ってプラズマを作るのは確かに簡単ではありますが、あまり効率のよい方法ではありません。1000℃を超える高温が必要な一方で、電離する割合は大したことはなく、できたプラズマの使い勝手もよいとは言えないのです。そこで普通は電気エネルギー(電場)の力を借ります。その基本はカミナリと同じで、電場によって加速された電子を別の原子や分子にぶつけて、その衝撃で電離させるのです。
電気的にプラズマを作る最も単純な方法は、図2(a)のように電流を流して加熱したフィラメントから出て来る電子(熱電子)を使うもので、
電子顕微鏡やブラウン管の電子銃と原理的には同じです。ただ、電子銃の目的が電子ビームそのものを使うことにあるのに対して、ここでは電子を使ってプラズマをを作ることが目的ですから、電子銃の先にはガスの入った部屋が用意されています。この部屋の中で電子がガス分子にぶつかって電離させ、飛び出した電子がまた電場で加速されて次の分子にぶつかり、そこから出て来た電子がまたまた次のガス分子にぶつかり・・・・、ということを繰り返し、多量の電子やイオンが作られるのです。部屋の中のガスの圧力が高いと(つまり分子がたくさんあると)、電子が十分に加速される前にぶつかってしまって効率よく電離が進みませんし、電離層のところでも書いたように、できたプラスイオンと電子が出会って元に戻ってしまう確率も高くなりますから、普通は部屋の中の圧力は低くしてあります。
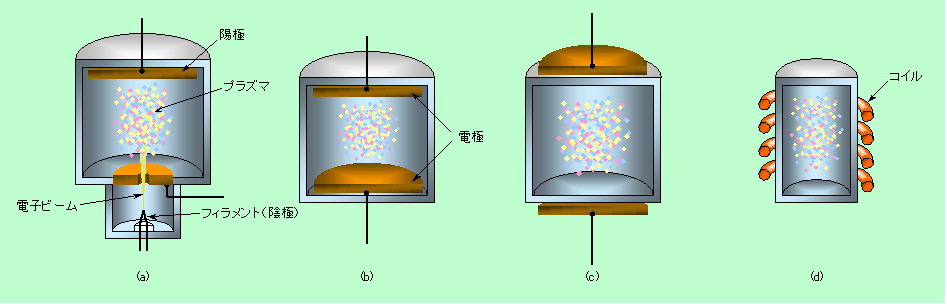
図2 電場を使ったプラズマ作り
図2(a)の方法では、電子だけでなくフィラメントそのものの材料(普通はタングステンなど)も多少なりとも蒸発して飛び出して来るので、プラズマが汚れる、という問題があります。そこで、加熱をしないで、電極の間に高い電圧をかけることでカミナリのような放電を起こさせる方法もあります(図2(b))。この場合、カミナリのようにものすごく高い電圧をかければ電極から強引に電子を引っ張り出すこともできなくはありませんが、普通はそこまでの電圧はかけません。となると電極からの電子の供給はありませんから、最初に加速する電子はどこから調達するのでしょうか。実は、前にも書いたように、地上には絶えず宇宙線が降り注いでおり、その影響でほんのわずかですがガスが電離しているのです。このわずかな電子を電場によって加速してガス分子にぶつけることができれば、あとはフィラメントを使う方法と同じようにネズミ算式に電離が進みます。また、重くて動きの鈍いプラスイオンもある程度は加速されて電極(陰極)に届き、ここで陰極から電子を叩き出しますので、これが連続的な電子の供給源となります。
電場として直流ではなくて交流を使う方法もあります。この場合、電子は一方向に飛ぶのではなく、電場の方向が切り替わるにつれて行ったり来たり、激しく往復します。これだと十分に加速される前に方向が反転してしまうので、電子の速度が不足してしまうのではないか、と思われるかもしれませんが、心配は無用です。ちょっと例を挙げてみましょう。電極間の距離が10cmで、その間に10kVの交流電圧をかけたとします。交流の周波数をかなり高めの1ギガヘルツ(1,000,000,000 Hz)にしても、電圧の方向が切り替わる僅か0.000000001秒の間に、電子は秒速17000kmにも加速されるのです(途中で他の粒子にぶつからなければ)。この速度の電子は、よく使われるエレクトロンボルト(eV)の単位では800eV以上に相当し、原子や分子から電子を剥ぎ取るには十分なエネルギーなのです。なお、交流の場合は直流のように電極に蓄えられた電荷を放出するわけではないのですが、プラズマを通して電流を流すことをやはり「放電」と呼んでいます。
図2(b)の方法では電極を加熱しないので、電極の材料が飛び出してプラズマを汚す可能性は低くなりますが、それでもイオンが電極にぶつかって電極材料を叩き出したりすること(スパッタリング)は起こり得ます。これに対して図2(c)や(d)のように、完全に電極を外に出してしまう方法もあります。この場合、電極とプラズマの間を電子やイオンが通過することはできませんから、直流を流すのは無理で、交流による放電になります。(c)はストレートに電極間に交流電場をかける方法、(d)はコイルに交流を流すことで内部に電磁誘導による電場(誘導電場)を発生させる方法で、いずれもプラズマを使った実験や分析に広く使われています。
どのパターンの場合でも、プラズマを発生しやすくするために、圧力を数分の1〜数百分の1気圧に下げるのが普通です。しかし、カミナリの例にも見られるように、エネルギーを十分に大きくしてやれば大気圧でも放電は起こり、プラズマが発生しますので、低圧というのは絶対に必要な条件ではありません。
放電のいろいろ
放電によるプラズマ生成の話が出たついでに、放電についても少し触れておきましょう。主なものとして、グロー放電、アーク放電、火花放電、コロナ放電、などがあります。
グロー放電
発光を意味する「グロー(glow)」という言葉がそのまま付いた放電です。「グロー」という言葉には、「白熱光」というような激しい鮮やかな発光というニュアンスが含まれていますが、実際のグロ−放電は火花などを伴わない、どちらかと言うとおとなしい部類に入る放電です。
グロー放電は、普通は図2(b)の形の装置でよく見られます。内部の圧力は1mmHgぐらいにするのが一般的で、この状態で電極間に数百〜数キロボルトぐらいの直流電圧をかけると現れます。放電の状態は一様ではなくて、図3のように光り方の違ういくつかの部分に分かれています。
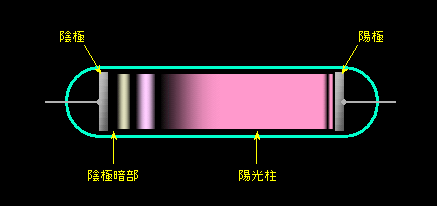
図3 典型的な直流グロー放電
陽極側の明るく光る部分は陽光柱と呼ばれ、イオンや電子がたくさんある、つまりプラズマになっている部分です。ここからプラスイオンが電場に沿って移動し、陰極にぶつかることで、陰極から電子が叩き出されます。叩き出された電子は電場によって加速されながら陽極に向かいますが、初めのうちはまだ十分な速度になっていないので、ガス分子にぶつかっても電離させることができず、発光も起こりません。このような電子の助走領域に当たるのが、負極附近の暗い部分です。陽光柱の部分には電気を運ぶ粒子がたくさんあって導電性が高いですから、「導体の中には電場はできない」、という理屈に従って、陽光柱の内部にはほとんど電場はかかりません。電極間にかけた電圧はほとんどが陰極附近の暗い部分に集中することになります。そのため、電極の間隔を変えても陽光柱が伸び縮みするだけで、陰極附近は変化しません。逆に電圧を変化させると、電子の加速に必要な距離が変わりますから、暗部の長さが変わり、暗部と陽光柱の比率が変化することになります。グロー放電にはその他にも細かい構造が現れることが多いのですが、ここでは省略します。
また、グロー放電は交流でも起こすことができます。図2(b)〜(d)のどの形でも可能で、この場合はもちろん図3のような左右非対称の形にはなりませんが、やはり火花などを伴わない、安定したプラズマができます。蛍光灯などはその典型ですね。
アーク放電
直流グロー放電では陰極からの電子の放出はプラスイオンの衝撃によるものでしたが、電流が増して陰極の温度が上がって来ると、陰極からどんどん電子(熱電子)が出るようになります。こうなるとますます大きな電流が流れるようになり、アーク放電へと移って行きます。アーク放電では電子が多量に供給されるので、プラズマ部分の導電性が高く、全体がグロー放電の陽光柱のような状態になります。そのため電流が大きい反面、電圧は低く、圧力が高くても(大気圧でも)放電します。
アーク放電の特徴の一つは、その強烈な火花にあります(図4(a))。電極と電極の間を、場合によってはまともに見ていられないぐらい強烈な光を発して、弧を描くように火花が飛びます。火花が弧を描くのは、プラズマ周辺が高温になり空気が膨張して上昇気流が起こるからで、ここから、アーク(arch=弧)放電という呼び名が付けられました。乾電池の両極に炭素棒や鉛筆の芯を1本ずつつないで接近させると火花が飛ぶ、という実験がありますが、これも一種のアーク放電です。やり方によっては鉄板に孔が開くぐらいのパワーが出ますし、目が眩むような閃光が飛びますから、電源が乾電池だからといって侮ってはいけません。サングラスの使用や、やけど、火災への注意など、十分に安全管理が必要です。(危険性という点では、どちらかと言うと高電圧よりも大電流、交流よりも直流の方が怖い、ということは頭に入れておいてください)
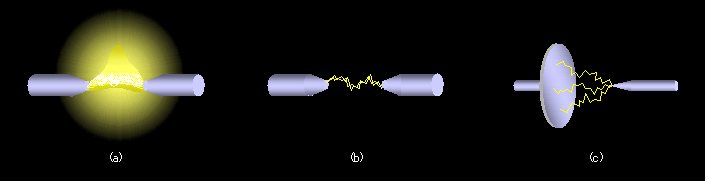
図4 放電いろいろ
火花放電
グロー放電やアーク放電は連続的な放電ですが、瞬間的にピカッと光っておしまい、という放電もあります。連続放電になる前の段階と言えるもので、例えば、接近して置いた電極間の電圧をだんだん上げて行くと最終的には連続的なアーク放電になるのですが、その手前で、パチンと火花が飛ぶことがあります。これが火花放電で、その最たるものがカミナリです。電場で加速された電子が気体分子にぶつかって電離させる、という点ではグロー放電やアーク放電と変わりありませんが、それが単発的なのです(もちろん、電圧をかけ続ければ、単発の火花を立て続けに飛ばすことはできます)。服を脱ぐ時や、ドアノブに触れようとした瞬間にパチパチと飛ぶ静電気の火花も、一種の火花放電ですね(図4(b))。
コロナ放電
電極の一方が針状や線状になっていると、その周辺には強い電場が集中します。そのため平面どうしの場合と比べて、針の先や細い線からは放電が起こりやすくなります。このような放電を特にコロナ放電と呼びます(図4(c))。カミナリに対する避雷針も、どこでも適当に落ちられては困るので、針の先へのコロナ放電を優先的に起こさせていると言えます。
コロナ放電は電圧をそれほど上げなくても大気中で起こすことができるので、手軽に電子やイオンを発生させるのに有効です。コピー機やレーザービームプリンターでは、帯電した感光ドラムにトナー(黒やカラーの粉)を吸い付けて文字や絵を作るのですが、この感光ドラムを帯電させるのに、ワイヤー状の電極によるコロナ放電が使われています。また、空気中の塵を帯電させて電極に引き付けて除去したり、放電で発生するオゾンで臭いの元の有機物や細菌などを分解するということを謳い文句にした空気清浄機が売られたりもしています(効果の程はノーコメントです)。
プラズマの温度
気体の温度を上げて行くと電離を起こしてプラズマになるということから、プラズマは非常に高温なのではないか、と予想されます。確かに、加熱するだけで作ったプラズマは高温なのですが、それでは電場を使って作ったプラズマはどうでしょうか。
プラズマが熱いのか冷たいのかを考える前に、そもそも「温度」とはいったい何なのか、ということをはっきりさせておかなければなりません。簡単に言えば、「温度」とは、物質を構成している粒子(原子や分子、イオン)の運動の激しさを表す尺度です。構成粒子が高速で飛び回っていたり激しく振動したりしていれば温度は高く、おとなしくしていれば温度は低い、ということです。この時、たくさんの粒子の運動の状態はそれぞれ違っていますから、1個1個の粒子に注目するのではなくて、全体としての平均を見ることになります。とは言っても、気体の中では粒子は互いに衝突を繰り返して速度(運動エネルギー)をやり取りしますし、液体や固体の中では原子や分子どうしの結合を通して振動が伝わりますから、実際には極端に速い粒子や極端に遅い粒子はほとんどなくなって、平均値を中心にした一定の分布に落ち着いています。いわゆる「熱平衡」という状態です。
プラズマの中でも、アーク放電でできるプラズマや、気体を加熱して作ったプラズマは、この熱平衡に近い状態にあり、「熱平衡プラズマ」とか「高温プラズマ」などと呼ばれます。圧力が高いために電子やイオンや中性の原子などの衝突が頻繁に起こり、全体が同じような状態に平均化されるのです。ですからこれらのプラズマの温度は普通の気体などの温度と感覚的に近く、例えばアーク放電の温度は数千℃です。
これに対して、グロー放電などの低圧のプラズマでは事情がかなり違います。まず電場によって加速される電子やイオンですが、当然ながら軽い電子は強烈に加速されるのに対して、重いイオンはあまり高速にはならず、スピードは電子の数千分の1です。それでも運動エネルギーという点では、同じ電場で加速された電子とイオンで違いはありませんので(遅くても重いのでエネルギーは大きい)、最初の段階では温度は同じと言えます。問題は、電荷を持っていない中性の原子や分子があることです。これらは当然、電場では加速されませんから、部屋が25℃ならば25℃のままで、高速で飛び回る電子やイオンの中で、もたもたしています。圧力が低いので粒子どうしの衝突はそれほど頻繁ではありませんが、それでも直径の大きなイオンはかなりの確率でもたもたしている中性粒子にぶつかって速度を失いますので、やがては低いエネルギー、つまり低い温度にならされてしまいます。これに対して、直径が何桁も小さい電子の方は中性粒子にぶつかってエネルギーを失うことは滅多にありませんから、エネルギーは大きいまま、つまり温度は高いままです。その結果、低圧のプラズマの中では、電子の温度は高く、イオンや原子の温度は低い、というアンバランスな状態ができるのです。これが「非平衡プラズマ」とか「低温プラズマ」と呼ばれる状態です。このような状況ですから、低圧のプラズマでは一つの温度の値で全体を表すことはできません。電子と、その他の粒子とで、別々に温度を示してやらなければならないのです。例えば、グロー放電で1Vの電圧で加速された電子は10000℃ぐらいの温度に相当する速度を持っているのに対して、イオンや原子の温度はずっと低く、数十℃しかない場合もあります。
ところで、たとえ電子だけとは言え、10000℃もの高温になると蛍光灯のガラス管を溶かしてしまうようなことはないのでしょうか。このことは、「温度」と「熱」とは違う、ということを理解すれば解決します。「熱」とは、温度の高い物から温度の低い物に流れ込むエネルギーのことですが、その量は温度だけでは決まりません。動きが活発な原子やイオンなどの粒子の数も重要なのです。つまり、個々の粒子のエネルギーと粒子の数とを掛け合わせたものが、全体の熱エネルギーなのです。蛍光灯の中の1cm3当たりの電子の数(これをプラズマ密度と言います)は10億個(109個)程度ですが、ガラスの中の原子の数は1cm3当たり1023個。単純に計算しても、電子の持っている熱エネルギーはガラスに接触すると100兆分の1に薄められてしまうことになります。これはもう検出不可能ですね。蛍光灯が暖かくなっているのは高温の電子によるのではなくて、加熱された電極と、温度の低い中性粒子の熱によるのです。
プラズマの温度に関して、もっと極端な例を挙げましょう。太陽で起こっている核融合と同じような現象を地上で起こして莫大なエネルギーを取り出そうという核融合炉です。核融合を起こすのに必要なプラズマの温度は何と1億℃以上。ちょっと想像がつきませんね。このような超高温のプラズマを閉じ込めるわけですが、圧力の方は10万分の1気圧もありませんので(プラズマ密度で1015個/cm3ぐらい)、蛍光灯と同じように、容器が溶けてしまう心配はありません。と言うよりも、肝心のプラズマの方が容器のために冷やされて温度が下がってしまいますから、それを防ぐために磁場などで閉じ込めて、プラズマが容器に触れないようにしています。ちなみに、太陽の中心温度は1500万℃で、核融合炉のプラズマよりも低いですが、圧力が2500億気圧(プラズマ密度で1025個/cm3)とケタ外れに高くなっています。このような圧力を容器内に作るのはさすがに無理ですから、核融合炉では温度を上げることでエネルギーを稼いでいるのです。
プラズマの温度と、そのついでにプラズマ密度の話をして来ましたが、ここでちょっと不思議なことに気が付きませんか? そうです。その値の範囲がムチャクチャに広いのです。主なプラズマの密度と温度(電子密度)をプロットすると、およそ図5のようになります。
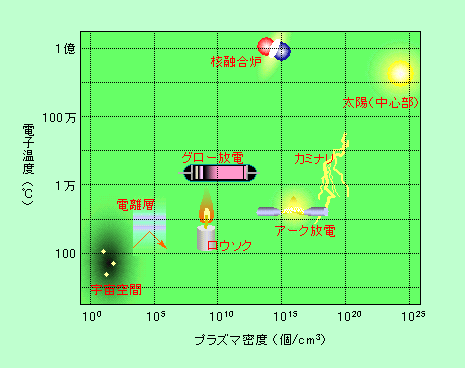
図5 広範囲に広がるプラズマの密度と温度
実に温度で8桁以上、密度では25桁にも広がっていることがわかります。これだけ広い範囲にわたっているにもかかわらず、プラズマはプラズマ。似たような性質を示す、同類の状態なのです。しかし普通の物質ではこうは行きません。例えば水は0℃以下では固体に、100℃以上では気体に変化しますし(もちろん1気圧での話です)、金属や塩類でも数千℃を超えると気体になってしまいます。図の下の方の狭い領域で、バタバタと状態が変化するわけです。密度で見ても同様で、1019以下では液体や固体ではあり得ず、気体状態ですが、逆に1023以上の領域では、気体の状態でいることはまずありません。これらと比べてプラズマがいかに様々な環境で存在できるかがわかりますね。
宇宙の環境は、誕生初期の超高温の状態から大きく変わりました。このように環境が激変しても、大部分の物質がプラズマ状態であることに変わりはありません。先に、宇宙では星も星間もプラズマだらけ、と書きましたが、この状態は宇宙誕生初期から今に至るまで、そしてこれからも続くのでしょう。
プラズマの利用
蛍光灯
プラズマの利用例として最も身近な物の一つは、再三登場している蛍光灯でしょう。ちょっとだけ水銀蒸気を含んだ低圧の管の中で放電を起こしてプラズマを作り、そこから出て来る紫外線を管の内壁に塗られた蛍光塗料に当てて可視光線に変えるのが蛍光灯です(
発光の話参照)。蛍光灯では加熱した電極から直接電子が飛び出しますので、蛍光灯の放電をアーク放電に分類する人もいるようですが、低圧、非平衡、という条件を考えれば、やはりグロー放電と言うべきでしょう。
蛍光塗料を塗らないで使えば紫外線を発するランプになります。また、普通の蛍光灯は赤、緑、青に発光する3種類の蛍光物質を一緒に塗ってありますが、蛍光物質の種類を適当に選べば、様々な色の蛍光管を作ることができます。さらに、内部に封入するガスをネオンにすれば赤色に、窒素にすればピンクに、というふうに、ガスの種類によっても色を変えることができ、これらをまとめて(内部のガスはネオンとは限りませんが)ネオン管と呼んでいます。最近は新しい光、
発光ダイオードも普及して来ましたが、夜の街の広告や看板ではまだまだネオンサインは健在ですね。
ついでに触れておくと、パソコンやテレビの液晶パネルを背後から照らしているのも蛍光灯です(最近では
発光ダイオードや
EL方式のものもありますが)。ただし、普通の蛍光灯が電極を加熱して電子を飛び出させる方式であるのに対して、加熱しないで電界によって電子を引き出す方式が使われており、冷陰極蛍光管と呼ばれます。普通の蛍光灯の電極表面には電子を放出しやすくするための物質が塗られていて、これが点灯時の加熱によって脱落して行くことで寿命が来るのですが、冷陰極蛍光管にはその加熱がありません。その分、当然寿命は長く、また予熱が要らないので点灯が速いというメリットもあって、光量では多少劣るものの、頻繁にON、OFFする液晶のバックライトにはうってつけなのです。
プラズマディスプレイ
液晶ディスプレイにも蛍光灯が使われているわけですが、蛍光灯の仕組みをストレートに利用したのが、液晶のライバルである
プラズマディスプレイです。図6にその簡単な構造を示しました。図のパネルは仕切りが縦方向にしかありませんが、狙った位置の上隣や下隣の蛍光体を光らせてしまうことを防ぐために、横方向にも仕切りを付けた構造になっているものもあります。
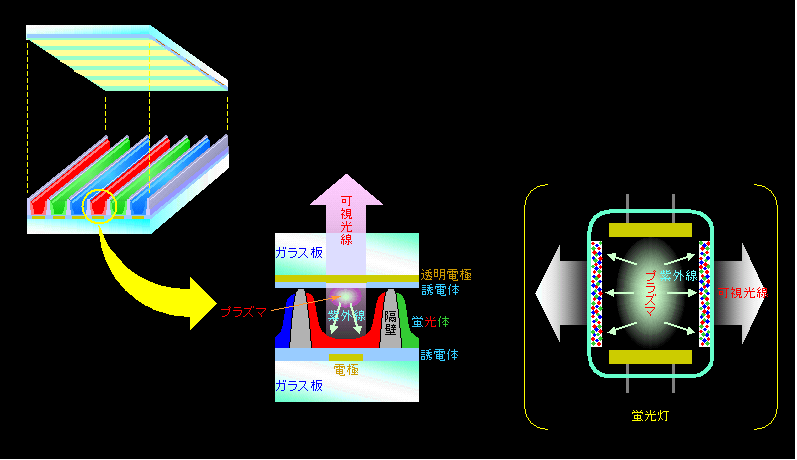
図6 プラズマディスプレイは微細な蛍光灯の集団
隔壁(リブ)と呼ばれる仕切りで区切られた小部屋の中にはネオンやキセノンなどのガスが封入されていて、赤、緑、青の蛍光体が塗ってあり、これを挟む上下のガラス板には電極が付けられています。電極に電圧をかけると小部屋の中で放電が起こってプラズマができ、プラズマから発生した紫外線を受けて蛍光体から可視光線が出るのです。図の右に蛍光灯の模式図も載せておきましたが、1個1個の小部屋はまさに蛍光灯そのものであることがわかると思います。
初期のころ、某メーカーではプラズマディスプレイ(プラズマテレビ)のことを「ガス放電テレビ」と呼んでいました。確かにガスを封入して放電させるのですが、世間一般では「ガス」=「気体」という考え方はなくて、「ガス」と言えば都市ガスやプロパンガスのことですから、「ガス管はどこにつなぐのですか?」という質問が出てもしかたのないネーミングですね。ちなみに、うちの娘は小学生のころ、「イナズマテレビ」と呼んでいました。知ってか知らずか、原理的にはまんざら違ってはいませんが・・・・。
加工・製膜への利用
民生用の用途にプラズマを直接使う例は蛍光灯やプラズマテレビ以外ではあまりありませんが、プラズマを使って細工された製品は身の回りにいくらでもあります。その代表的な例は半導体素子でしょう。シリコンなどの基盤に微細な回路を刻んで行くのに、プラズマはなくてはならない道具です。詳しいことは
微細加工の話に書いていますが、要するにプラズマの中に含まれる活性の高いイオンで機械的に、あるいは化学的に試料を削って行くのです。
酸素ガスを使ったプラズマアッシングという技法も、広い意味では加工法の一つです。アッシング(Ashing)とは、灰(Ash)化する、という意味で、主として有機物を酸素で燃やして取り除くことです。半導体を加工する時に使ったフォトレジストなどの有機物をきれいサッパリ除いてしまうのによく使われます。
このように削り取る働きだけではありません。試料の上に薄い膜を付けるのにもプラズマが活躍します。例えば、スパッタリングという方法では、膜にしたい物質(いろいろな金属や炭素材など)を陰極に使って(これをターゲットと言います)窒素やアルゴンなどのガスで直流グロー放電を起こさせます。発生したプラスイオンが陰極のターゲットに衝突してそこから微小な原子の塊を叩き出し、この原子の塊が対向して置かれた試料の上に膜として積もるのです(図7(a))。また、化学蒸着(CVD =
Chemical
Vapor
Deposition)という方法では、ガス状の原料に化学反応を起こさせて発生した固体を基板上に積もらせますが、その反応を起こさせるのに放電によるプラズマを利用する場合があります(図7(b))。シランガス(SiH
4)を高周波グロー放電で分解してアモルファスシリコン(Si)を堆積させる方法もプラズマCVDの一種です(
修士論文参照)。
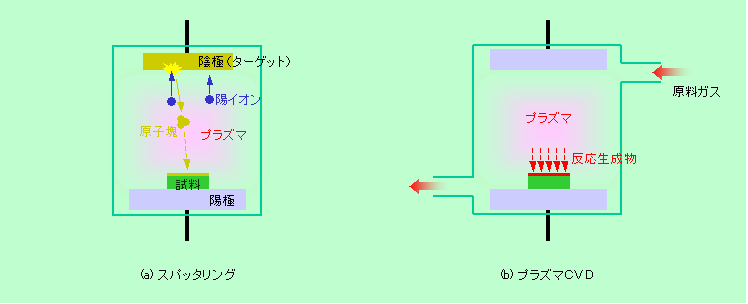
図7 プラズマを使って膜を作る方法
分析への利用
モノを作るだけでなく、分析にもプラズマは使われます。誘導結合プラズマ原子発光分光法(ICPAES = Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy)は、霧状にした液体試料に高周波をかけてプラズマ化し、微量に含まれる原子が発する光を捕まえて分析する装置です。元素の種類によっては濃度10億分の1(1ppb)の微量成分まで定量できる高感度分析法です。同じように試料を高周波プラズマでイオン化して質量分析するICPMSという装置もあります。
オモチャ・展示物
昔はプラズマをオモチャにするなどとても不可能でしたが、最近では安全性を確保する技術が格段に進歩して、簡単に手に入るようになって来ました。直径20cmぐらいのガラス球の中で、中心から放射状にイナズマが飛ぶように光が走る展示物を見たことがある人も多いでしょう。これと同じ物が、プラズマボールなどの名前で市販されるようになっています。
これは高周波放電(火花放電)を利用した物で、球の内部にアルゴンなどの低圧ガスを閉じ込め、中心に置かれた電極に2000V以上の高周波電圧がかかるようになっています。ガラス球の側には中心とは反対の極が発生しますから、その間のガスがプラズマ化し、火花が飛ぶのです。電流が流れる過程は図1のカミナリと同じで、ちょっとづつガスを電離させながらルートを探しますから、小刻みに折れ曲がるダイナミックな動きが見られます。このプラズマボールの面白いところは、ガラス球に手を近付けると火花が寄って来ることです。それまで全く球対称であった外側の電極が手を近づけることで変化し、手の部分に電場が集中する形になったためで、ちょうど針先からのコロナ放電のような状況になったと思えばいいでしょう。この時、微弱な電流が外に漏れ出し、手先から体の表面を通って流れ出ています。同じように手を近づけても人によって火花の形の変化の仕方が違うのは、体の表面の導電性が人それぞれ違うためでしょう(着ている服や靴の影響もあるかもしれません)。汗をかきやすい人とそうでない人では導電性はかなり違いますから、火花の寄り方も変わるのです。また、金属製の物を手に持って近付けるともっと極端に火花が集まり、球と金属との間で火花が飛ぶこともあります。指輪をしている場合も同じで、ちょっとしたショックを受けるかもしれませんから注意しましょう。
雑科学ホーム
hr-inoueホーム