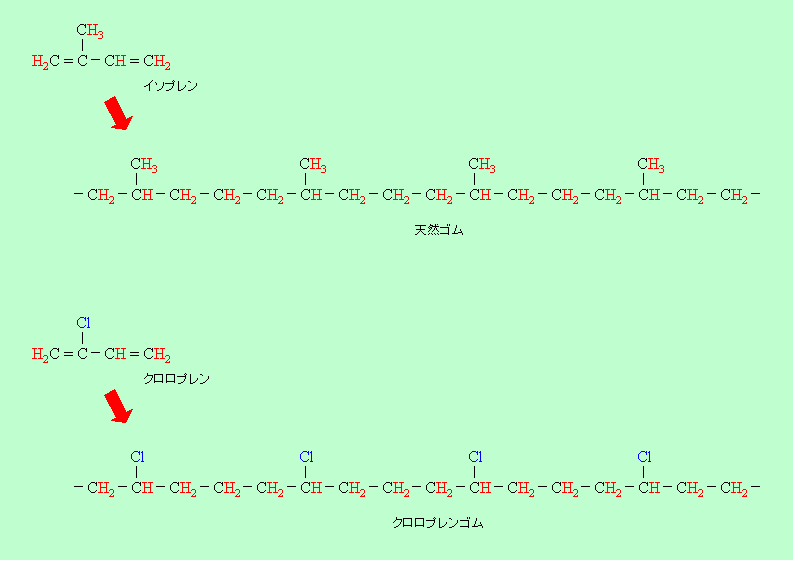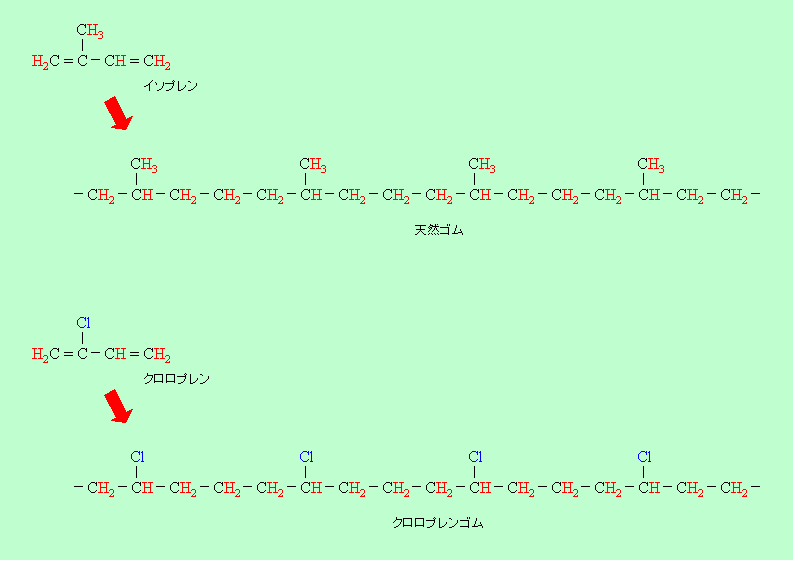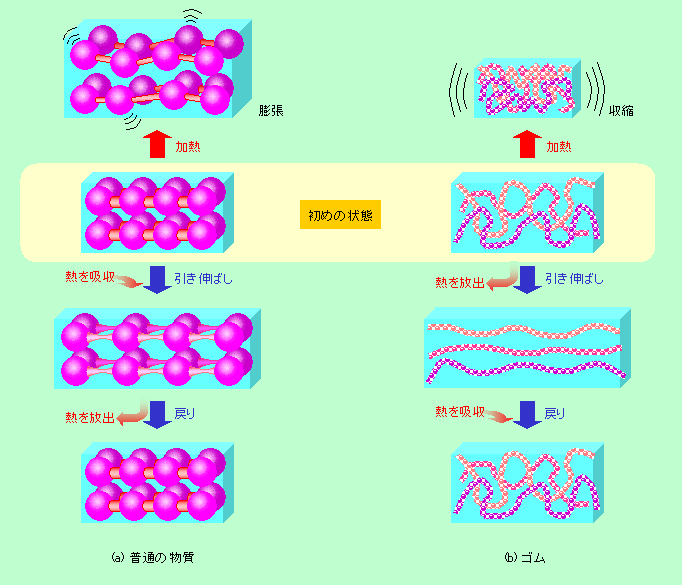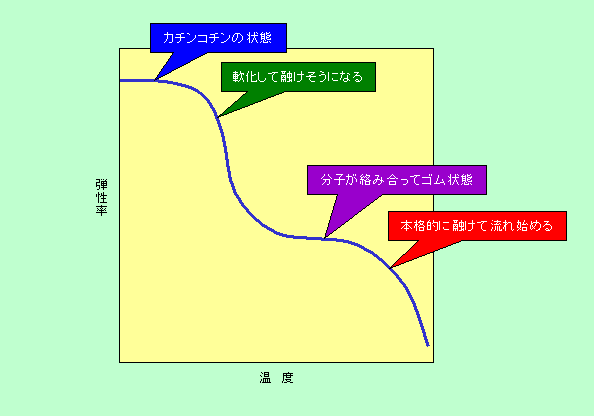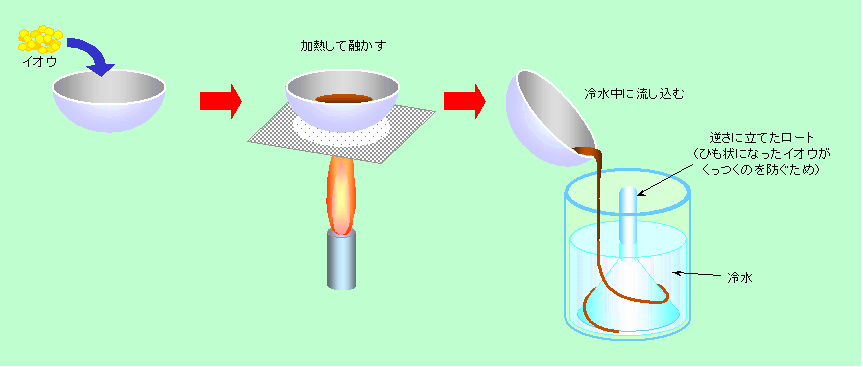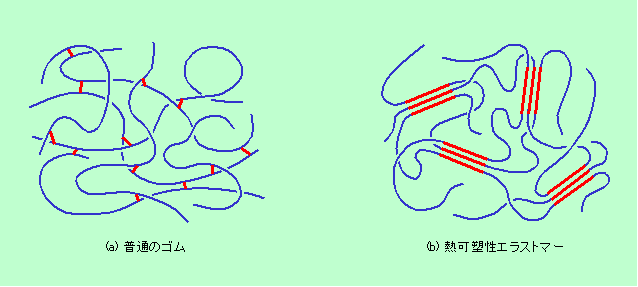雑科学ホーム
hr-inoueホーム
● ゴムの話 ●
ゴムの弾性は特別
実生活の中で、ゴムの恩恵は計り知れません。身近な輪ゴムやタイヤ、オモチャのボール、長靴、ゴムホースなどから、ビルの免震装置に至るまで、その活躍の場は極めて広い範囲にわたっています。ゴムが広く使われるのは、言うまでもなくその「伸び縮みする」性質のためなのですが、これってけっこう不思議な現象ですよね。他の物質の弾力とは一味違った、極端な伸び縮み。なぜこんなことが起こるのでしょうか。
弾力のある物と言えばバネもそうですが、例えば鋼鉄製のバネを考えた場合、例の螺旋状(つるまきバネ)にするか、薄い板状(板バネ)にしなければ、まともな弾性は出て来ません。鋼鉄の塊では、ものすごい力をかけて変形させれば別ですが、普通は弾力と言えるような性質は見えないのです。ところがゴムは、外形に関係なく伸び縮みします。ひも状であろうが塊であろうが、ちゃんと目に見える弾性を、それもケタ違いのスケールで示すわけで、このことを考えても、バネの弾力とはちょっと違っていそうです。事実、ゴムの弾性の起源はバネなどとは全く別物で、後で説明しますが、そのためにいろいろと個性的な振舞いをするのです。
ゴムの正体
ゴムを形作っているのが、単位となる化学構造がズラッとつながった高分子と呼ばれる化学物質であることはご存知でしょう。ゴムノキの樹液から採れる天然ゴムの基本単位はイソプレン、代表的な合成ゴムの基本単位はクロロプレンやブタジエンと呼ばれる物質で、図1のような構造をしています。これらの化学構造についてはここではこれ以上詳しくは触れませんが、要は、天然ゴムであれ合成ゴムであれ、基本単位となる物質が長く連なった高分子が基になっているということです(ちなみに、天然ゴムというのは必ずしもゴムノキの樹液から作ったゴムのことだけを言うのではありません。石油化学の産物であるイソプレンを使って化学合成したものも「天然ゴム」と呼ばれています)。
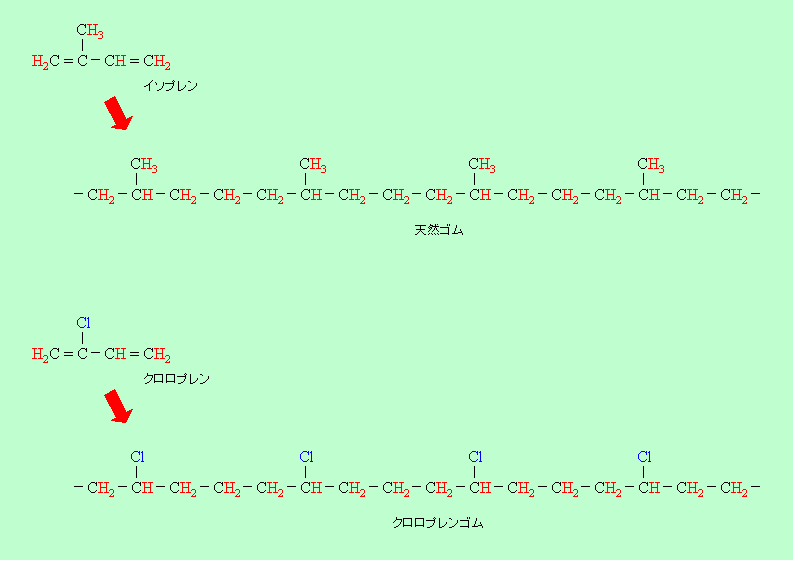
図1 ゴムの基本構造
ところで、単に基本単位が連なった高分子、ということであれば、繊維やプラスティックと何ら変わりありません。ゴムがゴムたる所以はどこにあるのでしょうか。それは、絡まった高分子の鎖がそこそこ自由に動き回れる、ということにあります。ポリエチレンやポリプロピレンなどの普通の高分子化合物では、鎖は比較的しっかりと固定されていて、外から力をかけても簡単には変形しません。十分に強い力をかければ鎖がズレて変形することはありますが、今度はズレた位置で固定されるので、元には戻らなくなります。ところがゴムでは鎖を固定する力が弱いので、ちょっとの力で変形し、変形した先でもやはり鎖の固定はあまいので、絡み合いの影響で簡単に元に戻ってしまうのです。普通の物質では原子や分子の位置はほぼ決まっており、移動できる範囲は限られていますが、ゴムでは高分子の鎖がダイナミックに動き回りますから、あの大きな伸び縮みが起こるのです。ただし、単に鎖が絡まっただけの構造(これを「生ゴム」と呼びます)では、例えば引き伸ばした状態で長い時間固定しておくと、少しずつ絡み合いの位置がズレて来てその状態になじんでしまい、完全には元に戻らなくなってしまいます。時間のスケールは違いますが、液体が流れて形を変えるようなものと思えばよいでしょう(
粘弾性の話参照)。これに対して、イオウを加えて鎖どうしを適当に橋架けすると(生ゴムの鎖には、このようなイオウと反応できるポイントがたくさん含まれています)、より強固な網目構造ができて変形しにくくなると同時に、変形から元に戻る性質も強くなります。この架橋する操作を「加硫」と呼びますが、このように加硫を施したのが普通に見られるゴムなのです。ゴムを燃やすと例の独特の臭いがしますが、その原因は主にこのイオウです。それならばイオウ以外の他の物質を使えば、いやな臭いを出さずに済みそうですが、残念ながらイオウの代わりになるものは今のところないようです。高分子の鎖を形作っている炭素と2本の手で結合して橋を架けるとなると、イオウ以外では酸素が候補になりますが、酸素は反応性が強すぎて、橋架けどころかいたるところで鎖をズタズタに壊してしまう、つまり燃やしてしまうのです。
加硫の程度を強めれば網目はどんどん強固になり、ゴムは硬くなって行きます。どのくらいの硬さのゴムが必要かによって、加硫の程度が調節されるわけです。生ゴムが持っている反応点をほとんど潰すくらいに徹底的に加硫すると(生ゴムの重量の3割〜4割ぐらいのイオウが加えられます)、ほとんど弾力のないカチコチのゴム(?)ができます。これがエボナイトで、熱や薬品に強く、割れにくいプラスティックです。硬いと言ってもいくらかはゴムの名残りを留めているので、歯で噛んだ時にも、他のプラスティックのような「カチン」とした不快感が少なく、管楽器の吹き口などにも使われています。ペンの軸やボウリングの球なども有名ですね。
特徴的なゴムの弾性
ゴムの正体がおよそわかったところで、今度はそこから来るゴムのユニークな弾性について見てみましょう。ゴムの弾性の特徴は、他の物質、例えば金属とか石ころとかと比べてみればいっそうはっきりします。
表 ゴムと他の物質との弾性の比較
| 項目 |
他の物質 |
ゴム |
| 伸び率 |
1%以下 |
数百% |
| 加熱した時 |
伸びる(膨張する) |
縮む |
| 引き伸ばした時 |
吸熱(冷たくなる) |
発熱(熱くなる) |
| 元に戻した時 |
発熱(熱くなる) |
吸熱(冷たくなる) |
ゴムの伸び率が大きいのは当然として、面白いのは伸び縮みと熱の出入りの関係でしょう。表のように、他の物質とは全く逆になる場合があるのです。これは、弾性の起源がゴムとその他の物質とで全然違うことによります。
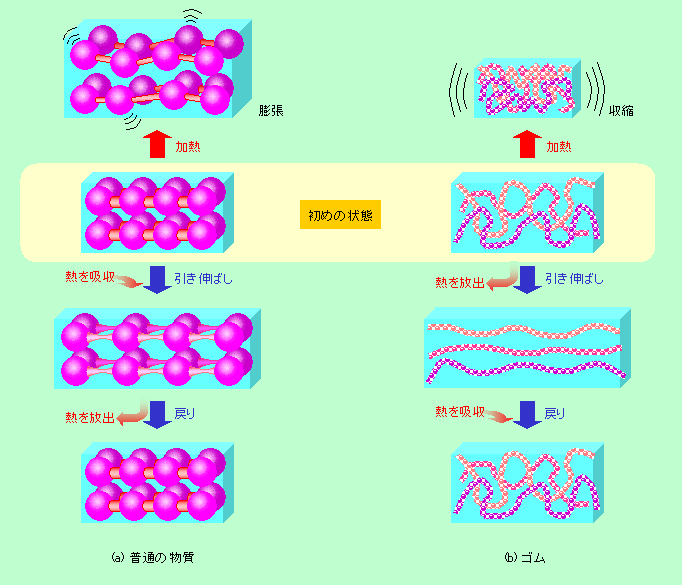
図2 物を引き伸ばした時、その内部では?
図2(a)のように、普通の物質では内部の原子や分子は互いに強く引き合っており、居心地の良い位置、つまりエネルギーの低い位置に落ち着いています。これを加熱すると、エネルギーをもらった原子や分子の振動が激しくなり、自分の占有スペースを押し広げるようになりますから、全体が膨張します。加熱すれば膨張する・・・当たり前の現象ですね。その裏返しで、外から力を加えて無理やりに引き伸ばすと、図のようにせっかく引き合って落ち着いていた原子や分子が引き離されてエネルギーの高い状態になります。足りないエネルギーは周りの熱から補充しなければなりませんから、温度は下がることになります。また、このエネルギーの高い状態というのは不安定な状態ですから、外からの力を取り除けば、当然、縮んで元の安定な状態に戻ろうとします。これが普通の物質の弾性の起源です。引き伸ばす時とは逆に、元に戻る時にはエネルギーが余りますから、これが熱として放出されて温度が上がることになります。
これに対してゴムの場合は、状況が全く違うケースが出て来ます。ゴムを加熱するとどうなるかを見てみましょう。分子の運動が激しくなる所までは普通の物質と同じです。ところが高分子鎖から成るゴムの場合、激しく運動した結果として分子鎖がぐしゃぐしゃになり、全体としては図2(b)のように縮んで来ることがあるのです。机の上に糸を伸ばして置き、適当なところを持って激しく揺すると両端が次第に近付いて来ますね。これと似たような現象です。つまり、熱を加えるとゴムは縮む場合もあるのです。同じ高分子でできた物質でも、鎖がガチッと固まっている場合には、動き回ってぐしゃぐしゃになることができませんから、ゴムのようには縮みません。またゴムの場合でも、初めからぐしゃぐしゃ度が十分に高い場合は、加熱によるぐしゃぐしゃの増加はありませんから、普通に膨張することになります。
次にゴムを引き伸ばしてみましょう。分子の鎖が動き回ることからもわかるように、ゴムでは分子どうしが引き合う力はそれほど強くありません。そのため、引き伸ばしても他の物質のようなエネルギーの増加は起こらず、その代わりに、ぐしゃぐしゃになっていた高分子鎖が引き伸ばされて並ぶようになります。先ほど、加熱によってぐしゃぐしゃになる、と書きましたが、今度はその裏返しで、無理やりに規則的に並ばされることで熱が外に放り出されて温度が上がる、という、他の物質とは逆の現象が現れることになります。当然ながら、規則性のある状態というのもエネルギー的には不利な状態です。分子としては本当はぐしゃぐしゃになっていたいので、やはり元に戻ろうとする力がはたらきます。これがゴムの弾性の起源です。聞いたことがあると思いますが、ぐしゃぐしゃの程度を表す尺度を「
エントロピー」と呼び、エントロピーが大きいほどその状態は安定です。ゴムの弾性はエントロピーが大きい状態に戻ろうとすることから発生する、と言えるのです。引き伸ばしたゴムを縮める時には、さっきとは逆に周りから熱を奪って温度が下がる、ということは容易に想像できるでしょう。
これらの特徴は、普通の輪ゴムを使って簡単に確かめることができます。輪ゴムを両手で持って急激に引き伸ばし、すぐに唇などの敏感なところに当ててみましょう。ほんのり暖かくなっていることがわかると思います(ちょっとわかりにくいかもしれませんが)。次に、引き伸ばした状態でしばらく保持し、輪ゴムの温度が安定するのを待ちます。普通は30秒も待てば十分です。そして急に輪ゴムを元の長さまで縮めて、再び唇に当てます。今度は少し冷たくなっていることがわかるはずです(よほど鈍感な人でなければ、こちらの方は簡単にわかるはずです)。普段はなじみの薄い
エントロピーを、文字通り肌で感じることができるわけです。
粘弾性とゴム
粘弾性の話でも書いているように、どんな物質でも、力を加えると変形し続ける粘性的な性質と、力に応じて変形し、力を取り去ると元に戻る弾性的な性質の両方を持っています。当然、ゴムは弾性の性質が際立っているわけですが、先に出て来た生ゴムなどは、かなり粘性的な要素も持っていると言えます。また、同じ弾性と言っても、ゴムとその他の物質とでは中身がずいぶん違っていることは先に説明した通りです。高分子の粘弾性の測定結果の中に、このようなゴムの特徴が現れることがよくあります。
粘弾性の測定は、温度を変化させながら試料に周期的な伸び縮みの力を加えて、それによって引き起こされる変形の変化パターンを解析することで行なわれます。詳しい測定方法や解析の仕方は
粘弾性の話に書いてありますのでそちらを見ていただくとして、ここでは、測定の結果として得られる、弾性率の温度変化について調べてみましょう。図3が典型的な高分子のパターンです。弾性率というのは、一定の変形をさせるのに必要な力の大きさを表すもので、「硬さの程度」と考えてもらっていいでしょう。
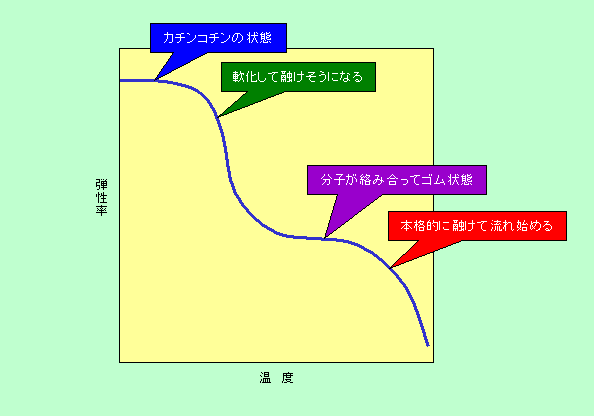
図3 高分子の弾性率の温度変化
極端に冷やせば、どんな物でもカチンコチンになります。つまり、弾性率は非常に大きな値になります。ものによっては結晶状態になっている場合もあるでしょう。分子はガチッと固まっていて、大きく動くことはできず、ここで示される弾性はゴムとは違った「普通の弾性」です。これを暖めて行くと、あるところから次第に軟らかくなって来ます。ミクロに見れば、分子の端や枝の部分がそこそこ動けるようになって来た状態、と言えます。軟らかくなり始める温度は物質の種類によっていろいろで、例えばビニール袋に使われるポリエチレンでは-100℃以下で、透明な窓などに使われるアクリル系の樹脂では逆に100℃以上の場合も多くあります。普通に「硬い」と言われる樹脂類はこの温度が室温より高く、「軟らかい」と言われる樹脂は室温よりも低いということです。
このまま暖め続けると、どんどん軟らかくなってやがてはドロドロの液体になる?、と思いきや、必ずしもそうはなりません。液状になる前にもう一回、平らな部分が現れることがあるのです。この領域では、分子はかなり自由に動くことができますが、互いに絡み合っているために、「流れる」ところまでは行っていません。まさしく、この記事の主題である「ゴム」の状態です。図2で示したように、ゴムは加熱すると鎖が収縮して小さく、硬くなろうとします。一方、温度が上がることで液体状態に向かって軟らかくなろうとする性質も、普通の物質では当然ありますから、この2つの性質がぶつかり合って、見かけ上、あまり硬くも軟らかくもならない状態がしばらく続くのです。このように、分子の鎖がある程度絡み合っている高分子ならば、温度を適当に選びさえすればゴムのような性質を持たせることができるのです。もちろん、普通にゴムとして使おうとすれば、このゴム状領域がちょうど使用温度附近(普通は室温附近)に来るようにしなければなりません。また、分子どうしの絡み合いに頼っているだけでは、やがては変形が元に戻らない、「流れる」状態になってしまいますから、普通のゴムでは、イオウによる架橋によってつなぎ止めているわけです。
「炭素の鎖」ではないゴム
これまで書いて来たように、ゴムの正体は高分子ですから、普通は炭素原子が長く連なったものです。しかし、中には「炭素の鎖ではない」ゴムもあるので、ちょっと紹介しておきましょう。その代表格は(と言うか、他にはほとんど見当たりませんが)シリコーンゴムです。
「シリコーン」というのは、ケイ素(シリコン)と酸素とが交互につながった高分子です。ケイ素には4本の結合手がありますが、その全部が酸素につながるとシリカ、つまり完全なガラスになってしまいますからゴムにはなりません。普通は4本の手のうちの2本はメチル基などの有機基で塞がれていて、残りの2本の手で、ケイ素−酸素−ケイ素−酸素−・・・・・とつながっています(というわけで、シリコーンは一応有機物とされています)。このシリコーンを、反応性の高い過酸化物などを使って無理やりに架橋して作ったのがシリコーンゴムです。ちなみに、ケイ素を意味するシリコン(Silicon)とシリコーン(Silicone)とはよく似ていて紛らわしいですが、英語の発音のちょっとした違いをカタカナで表現して区別するのが一般的です。ただし、シリコーンのことを短くシリコンと表記してしまう場合もありますので要注意です。
シリコーンゴムの最大の特徴は、熱や薬品に強く、腐食しにくいことでしょう。有機物とは言っても、メインの骨格はガラスと同じ無機物ですから、これは当然の結果です。この特徴から、化学実験用のゴム製品にはよく使われています。また、イオウを使っていないのでイヤな臭いがなく、食品に触れるような部分には好都合です。水筒のパッキンやストロー状の飲み口、密封容器や冷蔵庫のパッキンなどに使われている半透明の白っぽいゴムはみんなシリコーンです。ちょっと変わったところでは、整形手術で体の中に埋め込む型材にも利用されています。無味・無臭・無毒で、他の物と反応し難い安定性が活かされているのですが、この用途については賛否両論・・・・。
炭素の鎖ではないゴムとして、ゴム状イオウのことにも触れておきましょう。生ゴムの架橋にイオウが使われるのですが、ここで取り上げるのはイオウだけから成るゴムの話です。
イオウはほとんどの人が見たことがあるでしょう。火山や温泉地などの、地下から温水やガスが噴き出しているところで、周囲の岩などにこびり付いている黄色の塊です。どこから見ても「石」のようなもので、とても「ゴム」には見えません。このような普通のイオウでは、イオウ原子8個が作る環が基本になって結晶を作っています。結晶ですから当然硬く、弾力などはほとんどありません。110℃ぐらいに加熱して融かしても、初めのうちはただ融けて流れるだけです。
ところが、融けたイオウをさらに加熱して行くと、構造に変化が現れます。イオウ原子の環が開いてつながり、鎖状の構造ができるのです(色も黄色から赤っぽく変わります)。一旦このような構造ができても、加熱を止めて放っておくと、冷えるにしたがってまた徐々に環ができて来て、元の「石」に戻ってしまいます。そこで、ドロドロに融けて鎖状の構造ができているところで、これを冷水の中に一気に流し込みます。今度は、あまりに急激に冷えるために環を作る時間がないので、鎖状構造を残したまま固まります。これが「ゴム状イオウ」で、触ってみると本当に弾力があります。生ゴムの架橋に使われるイオウですが、自身にもこのようにゴム状になる性質があったわけです。
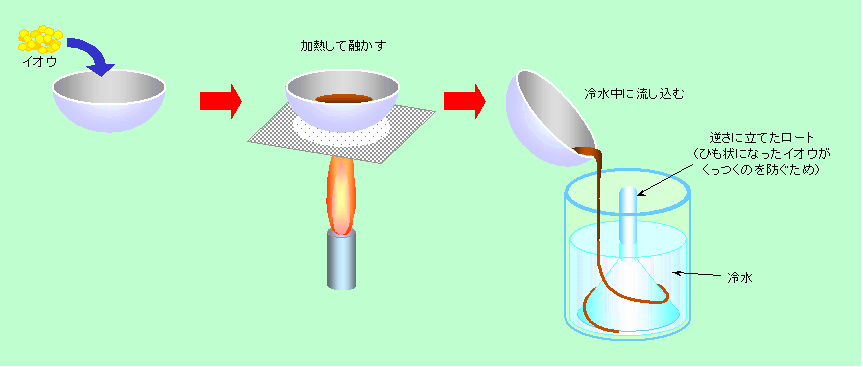
図4 ゴム状イオウを作る
子供のころに、温泉で拾ってきたイオウを使ってゴム状イオウを作ったことがあります。ゴム状態の間に加工して、面白い形のイオウを作ろうとしたのですが、簡単には加工できなくてうまく行かなかった記憶があります。なお、イオウを融かす時に加熱しすぎると粘度が高くなって冷水に流し込めなくなりますから、もし実験するのでしたら注意してください。
架橋しない弾性体 − 熱可塑性エラストマー −
加硫による架橋をしていない生ゴムはゴムとしての性質が不十分である、ということは既に説明しましたが、架橋しなくても十分なゴム弾性を示す材料があります。「熱可塑性エラストマー」です。「エラストマー」というのは、弾力のある樹脂材料全般に使われる言葉で、「ゴム」とほとんど同じ意味ですが、架橋とは違う方式で弾性を持たせている「熱可塑性エラストマー」をゴムとは別にして、この両方をひっくるめて「エラストマー」と呼ぶのが普通のようです。つまり「熱可塑性エラストマー」と「ゴム」とは同じ「エラストマー」という種類に属する親戚どうし、というわけです。
熱可塑性エラストマーの基本構造も普通のゴムと同じように、単位の構造が長く連なった高分子です。ただし、一つの高分子の中に、結晶化しやすい「硬い」部分と、結晶化しにくい「軟らかい」部分とが含まれているのが特徴です。「硬い」か「軟らかい」かは、そこを形作っている単位の構造で決まります。例えば、プラケースなどに使われるポリスチレンと同じような単位構造でできていれば硬くなりやすく、普通のゴムに使われるブタジエンのような単位構造でできていれば軟らかくなります。当然ながら、これらの違う種類の単位構造がでたらめにつながっていてはダメで、適当な長さの集団となっていなければなりません。一つの分子の中に硬い部分と軟らかい部分がブロック状に入っている「ブロック共重合体」であることが必要なのです。このようなブロック共重合体でできた材料の中では、分子の鎖は図5(b)のような面白い形になっています。
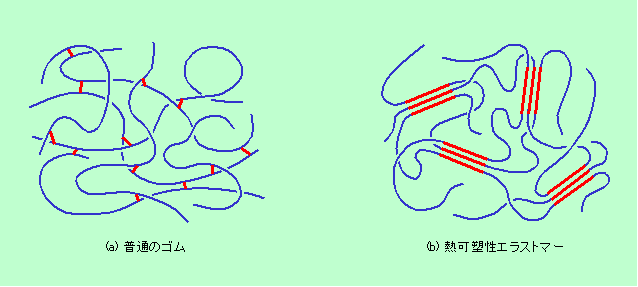
図5 熱可塑性エラストマーは普通のゴムとは違う
図の赤色で示したのが硬い部分で、青色で示したのがやわらかい部分です。硬い部分は互いに集まって来て、ガッチリ固まった結晶のような状態を作りますが、やわらかい部分は、相変わらずフラフラと動き回っています。これは、架橋によって鎖どうしがつながれた部分と、自由に鎖が動き回れる部分とができている図5(a)の普通のゴムとよく似ています。つまり、架橋することなく、ゴムの性質を持った材料が作れるのです。
普通のゴムは加硫によって架橋していますから、一旦形を作ってしまったら、別の形に変えることはほとんどできません。タイヤを作ったらタイヤのまま、ホースを作ったらホースのままで、再利用しようとしても、そのままの形で公園の遊具にするぐらいです。これに対して熱可塑性エラストマーは、その名の通り、加熱すると硬い部分の束縛が解けて流動性が出て来る、つまり、変形可能な「可塑性」が出るのです。加熱によって硬く小さくなる普通のゴムとは全く逆ですね。この点が熱可塑性エラストマーの最大のウリです。ポリエチレンなどと同じように熱をかけて自由に成型できますし、融かしてしまえば全く別の形に成型し直すこともできる、つまり材料としてリサイクルができるのです。
もっとも、いいことばかりではありません。硬い部分の束縛は、化学的に結合しているゴムの架橋ほどは強くはありませんから、低い温度でも多少は動いてしまうことがあります。こうなると、弾力が不足したり、一度起こった変形が完全には元に戻らないなど、生ゴムと同じような状況になってしまうのです。とは言うものの、材料の設計の仕方でこの辺りはいろいろと改良することができますから、今後の開発が期待されています。
雑科学ホーム
hr-inoueホーム