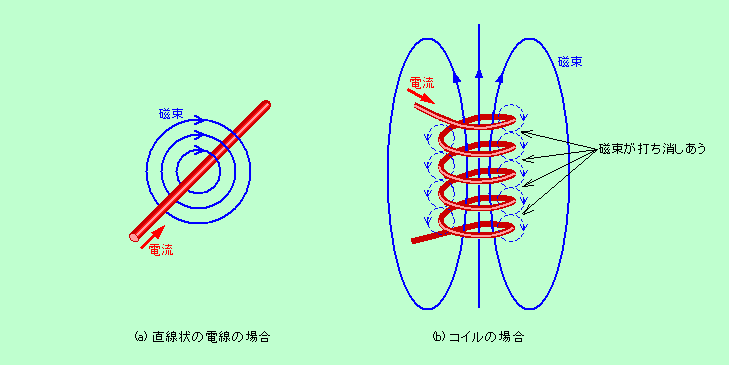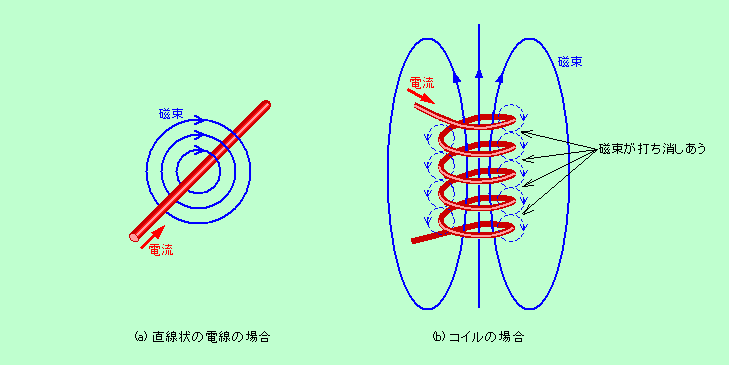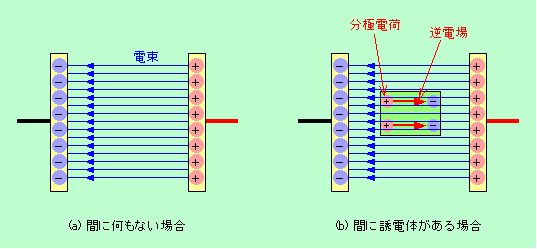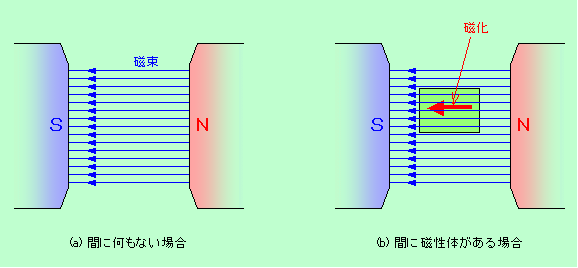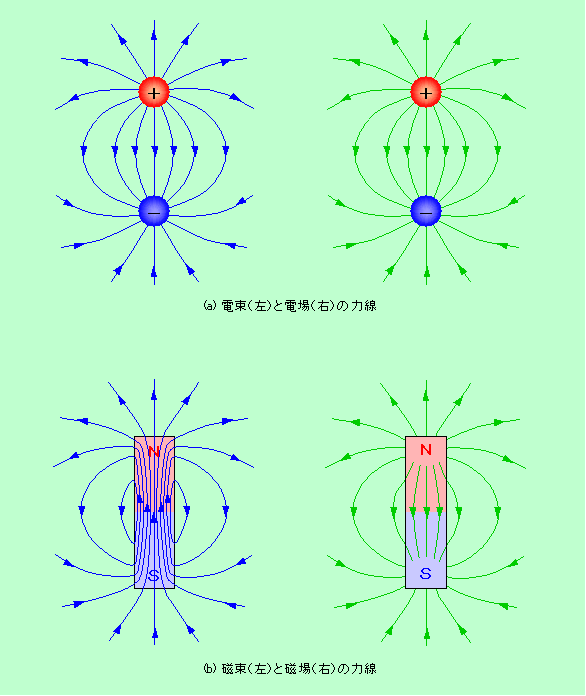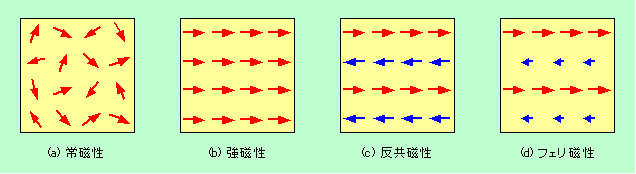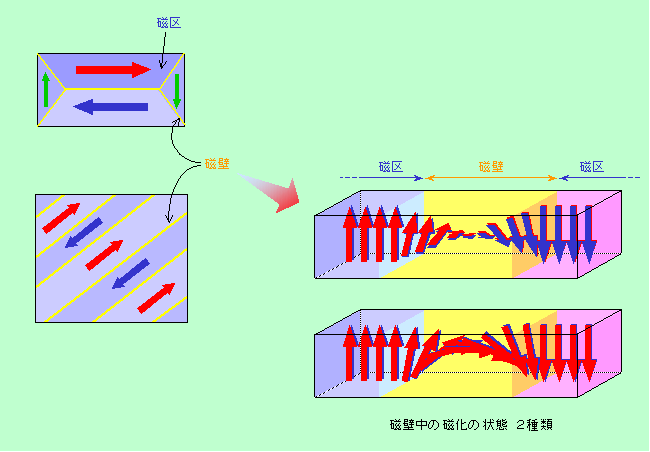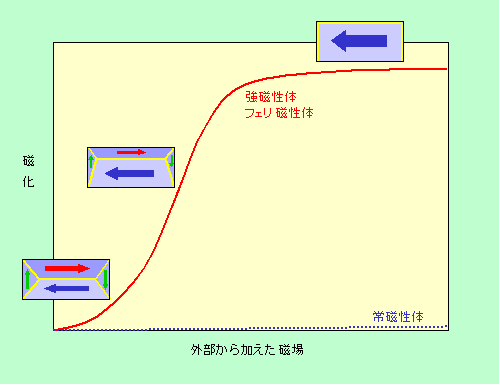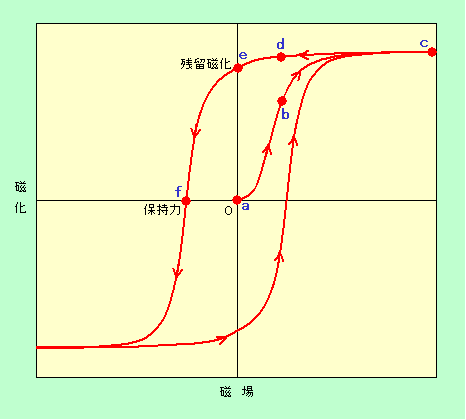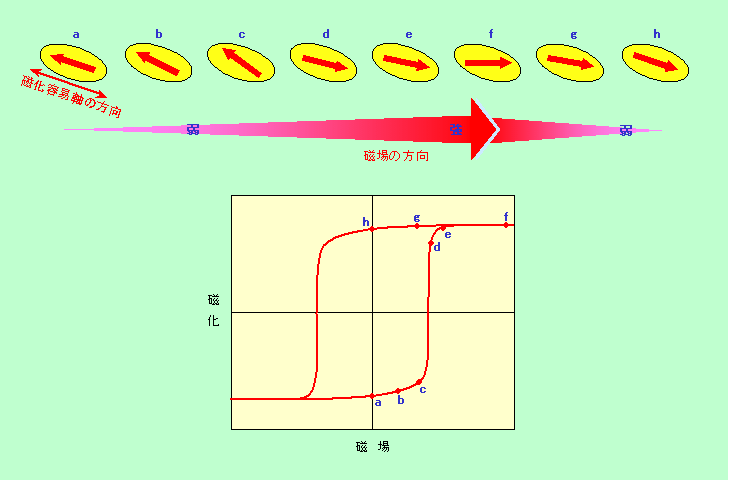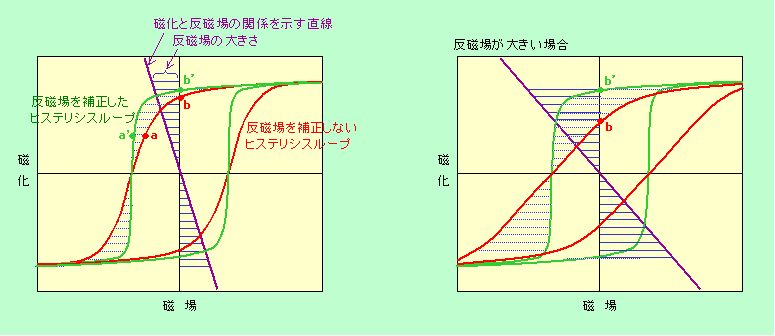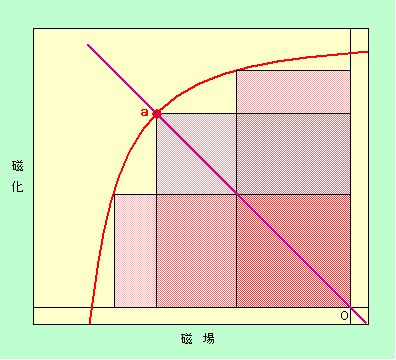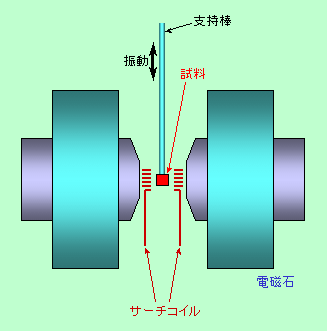雑科学ホーム
hr-inoueホーム
● 磁石の話 ●
簡単で難しい? 磁性の話
磁石の話は小学校4年生ぐらいで理科に登場するのでしょうか。砂鉄を広げて磁力線を出してみたり、いくつかの磁石を組み合わせて複雑な動きをさせてみたり、子供のオモチャとしてはけっこう楽しいものです。ところがひとたび磁性の原理・理論に足を踏み入れると、微積分の式がやたらに登場する電磁気学の世界に入りますから、ここで匙を投げてしまった人も多いのではないでしょうか。電磁気学それ自体は非常にすっきりした、きれいな体系にまとめられた学問で、理解してしまえばそれほど難しいものではないのですが、入口でつまづくと、頭の中が混乱してわけがわからなくなりやすいのも事実です。その原因の一つは、電気と磁気の関係がこんがらがっていることにあるのではないかと思います。そこで本稿では、まず電気と磁気の似たところ、違っているところをチェックしながら磁性の説明をし、その後、具体的な磁石の話に入って行こうと思います。
電磁気学の基本はマックスウェルの4つの式です。これらを初めとする数式なしで電磁気学の詳細を説明するのはさすがに無理がありますし、かえってわかり難くなる可能性があります。しかしこのサイトでは数式は一切使わないと宣言してしまいましたから、ここではあくまでも現象の説明に留めることにします。電磁気学をさらに詳しく知りたい方は、別の参考書などを見てください。
磁性の正体は回る電気・環電流
中学校の理科で電流と磁界の関係を習いますね。基本の基本ですから簡単におさらいをしておきましょう。
図1(a)のようにまっすぐな電線に電流を流すと、右ネジが進む方向に回転する環状の磁界が現れます。この磁力の向きを表す線=磁力線の束を「磁束」と呼び、磁力の強さは単位面積あたりの磁束の本数、つまり「磁束密度」で表されます。「磁束」などと言わなくても「磁力線」のままでよさそうな気もしますが、磁力の強さを「磁束密度」で表すことに決められているので、ここは単なる単位の取り決めの問題として納得してもらうほかありません。また「磁場」という言葉は、この段階ではあえて使いませんでした。「磁場」と「磁界」は同じ意味なのですが、「磁場」という言葉はもっと厳密な意味で使いたいので、もう少し説明が進んでから登場してもらいます。
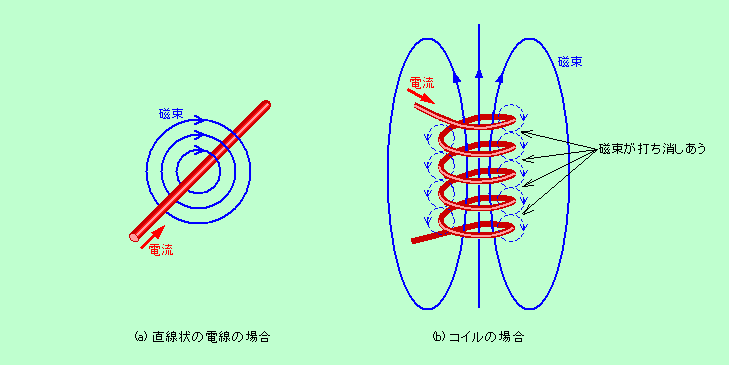
図1 電流と磁界との関係
次に図1(b)のように電線を環にしたコイルを考えます。環になった電線の1本1本から右ネジの法則に従って環状の磁束が現れますが(青の破線)、電線と電線の間では逆方向の磁束が打ち消しあいますから、結局一番外側の磁束だけが残ります。その結果、コイル全体としては青線のような磁束が発生することになるのです。
磁石の磁性の正体もこの環電流です。電磁石はコイルそのものですから、図1(b)そのままですね。一方永久磁石では、磁石を構成する物質が持っている電子の自転が環電流の源です。普通の物質では電子の自転の向きはてんでバラバラですから外からは磁性は見えませんが、何かの原因で自転の向きが揃った電子が多くなると磁性が現れて来るのです。このように電子の自転の向きが常に揃っているのが自ら磁性を発する永久磁石であり、普段はバラバラですが磁界の影響で向きが強引に揃えられて磁性を現すようになるのが鉄などの磁石に吸い付く物質なのです。
混乱しやすい電場と電束密度、磁場と磁束密度
磁性の正体は環電流であったわけですが、これに対して電気の方の基本は「電荷」です。電荷があるとその周囲に「電場」ができ、別の電荷は電場の中で力を受けるのです。何もこんな回りくどいことをしなくても、電荷と電荷が直接作用して引っ張り合ったり反発し合ったりすると考えればよいではないか、と言われるかもしれません。確かにその通りです。ところが、電荷が2個だけならいいのですが、例えば100個の電荷がある場合は全部で4950通りの組み合わせができますから、めんどう見切れません。そこで、他の全ての電荷の影響で電場が作られ、そこに置かれた電荷は電場から作用を受けると考えた方が便利なのです(実は「場」の考え方は取扱いの都合だけでなく本質的なものなのですが、ここではその詳細には触れません)。
電気の世界でも磁性と同じように「電束密度」という考え方があります。電荷から電束が飛び出し(マイナス電荷の場合は電荷に飛び込み)、その電束の密度で電場の強さが決まる、とするのです。とすれば、電束密度=電場、ですから、2つの言葉を使ってややこしくする必要はありません。ところが、これは空間に何もない時の話であって、別の物質があると様子が違って来るのです。
図2(a)のように、プラスとマイナスの電荷を持った1組の平板を考えましょう。2つの平板の間では、端の方は別にして、どこでも同じ均一の電場ができています。電束で表せば図のような平行で等間隔の矢印になります(電束の密度はどこでも同じです)。この状態では電束密度と電場の違いは見えません。ここに
誘電体を置いてみましょう。誘電体というのは電気を通さない絶縁体のことで、導電体以外の世の中の全ての物質がこれに当たります。誘電体の中では電荷は自由に移動することはできませんが、電子やイオンなどの電荷を持った粒子が詰まっていますから、電場の中に置かれるとそれらが全体として位置ズレを起こし、プラスの平板側にマイナス電荷が、マイナスの平板側にプラス電荷が現れます。この現象を「分極」と呼びます。分極が起こると、例えばマイナスの分極電荷はプラスの平板からの電場を一部止めてしまいますので、誘電体の内部の電場は弱くなります。別の言い方をすれば、分極で発生した電荷によって元々あった電場とは逆方向の電場(図の赤矢印)ができるために元の電場が弱まる、ということです。とにかく、誘電体の内部では、分極によって外側よりも電場は弱くなるのです。
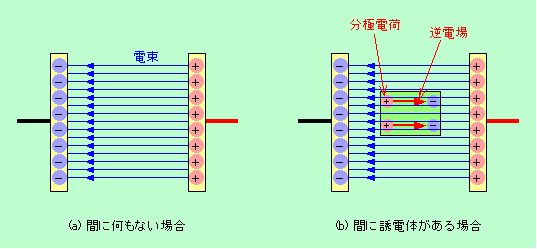
図2 電場の中に誘電体を置くと・・・・・
電場がどれくらい弱くなるかは誘電体の種類によって変わりますし、ひとかたまりの誘電体でも全体が均一とは限りません(と言うより現実的には均一な方が希です)。こうなると誘電体の内部の電場を考えるのは結構やっかいです。そこで、初めの電束密度の考え方が再浮上します。誘電体があろうがなかろうが、初めにあった電束(密度)は変化しない、とするのです(元々電束とはこのようなものであると考えられていました)。つまり電束は、図2の平板のように電荷から発生するのですが、途中に分極した誘電体があっても一切関係なく、平板上の電荷が変化しない限り永久不変である、と考えるのです。こんなものが実際にあるはずはありません。現実に存在するのは誘電体の中で弱くなった電場だけです。しかしこのようにすると、とりあえず電束密度というものが空間にあり、そこに置かれた誘電体の内部では、電束密度をその誘電体特有の値(誘電率)で割った強さの電場ができる、と考えることができて、複雑な状況を割と簡単に表現できるのです。電束密度と言うのは、考えやすくするために人間が勝手に決めた仮想的なものであり、電場こそが本質的な現象を示しているのだということです。
それでは磁性の方はどうでしょうか。同じように巨大な磁石が作る均一な磁界を考えましょう。図3(a)のように、ここでは平行で等間隔の磁束ができています。ここに磁性体を置いてみます。ここでの磁性体は、自転する電子は持っていますが、普段は回転の向きが揃っていないために磁性を示さない物質です。これを磁束の中に置くと、その影響で電子の回転方向が揃えられて磁束が発生します(ここで現れる単位体積あたりの磁性の強さを磁化と言います)。その向きは図3(b)の赤い矢印の方向になりますので、これは外部の磁束と同じです。ということは、磁性体の内部では電場の場合とは逆に磁束は強くなるのです。ここで電場の時と同じことを考えます。磁性体の種類によってその内部の環電流(つまり磁化)が色々変化するのはめんどうくさい。そこで磁性体のあるなしにかかわらず、N極から出てS極で終わる永久不変なものを決めてしまおう、というわけです。実はこれが「磁場」なのです。そして磁場にその磁性体特有の値(透磁率)をかけあわせると磁束密度になる、と決めてやるのです。つまり磁性の世界では磁場は仮想的なもので、磁束密度の方が本質的なのです。
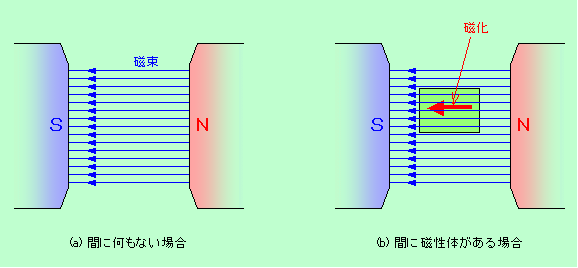
図3 磁場の中に磁性体を置くと・・・・・
電気と磁気で、なぜこのような逆の関係が起きてしまったのでしょうか。それは電気の起源がプラスやマイナス電荷であるのに対して、磁性の起源が環電流であり、そこから生じるNSの組であるからです。プラスやマイナスの電荷は単独でも存在します。しかし磁性の方は、N極だけ、S極だけという単独の磁荷(磁気単極子)は存在しない(少なくとも今のところは見つかっていない)のです。
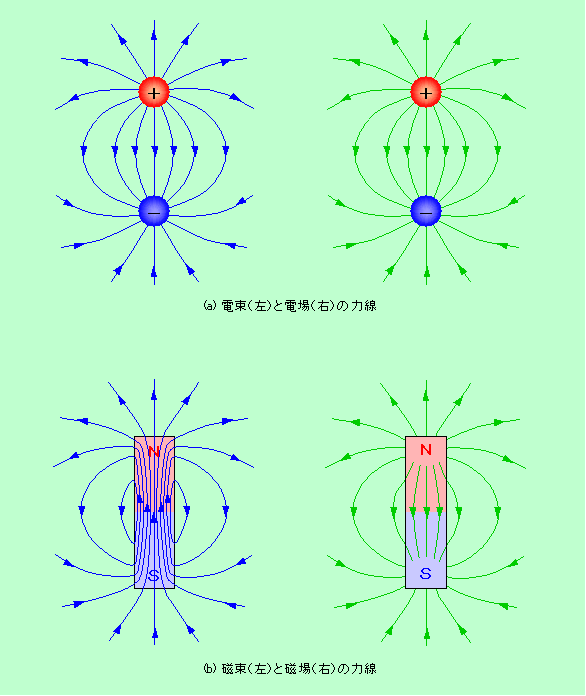
図4 電束と磁束は違う
図4(a)を見てください。左が電束、右が電場を図示したものですが、いずれもプラス電荷から出てマイナス電荷の中に吸い込まれて行きます。誘電体がなければ、両者に違いは見えません(値は単位の取り方によって違いますが)。これに対して図4(b)の磁束・磁場の方は全く様子が違います。これは両端にN極とS極がある棒磁石と思ってもらえばよいのですが、その棒磁石内部の環電流によって、磁束は図1(b)と同じように右ネジの法則に従ってループを描きます。単独の磁荷が存在しないので、磁束には湧き出し口も吸い込み口もないのです。一方磁場の方は電場からの類推で考えられていますので、N極から出てS極に入ります。そのため遠くから見れば磁束と磁場とはよく似た形をしていますが、近くでは(特に磁石の内部では)方向も形も違っているわけです。
歴史的に見れば、まず電荷から発生する電束というものが考えられ、後に本質的なものは電場であることがわかったので、両者をつなぐ誘電率という考え方が導入された、というのが本当です。磁性の方は、電場・電束密度からの類推で磁場と磁束密度を考えて理論を組み立てていたところ、実は環電流から発生する磁束が本質的なものであり、電場に対応するのは磁束密度であることが判明しました。これはちょうど、電流はプラス極から出てマイナス極に戻ると決めたのに、後になって電流の本質が電子であり、流れの方向は実は逆であることがわかった、という話とよく似ていますね。世の中すんなりとは行かないようです。ただし、現在では「電場-磁束密度」、「電束密度-磁場」という対応で理論を組み立てるのが主流ですが、あくまでも形式的な類似性に主眼を置いて「電場-磁場」、「電束密度-磁束密度」という対応をさせる考え方もあることを付け加えておきます。将来「磁気単極子」が発見されるようなことがあれば、いっぺんに立場が逆転する、ということもないとは言えないのです。
さて、これまで電磁気の基本的な話をして来ましたが、ここからは実際の磁性体の話に入ります。永久磁石に行き着くには、まだまだ遠い道のりがありますから、ステップを踏んで順番に見て行きましょう。
永久磁石への道
第1段階 − 物質を構成する原子が磁気モーメントを持つ
先にちょこっと触れましたが、磁性体の磁性の起源は電子の自転です。自転と言っても、形もわからない電子の話ですから、地球の自転やコマの回転のようなものとは少し違いますので、以後は「スピン」と呼ぶことにしましょう。このスピンの向きがそのまま各電子の磁気の向きになります。これを電子の磁気モーメントと言います。
原子の中では、電子は原子核の回りのある特定の軌道に入っており、エネルギーの低い内側の軌道から順次埋めて行く、ということはご存知でしょう。この時、同じ軌道の中でスピンの向きを逆にした2個が対を作って安定する性質がありますので、互いの磁気モーメントが打ち消しあって、トータルの磁気モーメントはなくなってしまいます。しかし電子の数が奇数の場合はペアを作ることが出来ない電子が一番外側の軌道に1個余りますから、原子全体として磁気モーメントを持つことになります(複数個の電子がペアを作らないで存在している原子もあります)。ところが、これで終わりではありません。内輪で相手が見つからないとなると今度は外に相手を求めるようになり、電子が余っている別の原子(同種の原子でも別の種類の原子でもよいのですが)とくっついて、ここでペアを作ってしまうのです。というわけで、原子が集まって作られている普通の物質では、磁気モーメントは発生しません。大半の物質が磁性を示さないのはこのためです。
ところが、一部の原子では状況が違っていて、内側の軌道が全部埋まらないままに外側の軌道に電子が入ります。一番外側で余った電子は、先に書いたように他の原子とくっついてペアを完成させますが、内側の軌道で余った電子はそうは行きません。その結果、ペアを作らない電子を内側の軌道に持っている原子は、原子が集まった物質の中でも磁気モーメントを持つことになります。鉄やニッケル、コバルトなどのいわゆる鉄属の原子や、希土類と呼ばれる原子がこれに当たります。
第2段階 − 原子の磁気モーメントの向きが揃う
原子が磁気モーメントを持っているからと言って、即、磁石になれるわけではありません。各原子の磁気モーメントの向きがバラバラだと、物質全体としては磁性を示さないのです。例えば溶液の中の金属イオンなどでは、各イオンは好き勝手な方向を向いていますから、例え1個1個のイオンが磁気モーメントを持っていたとしても、全体としては磁性は持ちません。このような状態を「常磁性」と言います。常磁性の物質は普段は磁性は示しませんが、磁場の中に置かれると一部の磁気モーメントの向きが無理やりに揃えられ、磁石のように振舞う、つまり磁化を持つようになります。磁場が強くなればなるほど、向きが揃えられる割合も多くなって磁性が強くなりますが、その強さは大したことはありません。また磁場が取り除かれると、元の磁性を持たない状態に戻ってしまいます。
これに対して金属原子が集まった結晶では、原子が互いに相互作用して磁気モーメントの向きが結晶の特定方向に揃えられる場合が出て来ます。こうなると物質全体としても磁化を持つようになるわけですが、磁気モーメントの方向の揃い方によって、外に現れる磁化は大きく変わります。その様子を図5に示しました。
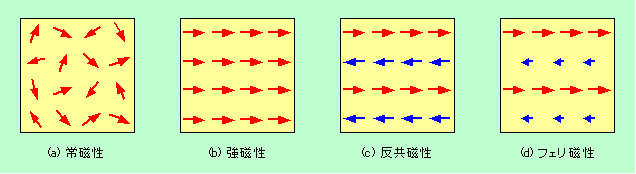
図5 原子の磁気モーメントの揃い方で磁性は変わる
図5(a)は常磁性の場合で、磁気モーメントの向きはバラバラです。これに対して図5(b)のように全ての磁気モーメントが一方向に揃うと、大きな磁化が現れます。これが「強磁性」の状態です。鉄などはこれに相当し、結晶の軸の方向に磁気モーメントが揃っています。逆に全ての磁気モーメントが同じ向きに揃うのではなく、図で言えば右向きに揃った磁気モーメントと左向きに揃った磁気モーメントが同じだけできると、外からは全く磁化が見えません。これが「反強磁性」です(図5(c))。マンガンやクロムの一部の酸化物がこれに当たります。また、反強磁性と同じように逆向きの磁気モーメントが混在しているのですがその総量に差があり、全体として一方の向きの磁化が残る場合があります。これが「フェリ磁性」で、名前の通り、フェライトと呼ばれる鉄系の化合物がその代表格です(図5(d))。言うまでもなく、磁石になるには強磁性、またはフェリ磁性を持っていることが必要です。
常磁性以外の3つの状態の物質は磁気モーメントの向きが揃っているわけですが、温度を上げるとそれぞれの磁気モーメントが勝手に動き出し、バラバラの常磁性状態になります。つまり高温ではみんな常磁性になってしまうのです。常磁性になる温度(キュリー温度)は物質によって違っていて、鉄の場合は770℃です。
物質の磁性にはもう一つ、「反磁性」というのがあります。外部から磁場をかけると、その磁場とは逆向きにごく弱い(常磁性よりも弱い)磁気モーメントが現れる現象で、これは電子のスピンによるのではなく、「環状の電流は外部磁場を妨げる方向に向く」というレンツの法則に従って電子が運動した結果です。どんな物質でも電子を持っていますから、この反磁性はあらゆる物質が持っている性質です。ただし、その磁性が非常に弱いために、電子のスピンに基づく磁性がある場合には、それに隠れて全く見えなくなってしまいます。ここで扱おうとしている磁石の磁性には関係ありませんから、反磁性についてはこれ以上は触れません。
第3段階 − 特定の方向に磁気モーメントが揃った部分が多くなる
強磁性かフェリ磁性を持っていれば磁石になるか、と言えば、そうではありません。まだもう一段階必要です。その理由を説明しましょう。
図5では物質内部の磁気モーメントの状態はどこでも同じであるように描いています。しかし実際には、このように物質全体が同じ状態になることはめったにありません。エネルギー的に不利だからです。例えば2本の棒磁石を近付けると、互いにNSを逆に向けてくっつきますね。この方が安定だからです。もしNSの向きを同じにしてくっつけようとすれば、無理やり力をかけて押し付けなければなりません。磁性体の内部で全ての磁気モーメントの向きが揃っているというのは、このように磁石を同じ向きにしてくっつけているのと同じで、非常に不安定な状態なのです。そのため実際の磁性体の内部は、図6のように磁気モーメントの向きが違ういくつかの部分(磁区)に分かれているのが普通です。この時、磁区と磁区との境界では突然磁気モーメントの方向が変わるのではなく、ある幅の中で徐々に向きが変化します。この部分を磁壁と呼びます。このような磁区構造ができると、一つ一つの磁区は磁気モーメントを持っているのに、全体としては磁化は現れないのです。
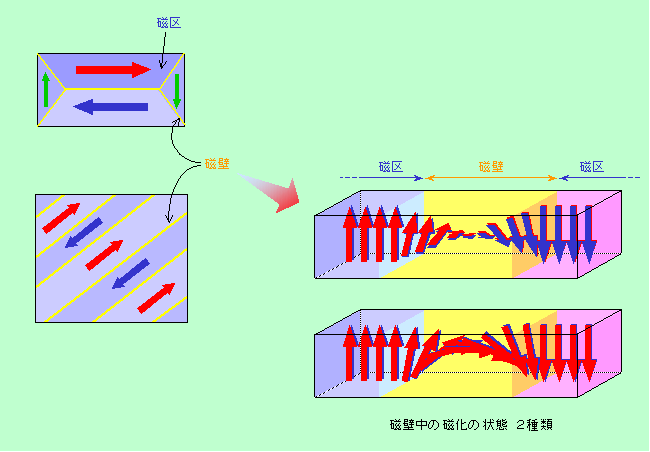
図6 現実の強磁性体、フェリ磁性体は磁区に分かれている
これに磁場をかけてみましょう。すると、磁場と同じ方向の磁気モーメントを持った磁区が勢力を増し、その領土を拡張します。磁壁が移動するのです。このように磁気モーメントの向きが違う磁区のバランスが崩れると、全体として磁化を示すようになるのです。
これだけならば常磁性と大差ないように思えますね。しかし現れる磁化の大きさは桁違いで、常磁性体の数百倍から数万倍もありますから、常磁性体は磁石にくっつきませんが、強磁性体、フェリ磁性体は磁石にくっつきます。もう一つの常磁性との違いは、磁場の増加に対して磁化の増加が頭打ちになることです。全体が一つの磁区になってしまうとそれ以上は磁化が増加しないからです。この様子を図7に示しました。
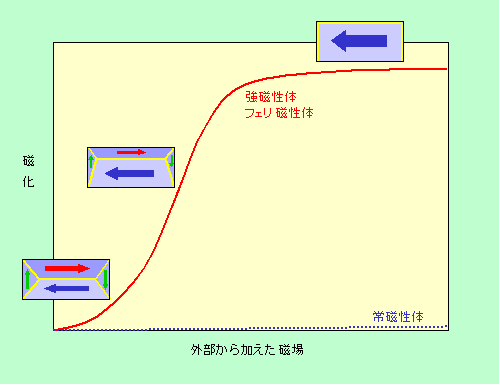
図7 常磁性体と強磁性体(フェリ磁性体)の磁化曲線
これでだいぶ磁石に近付きました。しかし、まだ完成ではありません。純粋な鉄などでは、加えた磁場を取り去ると磁区が元の状態に戻ってしまうのです。磁場を加えている間だけの磁石、ということです。これはこれで使い道があります。電磁石や変圧器の鉄心、磁気記録用のヘッドなどは磁性が残っては困る材料ですから、このような元に戻る磁性材料(軟磁性材料)が必要なのです。ただしここでは磁石が目的ですから、軟磁性では困ります。そこで、不純物を加えたり材料を工夫したりして、磁壁が自由に動くのを邪魔してやり、一旦磁化してしまえば簡単には元に戻らないようにするのです。これでようやく永久磁石の完成です。
鉄の磁壁移動を邪魔するには炭素などを加えます。つまり鋼です。縫い針などを磁石でこすって、針自体を磁石にした経験があるでしょう。これは縫い針が鉄ではなく鋼だからこそできる芸当なのです。また一部の希土類と呼ばれる元素の化合物は、磁気モーメントの向きを揃える力が強い上に磁壁が動きにくい性質があり、非常に強力な磁石を作ります。サマリウム・コバルト磁石や、史上最強のネオジム・鉄・ホウ素磁石がこれに当たります。
完成した永久磁石に磁場をかけたときの磁化の変化を図8に示しました。これは磁化曲線のヒステリシスループと呼ばれるもので、横軸に外から加えた磁場、縦軸に磁化、または磁性体内の磁束密度をとります。磁束密度は外から加えた磁場による分と磁性体の磁化による分の合計ですから、磁束密度を縦軸に取ったヒステリシスループは、磁化を縦軸に取った場合よりも右肩上がりの図になります。ここで示しているのは縦軸に磁化をとった図です。
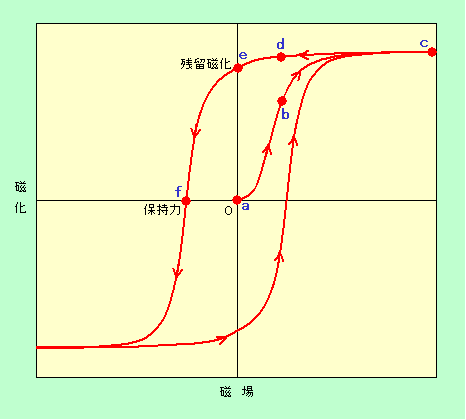
図8 永久磁石のヒステリシスループ
初めは均等な磁区構造ですから磁化はゼロで(a点)、磁場をかけると磁壁が移動して図7と同じように磁化が進みます(b点→c点)。ここから磁場を減らして行くと、軟磁性材料では元のカーブに近いところをたどるのですが、磁壁移動を邪魔するように細工した磁性体では簡単には磁壁が戻れませんので、高い磁化を保って変化します(d点)。磁場がゼロになったe点でも、かなりの磁化が残り(残留磁化)、永久磁石として機能するのです。しかし逆方向に一定の磁場をかけると、ついには磁化はなくなってしまいます(f点)。この時の磁場の大きさが、その磁石の保持力です。さらに逆向きの磁場を強くすると、今度は逆方向で同じような過程をたどるのです。
磁石としては、残留磁化が大きい方が磁力が強く、保持力が大きい方が磁力を失う可能性が少なくなります。また、ループの形ができるだけ長方形に近い「いかり肩」の方が、「なで肩」よりも逆方向の磁場を受けた時の磁力の低下が少ないですから、より強い磁石と言うことができます。
磁化を残す別の方法 − 微粒子化
永久磁石を作るのに、磁区構造を持っている磁性体の磁壁を動きにくくする方法について書きましたが、実はこれとは別の方法があります。磁性体を細かい粒子状にして、磁区構造そのものをなくしてしまうのです。
磁区ができるのは、磁気モーメントが全て同じ方向に揃うと不安定になるからでした。ところが図6の磁壁の図からもわかるように、磁壁の中では磁気モーメントの向きは本来の向きとは違いますから、これも不安定な状態です。磁壁を作ることによる不安定さと磁区を形成しないことによる不安定さのどちらが大きいかで、磁区ができるかどうかが決まるのです。磁性体が十分大きい時には全体が一様になった時の不安定さが大きいので、磁区が作られます。ところが磁性体が小さくなると、全体が一様になっても大したことはありませんから、無理に磁区を作る必要がなくなるのです。材料の種類や形にもよりますが、1ミクロン以下の微粒子になると、磁区構造がなくなって粒子全体が一つの磁区になる可能性が出て来ます。
粒子が一つの磁区でできていると、外部から磁場をかけた時に磁壁の移動で磁化することはできません。1個1個の磁気モーメントを直接ひっくり返すことが必要になります。磁壁の移動のように磁気モーメントの方向を徐々に変えるのと比べて難しそうなことが想像できるでしょう。特に、粒子が特定方向に磁化されやすい性質を持っている場合、ひっくり返すのは大変になります。
この特定方向に磁化されやすい性質(磁気違方性)は、結晶構造による場合(結晶磁気違方性)と、粒子の形による場合(形状磁気違方性)とがあります。先ほど出て来た強磁性体やフェリ磁性体は多かれ少なかれ結晶磁気違方性を持っているわけですが、中でも安価な永久磁石によく使われるバリウムフェライトなどでは、結晶の特定の一方向だけに強く磁化される性質があります。一方、磁気テープのような記録材料に使われる酸化鉄などでは結晶構造の影響は小さく、粒子の形がものを言います。これらの記録材料用の粒子は細長い形をしており、N極とS極を遠く離した方が安定になるという理由から、長い軸方向に磁化されやすいのです。
このような磁気違方性を持った粒子が磁化する様子を図9に示しました。より現実的にするために、磁化しやすい方向(磁化容易軸)から少しずれた方向に磁場をかけた例を出しています。
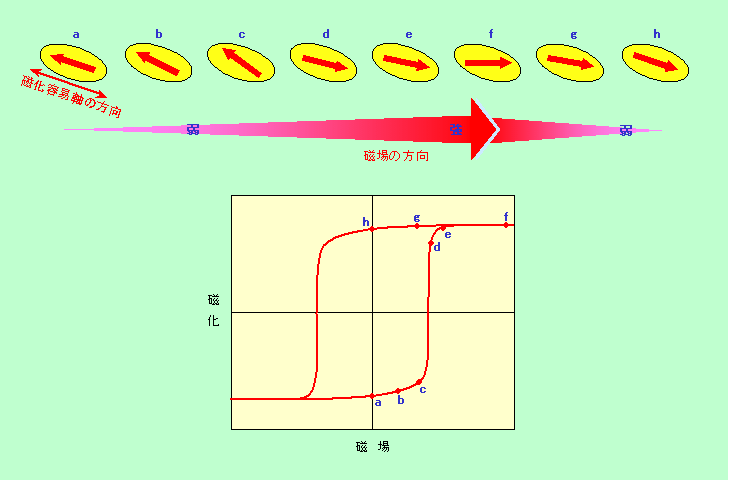
図9 一つの磁区でできた微粒子の磁化
初めは粒子の磁化は左やや上を向いています。これに右方向の磁場をかけ、それをだんだん強くして行くと、粒子の磁化は少しずつ回転し始め(a→c)、ある限界点を超えると一気に反対側に倒れます(c→d)。ただしこの時点では、磁化容易軸の方に引っ張られて、磁化は磁場の方向よりも少し下を向いています(d)。さらに磁場を強くすると最終的には磁化はほとんど磁場の方向を向きますが(f)、ここから磁場を減少させて行くと、磁化はしだいに磁化容易軸の方向へ向き直り(f→h)、磁場がなくなったところで、初めとは180度逆の磁化容易軸上に落ち着きます(h)。
このように微粒子の磁化の変化は極端で、磁化の方向が突然に反転しますから、微粒子1個のヒステリシスループは図8と比べて長方形に近い形(磁化容易軸と磁場の向きが一致していれば完全な長方形)になります。これは磁石材料としては理想的な形ですから、微粒子を集めて磁石を作れば完璧・・・・・、と思いきや、実はそううまくは行きません。微粒子を集めた場合、全ての粒子が全く同じ性質であることはあり得ず、粒子によって磁化を反転させるのに必要な磁場や磁化の大きさは微妙に違っています。粒子の向きもそうです。そのため、少しずつ違ったヒステリシスループが重なることになり、結局、かなり「なで肩」の形になってしまうのです。
とは言っても、微粒子タイプの磁石は残留磁化や保持力を大きくしやすいですから、磁石を作る有力な方法であることには違いありません。実際にフェライト磁石はバリウムフェライトなどの微粒子を焼結して作られますし、有名なアルニコ磁石はアルミとニッケルとコバルトの合金中で非磁性部分の中に磁性を持った微粒子を析出させたものです。また磁力を高める目的とは違いますが、ボンド磁石と言って磁性粒子をゴムやプラスティックで固めたものもあります。自由な形に作れますし、柔軟性があるものもできますから、冷蔵庫の扉のパッキンだとか磁石シートなどに使われています。
磁石の形
磁化された磁石はエネルギーの高い不安定な状態であることを再三書いて来ました。普通はそこからエネルギーの低い状態に落ち込むはずですが、途中の磁壁移動や磁化反転の過程でさらに高い山を越えなければならないようにすることで、なんとか不安定状態を保たせているのです。それでも磁石は多少なりとも安定になろうとして抵抗を試みます。磁気モーメントの向きを少し変えて、磁化を減らそうとするのです。これが磁石の減磁(自己減磁)です。
自己減磁を説明するのには、「反磁場」という考え方が便利です。図4(b)に示したように、磁石の内部には逆方向の磁場が発生しており、これによって自身の磁化が減少する、と考えるのです。当然ながら、NSの極方向に細長い磁石と平べったい磁石とを比べれば、平べったい磁石の方が極の面積が広い分、反磁場も大きくなり、減磁も大きくなります。これをヒステリシスループで見てみましょう。
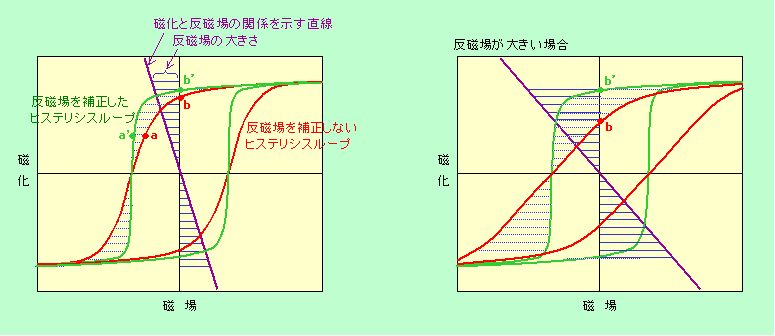
図10 反磁場でヒステリシスループの形が変わる
初めに左の図を見てください。図の紫の直線は、磁化に対する反磁場の大きさを示しています。例えばプラスに大きい磁化(図の上方)があった場合、左方向に大きな反磁場が出る、ということです。実際の磁性体には、外から加えた磁場の他に、この反磁場もかかっているとみなすことができます。
赤線は外から加えた磁場に対して測定されたヒステリシスループです。この時は、磁性体には外から加えた磁場と反磁場の両方がかかっているのですが、横軸には反磁場なしの磁場の値がプロットされています。それでは、横軸を反磁場も含めた磁場にするにはどうすればよいでしょうか。先の反磁場の紫線を使えば簡単です。ヒステリシスループ上のある一点(a点)に着目すると、その時の磁化の値から、紫線を利用して反磁場の大きさがわかります。その反磁場の分だけ磁場の値を(この場合は左に)ずらしてやればよいのです(a'点)。同じ操作をループ全体に対して行なえば、図の緑のループが描けます。これが反磁場を補正したヒステリシスループなのです。この磁性体は本来は緑線のようなパフォーマンスを持っているにもかかわらず、反磁場を考えないで外部から加えた磁場だけで評価すると赤線の形になってしまうのです(実際に測定されるのはこちらの方)。
この磁石の反磁場がもっと大きくなるようにしたらどうなるでしょうか。例えば、もっと平べったい形にするのです。そうすると反磁場を表す紫の直線はもっと傾きが大きくなりますから、図10の右のようになります。その結果、反磁場を補正すれば緑線のようになるはずのループが赤線のように変化し、磁石としての性能がさらに悪くなるのです。右上の領域で言えば、反磁場が足を引っ張るので非常に大きな磁場をかけなければ磁化させることができませんし、一方左上の領域では、外部磁場は小さくても左向きの反磁場が大きいですから、それによって磁化が減少してしまうのです。
磁石を使う上で重要なのは、外部磁場がゼロのb点です。反磁場がなければ緑のb'点で示される大きな磁化が残るはずですが、実際には反磁場がありますから、赤のb点まで磁化が落ちてしまうのです(b点は、紫の反磁場を表す直線と緑のループとの交点の磁化に相当します)。これが自己減磁です。実際の磁石には常に反磁場がかかっていると考えられますから、これがその磁石の本当の実力、ということになります。
それでは、磁石を細長くしてN極とS極を思い切り遠ざけてしまえばよいのでしょうか。確かに反磁場は小さくなりますから自己減磁は少なくなりますが、極の面積が小さいので、磁石全体の体積の割には強い磁力は得られません。実は磁石には、最も強いパワーが得られる形があるのです。
何度も書いているように、N極とS極が両端に現れた磁石というのはエネルギーが大きい、不安定な状態です。これに鉄などが吸い付くと、磁石の極は吸い付けた鉄の一番先端に移りますから、N極とS極が遠くなって少し安定化します。その時のエネルギーの差が磁力の源です。ということは、形から来る不安定さがある程度大きい方が、鉄を吸い付けた時の安定化の度合い=磁力も大きくなる、ということです。もう一度ヒステリシスループを見てみましょう。図11はヒステリシスループの左上の部分を拡大したものですが、ここは磁石に自身の作る反磁場がかかって磁化が減少する様子を表す領域でもあります。つまり、反磁場という逆風の中で磁化を維持しようとがんばっている不安定な状態であるわけで、それだけエネルギーが大きいのです。
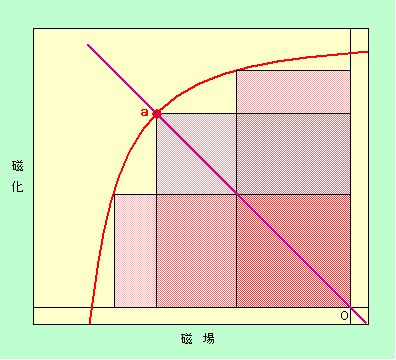
図11 磁石のエネルギー
ただし、磁石を平べったくして反磁場が大きくなりすぎると自己減磁も大きくなってしまいますから、逆風もほどほどに抑えておかなければなりません。詳しい説明は省略しますが、磁石のエネルギーは逆方向の磁場とその時の磁化の掛け算、つまり図11の赤四角の面積で表されるのです。ですから、この面積が最大になるような反磁場を持たせてやれば、その磁石のエネルギーを最大に引き出せることになります。図ではa点での面積が最大になりますから、反磁場の大きさを示す直線(紫色の直線)がa点を横切るように磁石の形を決めればよいのです。このように、磁石の形には実は重要な意味があったのです。
磁化の測定
最後に、図8〜11のようなヒステリシスループを測定する方法について簡単に触れておきましょう。磁性体の磁化を計ろうとすれば、磁場をかけて試料を磁化しなければなりません。このような磁場の中で、試料が持っている磁化だけを取り出すには工夫が要ります。その一つが、試料を振動させる方法です。
図12のように、外部磁場を加えるための大きな電磁石の中に測定する試料をセットして、一定の周期で振動させます。そして試料の近くに設置したコイル(サーチコイル)に電磁誘導の原理で流れる電流を計ることで、試料の磁化を知ることができるのです。ヒステリシスループは外部磁場を変化させながら測定するので、サーチコイルには変化する外部磁場による電流も流れますが、試料の振動と同じ周期で振動する成分だけを取り出せば(これは電気的に簡単にできます)、試料だけの磁化がわかるのです。この方式の装置を「振動試料型磁力計(Vibrating Sample Magnetometer = VSM)」と呼びます。見た目はほとんど巨大な電磁石の塊、という感じです。
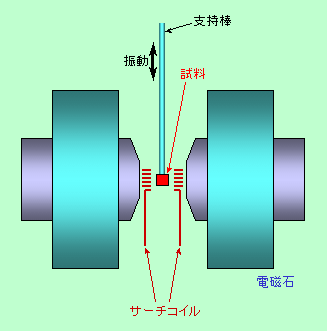
図12 振動試料型磁力計
この他に、外側の電磁石を回転させることで磁化した試料に捩れる力を与え、その力を捩れ計りで計ることで磁化を調べる方法もあります。外見はVSMとよく似ていて、トルクメーターと呼ばれます。この方式を使うと、試料の磁化の向きに関する情報も得られるので、図9のような微粒子の磁化反転の様子なども調べることができます。
雑科学ホーム
hr-inoueホーム