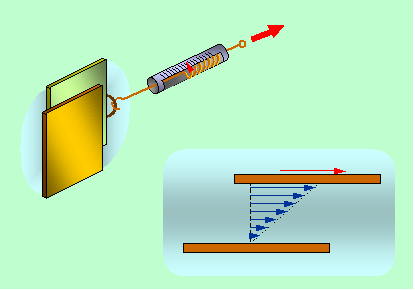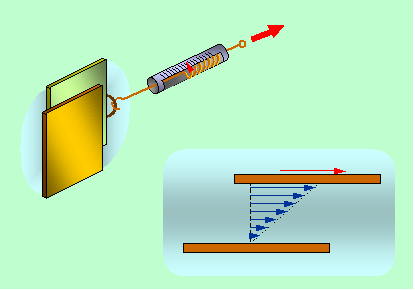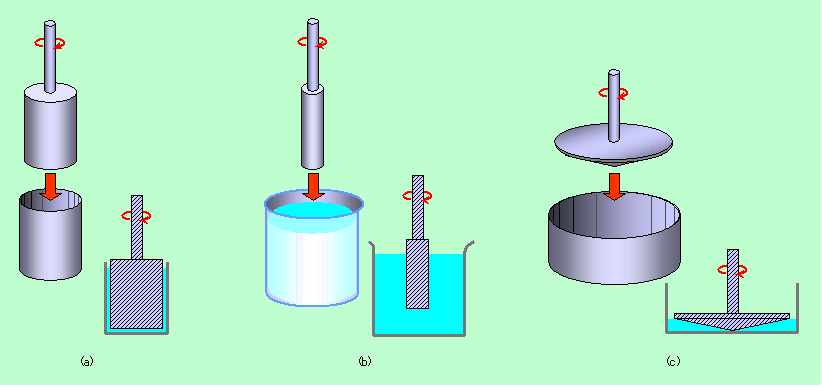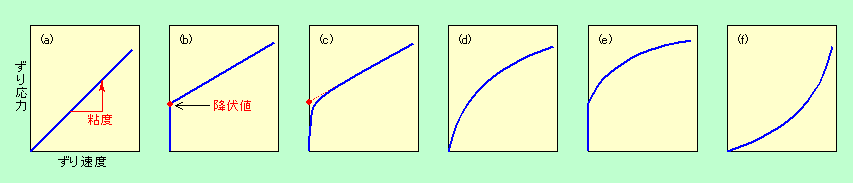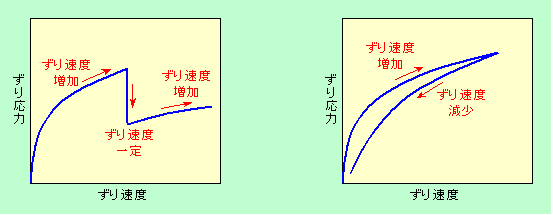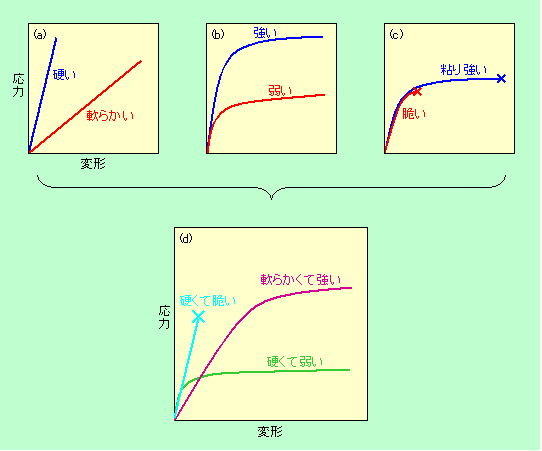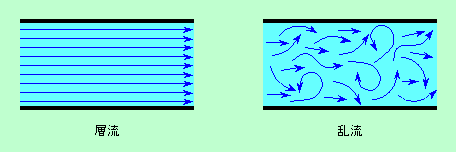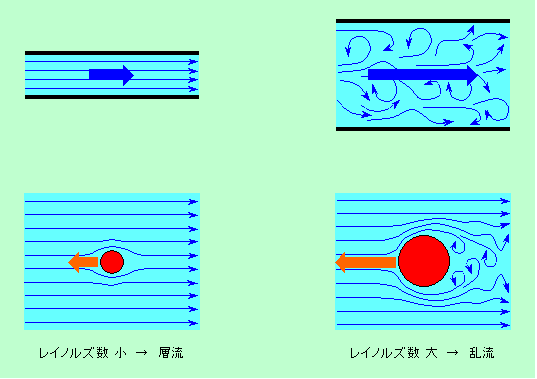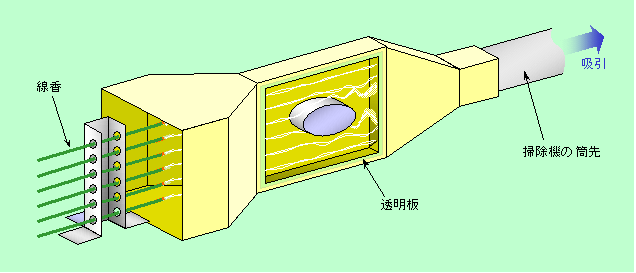雑科学ホーム
hr-inoueホーム
● 流動の話 ●
行く川の流れは・・・・・
川などの水の流れというのは、古くから人の心にいろいろな想いを起こさせて来ました。特に日本をはじめ東洋では、鴨長明の方丈記を引き合いに出すまでもなく、水の流れを題材にした話が多く見られます。そこで語られる「流れ」は、一見するといつも同じようでありながら、実は中身は同じではない、つまり定常状態として描かれています。この「定常状態」というのは、案外「流れ」の本質かもしれません。細かく見れば激しく変化している「乱流」であっても、長い目で、もっと大きな時間スケールで見れば、いつも似たような状態にあると言えるわけですから。
もちろん、「流れ」を見ながら「無常観」に浸っていたのでは、本サイトの目的には合いません。ここでは、「流れ」、「流動」とはどういうものか、ということについて、主に「粘性」という観点から見てみることにします。「行く川の流れ」は絶え間ないのですが、砂が巻き上がったり、いろいろな物が溶け込んだりすると流動の様子が変わります。また、流れるものが水ではなく他の流体だったら、まるっきり違った動きも見られます。空気の流れは「風」ですし、固体のはずのガラスだって「流れる」ことはあり得るのです。
「粘性」はズレに対する抵抗力
粘性、粘度については
粘弾性の話や
微粒子分散系の話の中でも触れていますが、ここでももう一度確認しておきましょう。
微粒子分散系の話の中では、次のように説明しています。
|
粘度というのは、2枚の板を互いに逆方向にずらす時の抵抗力のことで、その起源は、大雑把に言うと液の成分粒子(液体の分子や溶質、分散粒子)が互いに位置ずれを起こすのに逆らう力です。板のすぐそばの粒子は板にくっ付いて同じ速さで動きますが、板から離れるに従って速度は低下しますから、結果として隣り合う粒子間で速度の差が生じ、互いの位置関係がずれて来ます。これを妨げようとする力が粒子間で働き、粘度として現れるのです。厳密に言うと、速度の速い粒子が速度の遅い粒子にぶつかって後押しし、速度の遅い粒子が速度の速い粒子の動きを邪魔することで、トータルとして速度差をなくす方向に力が働く、ということになるのですが、感覚的には、速度が違う粒子間に働く摩擦力のようなもの、と考えればよいでしょう。この抵抗力は、2枚の板を接近させて速く動かすほど大きくなり、また、板の面積が大きいほど大きくなりますから、当然、これらの条件を単位量にした時の抵抗力として粘度が定義されています。
|
この説明でほぼ問題ないように思えますが、後の内容の都合上、もう少しだけ付け加えましょう。一つは粘度の単位に関することです。
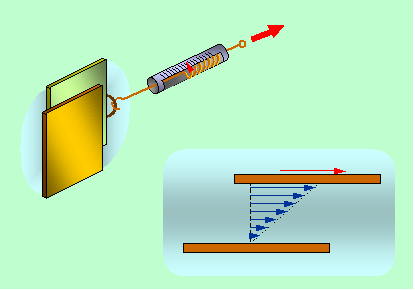
図1 粘度は「ずり応力」と「ずり速度」の比
粘度は2つの要素の比で表されます。一つは、上の説明にあるように単位面積の2枚の板をズラすのに必要な力で、「ずり応力」または「せん断応力」と呼ばれます。単位面積当たりの力ですから、この単位は圧力と同じになります(圧力の場合は面に垂直に力がかかり、ずり応力の場合は平行にかかる、という違いがありますが、数式の上では同じになってしまうのです)。もう一つの要素は、2枚の板をズラす速さに係わるものです。ただし、単純な速度ではありません。上にも書いているように、同じ速さでも2枚の板が接近していると抵抗は大きくなりますから、板の間隔も加味した「速さ」です。具体的には、2枚の板の相対的な速度を板の間隔で割った値で、図1に示したように、速度ゼロの一方の板から他方の板に向かうに従って、どれだけ急激に速度が増すか、ということを表しています。これを「ずり速度」または「せん断速度」と言い、速度(例えば「毎秒□m」)を距離(例えば「△m」)で割ったものですから、単位は時間の逆数(例えば「毎秒」)になります。粘度は、この「ずり速度」で「ずり応力」を割った値なのです。この後の話では、「ずり速度」や「ずり応力」が頻繁に出てきますので、このあたりのことは一応頭に入れておいてください。
ついでに単位の話をもう少し。粘度の単位としてよく知られているものに「P(ポアズ)」があります。流体の研究で知られるフランスの学者ポアズイユ(Poiseuille)にちなんだもので、普通はこの100分の1に当たる「cP(センチポアズ)」が使われます。例えば水の粘度はほぼ1cPです。これに対して、世界的に単位を統一する動きに従って、正式な論文などでは「Pa・s(パスカル・セカンド)」が使われています。「Pa」は圧力の単位(天気予報などでお馴染みの「ヘクトパスカル」の「パスカル」)で「s」は秒ですから、先に説明した粘度の定義そのままですね。実際にはこの1000分の1の「mPa・s(ミリパスカル・セカンド)」を使う場合が多く、これは「cP」と全く同じ大きさになります。
もう一つの付け足しは、気体と液体との違いです。どちらも分子同士で押したり引っ張ったりの相互作用をすることで粘性を示すのですが、液体の場合は本当に分子同士で引き合ったり、近付きすぎて押し合ったりする力が働くのに対して、気体では分子は互いに関与せずに飛び回っていますから、衝突による衝撃のみが相互作用の起源になります。例えば、ある分子のそばを別の分子が通り抜けようとする場合、液体では少しぐらい離れていても引力で引きとめようとする作用が働きますが、気体では、互いに接触しない限り知らぬ顔で通過してしまうのです。このような違いがあるため、温度が変わった時の粘性の変化が、気体と液体とでは逆になります。液体では、温度が上がって分子が元気よく動き回るようになると、互いの相互作用を振り切ってしまいますので粘度は下がります。一方気体では、分子の動きが激しくなると衝突する回数も増えますから、温度が上がると粘度も上がるのです。
粘度を計る方法
粘度を計るには、図1のような2枚の平板を使って適当なずり速度を与えた時のずり応力を調べればよいわけですが、実際にはそう簡単には行きません。板には必ず端があり、この部分では流れが乱れてしまいます。また板の速度が一定の値に達するにはいくらか時間がかかりますから、その助走も含めて、板は長い距離を移動する必要があります。つまり、端の部分の影響が無視できて、少々移動しても状況が変わらないような巨大な板を用意しなければならないのです。これは現実的にはムリですね。そこで実際には、端のない回転運動を利用した測定方法が採られています。図2に、よく使われる回転タイプの粘度計の例を示しました。
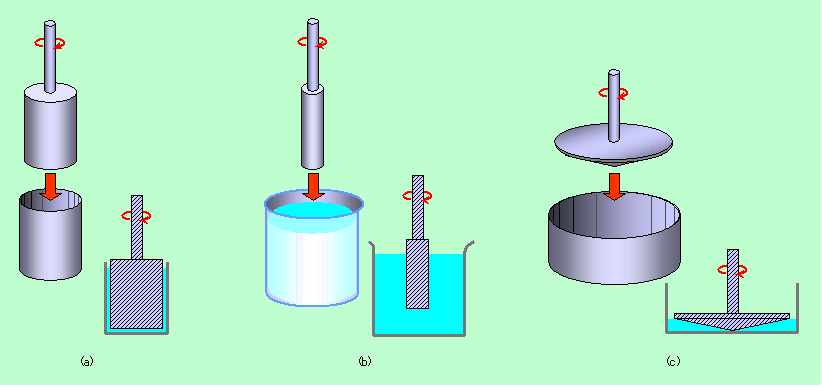
図2 回転型の粘度計いろいろ
図2(a)は二重円筒型と呼ばれるもので、2枚の板をくるりと巻いて筒にした形です。入れ子になった2つの円筒の間に液を入れ、どちらか一方の筒を回転させて、そこで加わる力をセンサーで測定します。筒どうしの間隔が十分に小さければ内筒と外筒の周長の差は無視できますから、平板と同じ扱いをすることができるのです。厳密に言えば筒の上下の端や液面の影響はあるのですが、その影響が出にくいように先端の形を工夫したりしています。これに対して、図2(b)はB型と呼ばれるタイプです。別の容器に入れた液にローターを浸して回転させるだけの簡単なもので、手軽なので広く使われています。このタイプの粘度計では、容器の壁の影響が出やすいですし、ローターのすぐ近くの液は動くのに遠くの液は動かないなど、場所によって状態が違うので、ずり速度の値が正確に出ません。そのため、粘度のわかっている液を基準にして、それとの比較で粘度を求めるのが普通です。さらに、図2(c)のように底が平ら(フラット)な容器の中に円錐(コーン)型のローターが入った、コーン-フラット型と呼ばれるタイプもあります(E型粘度計とも呼ばれます)。コーンとフラットの間隔が一定ではないので、何か都合が悪そうにも見えますが、実はココがポイントです。ローター表面の速度は外側ほど速く、半径が2倍になれば速度も2倍です。それに対してコーンとフラットの間隔も、半径が2倍の場所では2倍になりますから、速度を板間隔で割ったずり速度の値は全く同じ。つまりこのタイプの粘度計では、ローターの全ての場所が同じずり速度になるのです。なかなかスグレモノでしょう。
おおざっぱに言って、二重円筒型は精密測定向き、B型は簡易測定向き、コーン-フラット型はその中間、というところでしょうか。この他に円板を向き合わせて回転させるものや、回転ではなく振動を使って測定するものもありますが、流動を細かく調べようとすれば、やはり二重円筒型、最低でもコーン-フラット型は必要でしょう。回転数やローターの径、板間隔などをいろいろ変えて測定するのです。
余談になりますが、これらのタイプとは全く違った粘度計もあります。例えばオストワルド型やキャノンフェンスケ型などの流下式の粘度計。細いガラス管の中に液を吸い上げ、それが自重で流れ落ちる速さを測ります。ずり速度を簡単に変えることはできませんが、ちゃんと操作すれば、特に回転型の粘度計では測定が難しい低粘度領域で非常に高い精度で測定できます。また、玉を仕込んだ筒に液を入れ、筒を傾けて玉が転がる速さから粘度を求める方式の粘度計もあります。それぞれに得意分野がありますから、必要に応じて使い分ければよいのです。ただ今回の記事では、ずり速度を変化させた時の振舞いが話の中心になりますから、主に回転型の粘度計を頭において説明して行きます。
ずり速度で粘度が変わる
水などの単純な液体では、ずり速度を変えても粘度は変化しません。2倍のずり速度で動かせば2倍の抵抗(ずり応力)を受けます。このような素直な流動のことをニュートン流動と呼びます。ところが、世の中はこんな素直な流体ばかりではありません。一癖も二癖もある流体がたくさんあります。これらの流動の様子をわかりやすく表すのに、横軸にずり速度、縦軸にずり応力をとった流動曲線がよく使われます(縦軸、横軸が逆になっている場合もあります)。図3に、いろいろなパターンの流動曲線を示しました。定義からわかるように、流動曲線の傾きが粘度になります(傾きが急なほど粘度が高い)。
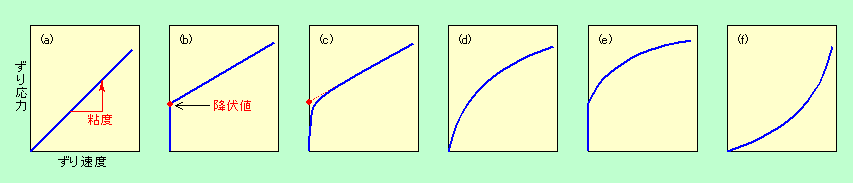
図3 いろいろな流動曲線
図3(a)はニュートン流動です。ずり速度とずり応力は完全な比例関係で、傾き、つまり粘度は、ずり速度に関係なく一定です。これに対して(b)は、ある力がかかるまでは全く動かず、そこから急に動き出すパターンです。初めのうちは力をかけても動かないのですから、見た目は固体なわけで、それが突然流れ始めるのです。これが塑性流動で、流れ始める点では固体的な構造が壊されることになりますから、この時のずり応力を降伏値(頑張って形を維持していた内部の構造が応力に負けて壊れる、という意味)と呼びます。ただし、これほど極端な例というのは実際の液状物体ではめったになく、初めから多少の流れは起こすことが多いので、(c)のようになるのが普通です。粘度の高い高分子の溶液や、微粒子の濃厚分散液などでは(c)のパターンになる場合があります。
塑性流動の場合でも、一旦流れ始めた後はニュートン流動と同じように直線になっていますが、これがカーブするケースもあります。(d)や(e)の場合がそれで、(d)は擬粘性流動、(e)は擬塑性流動と呼ばれます。また(c)も初めのうちは上に凸ですから、擬塑性流動の一種と言えます。このような上に凸の曲線になるケースでは、(塑性流動の場合の降伏値ほどはっきりした構造破壊ではありませんが)ずり速度を与えることによって構造が少しずつ壊されて粘度が下がる、という現象が起きているのです。内部にできている構造というのは、そんなに一発で完全に壊れるものではありませんから、(b)よりも(d)や(e)の方が一般的によく見られるわけです。
ちょっと変わった例として、(f)のような下に凸の曲線になる場合があります。ダイラタント流動(ダイラタンシー)と呼ばれるもので、非常に高濃度に粉末を分散させた液に見られることがあります。この現象は、流体を素早く動かすことで粒子の間の隙間が増えて、そこに液体が吸い込まれることで起こる、と説明されています(本当にこれだけなのかどうかはよくわかりません)。最近テレビや雑誌で、カタクリ粉などを水に溶いた液の上をパタパタと小刻みに足踏みして歩く様子が紹介されることがあります。ゆっくり足を入れると沈んでしまうのに、素早く足踏みすれば沈まない、ということで、ダイラタント流動の例として挙げられているのです。
素早い動きに対して高粘性を示す、というのは、
粘弾性と似ているようにも見えますね。実際に、先の水溶きカタクリ粉の上を歩く例などでは、粘弾性の要素も含まれていると思われます。ただし、粘弾性で速い動きに対して示されるのは「弾性」の要素であって、力の強さに応じて変形し、力を取り去れば元の形に戻る、という性質です。これに対してダイラタント流動の方はあくまでも「粘性」の要素ですから、力の大小によらず変形を続け(もちろん粘度が高いほど変形速度は小さいです)、力を取り去っても元には戻りません。もう少し具体的なイメージで説明しましょう。洗面器の中に液体が入っているとします。これにゆっくり指を突っ込むと、粘弾性体であれダイラタント流体であれ、指はズボッと入ってしまいます。ところが、素早く突いてすぐに引く、という動作をした場合は挙動が違って来ます。粘弾性体ではゴムのように瞬間的にへこんだ後、指を引くとすぐに元に戻りますが、ダイラタント流体は砂の塊のようになって指の侵入を阻止し、指を引くと、わずかにへこんだ状態、あるいはちょっとヒビが入ったような状態がそのまま残るのです。
流動のパターンとしてもう一つ有名なのがチキソトロピーです。マヨネーズなどが例として挙げられることが多いですが、攪拌を続けていると時間と共に構造が壊れて粘度が下がって来る現象で、流動曲線では図4のような形で現れます。
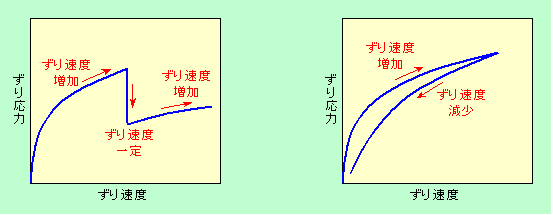
図4 チキソトロピーのパターン
チキソトロピーの典型的な特徴の一つは、図4(a)のように一定のずり速度で攪拌し続けると時間と共に粘度が下がって来ることです。ずり速度が変化しなくても、混ぜているだけでどんどん構造が壊れて行くのです。もう一つの特徴は、図4(b)のように、ずり速度を大きくして行った後に減少させると元のルートを通らないことです。一旦壊れた構造が元に戻るのに時間がかかるため、ずり速度の減少について行けないのです。もちろん時間と共に構造は徐々に回復して来ますから、ずり速度を減少させるスピードが遅くなるほど、行きと帰りのズレは小さくなります。
よく、図3(c)〜(e)のような上に凸のカーブを描くものを「チキソトロピー」と呼んでいる場合が見受けられますが、厳密に言えばこれは間違い。図4のような時間の影響を受ける振舞いが見られない場合はチキソトロピーとは言いません。つまり、ずり速度が決まると構造破壊の程度も一定に決まってしまい(何時間攪拌しても粘度が変わらない)、ずり速度を戻すと構造破壊状態もすぐに元に戻るようなケースはチキソトロピーではないのです。とは言っても、実際には図3(c)〜(e)のような流体では何らかのチキソトロピー性を持っているのが普通です。ずり速度を大きくすることで壊れるような構造であるならば、一定のずり速度で時間をかけても同じように壊れる可能性が高いからです。また降伏値を持っている流動の場合には、初めに破壊された構造がすぐには回復しないことがほとんどですから、やはりチキソトロピーを示すケースが多くなります。
チキソトロピーでは図4のように粘度が低下する場合がほとんどですが、まれに、攪拌によって粘度が増加することもあります。逆チキソトロピーなどと呼ばれる現象ですが、あまり一般的ではないので、ここでは省略します。
「硬さ」と「堅さ」は違う?
応力と変形の話が出て来たついでに、ちょっと脱線しますが、一般の固体の変形についても触れておきましょう。常日頃、「硬い」とか「軟らかい」とか、「脆い」とか、あるいは「硬いけど脆い」といった表現をよく使いますが、なんとなく曖昧ですね。これらの曖昧な言葉も、図3の流動曲線と同じようなグラフで表現すると、その実態がよく見えて来ます。「ずり応力」の代わりに単なる「応力」を(この応力は、ずり応力の場合もあれば、圧縮や引っ張りの応力である場合もあります)、「ずり速度」の代わりに「変形(歪み)」をとるのです。さて、図5のような形のグラフは、どんな性質に対応しているでしょうか?
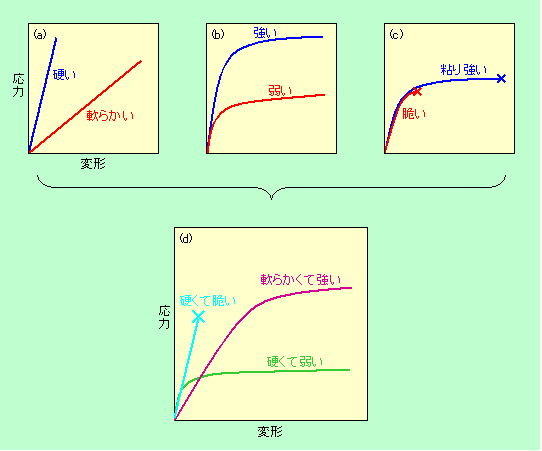
図5 固体の変形パターン
図5(a)は変形と応力が比例する単純な形で、バネのような性質、つまり弾性体のパターンです。傾きが急なほど、変形させるのに大きな力が必要ですから、「硬い(Hard)」材料と言えます。逆に簡単に変形を起こすのが「軟らかい(Soft)」材料です。
これに対して、流動曲線の場合と同じような降伏値が現れるのが(b)のパターンです。(a)のような弾性体でも、変形をどんどん進めて行けばやがては(b)のような降伏現象を示すのが普通です。液体の場合は、ずり速度を小さくすれば(チキソトロピーのように時間がかかるにしても)構造が復活して元に戻る場合が多いのですが、固体の場合は一旦降伏してしまうとほとんど元には戻りません。永久に変形が残ってしまうのです。このような降伏現象が早く(小さな応力で)起こるのが「弱い(Weak)」材料であり、なかなか降伏しないのが「強い(Strong)」材料です。
どんな固体であれ、力をどんどんかけて変形を進めて行けば、いつかは壊れます。降伏する前に壊れるものもあるでしょうし、降伏して大きく変形しながらも壊れないものもあるでしょう。このような壊れるまでの変形の大きさで性質を表現することもできます。壊れやすいものは「脆い(Brittle)」、壊れにくいものは「粘り強い(Tough)」、というわけです。壊れにくい物に対して「堅い」という字を当てる場合もあります。「硬さ」と「堅さ」は違うのです。
実際の材料は、これら3つの特徴を組み合わせて表現されます。例えば図5(d)の緑の線は、初めは変形しにくく硬いのですが、割と簡単に降伏してしまう根性なしです。これに比べて紫の線は、軟らかい割に粘り腰で、なかなか降伏しません。また水色の線は、硬いし降伏もしないのですが、ある時突然ポキンと折れてしまいます。このような固体の変形と対比して見れば、流動曲線の意味も見えやすくなるかもしれません。
流れ方は粘性だけでは決まらない
どのくらいの力がかかっている時にどのくらいの速さで流れるか、ということは流動曲線でわかります(もっと極端な言い方をすれば粘度でわかります)。しかし、その流れの様子までは決まりません。容器の形などの色々な要素が加わって、整然と流れるのか、グチャグチャと乱れた流れになるのかが変わってきます。
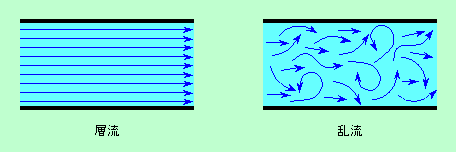
図6 層流と乱流
図6左のような整然とした流れを「層流」、右のような時間と共に不規則に変化する流れを「乱流」と呼びますが、層流になるのか乱流になるのかは何で決まるのでしょうか。それは、流体の部分部分がデタラメな方向へ勝手に動こうとする性質と、それを阻止して全体を同じ方向、同じ速さにまとめようとする性質との綱引きで決まります。もちろん初めからデタラメに動くわけではないのでしょうが、何かのきっかけで違った方向、違った速さの動きが発生した時に、それをそのまま維持する性質と、阻止する性質とのせめぎ合いが起こるのです。
一旦動き出したらその動きを維持しようとする性質は、当の物体が重ければ重いほど強くなります(慣性が大きい)。重い物は動き出したら止めにくい、ということは誰もが経験しているでしょう。つまり、流体の場合は密度が大きいほど乱流になりやすい、ということになります。
一方、乱れを阻止してまとめようとする性質は粘性そのものです。先に粘性の定義で、「速度の速い粒子が速度の遅い粒子にぶつかって後押しし、速度の遅い粒子が速度の速い粒子の動きを邪魔することで、トータルとして速度差をなくす方向に力が働く、ということで、感覚的には、速度が違う粒子間に働く摩擦力のようなもの」と書きました。これは粒子の速さだけでなく方向にも言えることで、速さや動く方向が違うものを、互いの相互作用で揃えようとするのが粘性ですから、まさに層流を作り出そうとする働きなのです。ですから、粘度が高い流体ほど層流になりやすい、と言えます。
このように考えると、粘度と密度は流れ方を決める上で逆の働きをすることがわかります。そこで粘度を密度で割った値を考えてやれば、この値がそのまま層流のできやすさ、乱流のできにくさを表す指標になります。これが動粘度です。例えば水と空気では、普通の粘度は2桁違いますが(もちろん水の方が大きい)、水の方が密度も3桁大きいので、動粘度という点では空気の方が10倍程度大きくなります。その結果、同じ条件で流れている場合は水の方が乱流になりやすい、ということになるのです。
動粘度というのは流体そのものの性質を表す量ですが、層流になるのか乱流になるのかを見積もるには、流れの速さや通路の幅も考えなければなりません。当然ながら、流れが速くなるほど勢いのついた流体が適当な方向へ突き進む可能性が高くなりますから、乱流になりやすくなります。また管の中を流れるような場合を考えると、管が太いほど横方向に向かう流れが起きやすいですから、やはり乱流になりやすくなります。田んぼの中の小川では、水は川上から川下に向かって、比較的整然と流れます。しかし、川幅100mの大河になると、部分部分を見れば、必ずしも流れは川下に向かっているとは限りません。横に流れている部分もあれば、渦を巻いていることもあるでしょう。さらに洪水にでもなれば、全体としては川下に向かうとしても、あちらこちらでムチャクチャな流れができるのです。
「レイノルズ数」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。これは、先ほど出て来た3つの要素、「動粘度」と「流れの速さ」と「通路の幅」とを全部盛り込んだ数値です。「流れの速さ」と「通路の幅」が分子に、「動粘度」が分母に来ますから、数値が大きいほど乱流になりやすくなります。具体的な数値を挙げてみましょう。直径1cmの管の中を秒速5cmで水が流れているとすると、この時のレイノルズ数は約500になります(水の粘度は1cPですが、グラムやセンチメートルを使った単位に合わせると約0.01になります)。層流と乱流の境目の目安はレイノルズ数2000〜3000あたりですから(場合によっては1000ぐらいとも言われますが)、このくらいですと、ほぼ層流になります。ところが、管径が20cmになったり、流れの速さが秒速1mになったりすると、レイノルズ数は10000になり、乱流の領域に入って来ます。ホースの中をゆっくり流れる水は層流ですが、土管の中を勢いよく流れる水は乱流になるのです。これが空気になると様子が変わって来て、後の条件でもレイノルズ数は1000に届きませんので、乱流にはなりにくい、ということになります。
同じような考え方は、止まっている流体の中を別の固体などが移動する場合にも使われます。例えば、池の中を魚が泳いだり、海の上を船が進んだりするケースで、この場合は、先の「通路の幅」に相当するのは魚や船の「大きさ」になります。もちろん魚や船の形なども流れを決める大きな要素になるので簡単には行きませんが、単純に球形の物体が移動するような場合には、その周りにできる流れの様子はレイノルズ数でおおよそ見当を付けることができるのです。当然ながら、「大きなもの」が「高速」で、「動粘度の低い(粘度が低く密度が大きい)」流体の中を移動するほど乱流ができやすくなります(図7)。メダカがゆっくり泳いでいる時のレイノルズ数は500ぐらいですが、飛んでいるジェット機の周りでは100000000(1億)もの値になるのです。
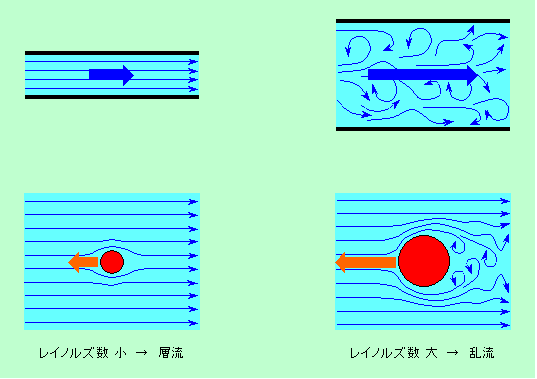
図7 レイノルズ数と流れの様子
レイノルズ数には3つの要素が絡んでいますから、それぞれの値が全く違っていても、全体として同じ数値になる場合が出て来ます。例えば、管径1cm、流速1m/sの場合と、管径10cm、流速10cm/sの場合がそうです。条件はずいぶん違っていますが、面白いことに、このようなケースでも流れの様子は同じようになるのです。
風洞を作る
層流や乱流を実際に見るにはどうしたらよいでしょうか。もともと水や空気などの流体は均一なものですから、そのままでは動きは目にはよく見えません。そこで、層流と乱流の変化などを観察するために、目に見えるものを混ぜ込むことになります。よく使われるのが、細長い水路を流れる水の中に線状にインクを流す方法です。うまくいけば、インクが一直線にきれいに流れたり、乱れて渦を巻いたりする様子が観察できます。ただ、水を流しっぱなしではもったいないですし、ポンプで汲み上げて循環させるのも大掛かりになりますから、ここではもっと簡単な、空気の流れを使った風洞を紹介することにします。風洞と言っても航空機の飛行解析をするような本格的なものではなくて、紙製のオモチャのようなものですが・・・・。30年程前にNHKの番組(平日に毎日放送されていた「みんなの科学」という番組の中の「たのしい実験室」というシリーズ)で同様のものが紹介されたことがありますので、記憶にある人もいるかもしれません。
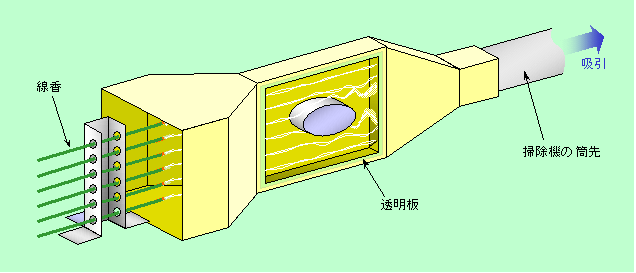
図8 簡単な手作り風洞
構造は非常に単純なもので、厚手の紙などで図8のような形を作り、一方の端に置いた線香の煙を、反対側に取り付けた掃除機で吸い出すのです。中央の部分にはプラスティックなどの透明な板が貼ってあり、中を通る線香の煙を見ることができますから、ここに発泡スチロールなどで作った色々な形の障害物を置くと、気流の乱れを観察することができます。
ただし、線香に火をつけますので、火災には十分注意しなければなりません。できれば全体を金属やガラスで作りたいところですが、なかなかそうも行かないでしょうから、最低限、線香の取り付け台だけは金属で作ることをお勧めします。私の場合は、缶詰の空き缶を壊して取ったブリキ板を使って作った記憶がありますが、他にもいろいろな代用品が工夫できると思います。
雑科学ホーム
hr-inoueホーム