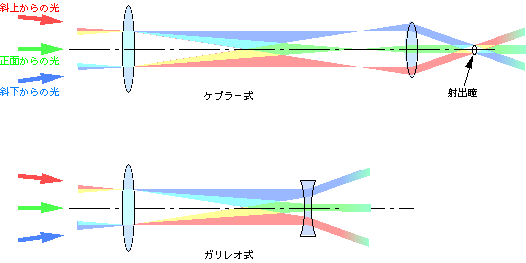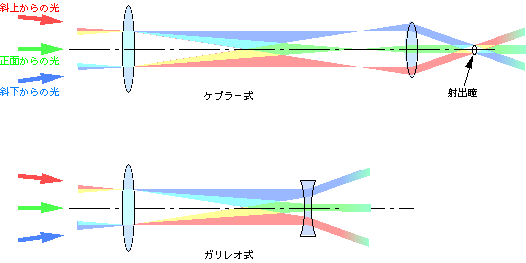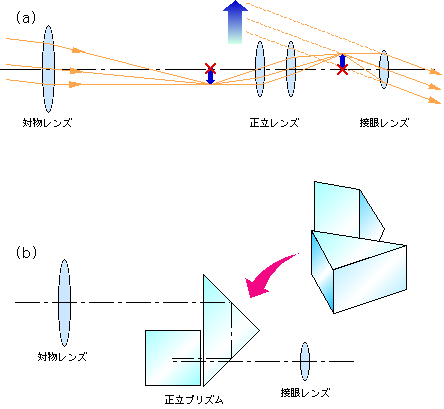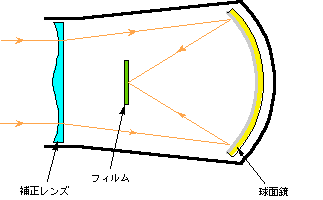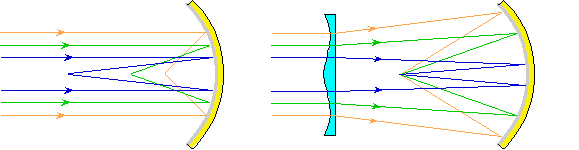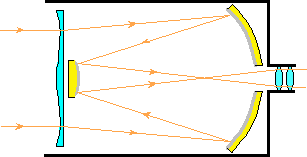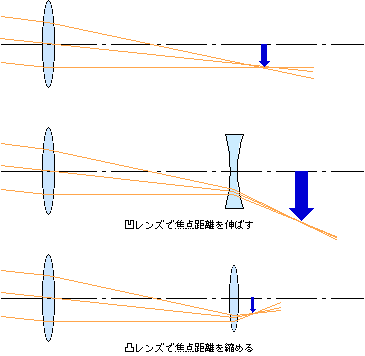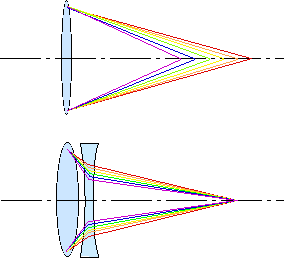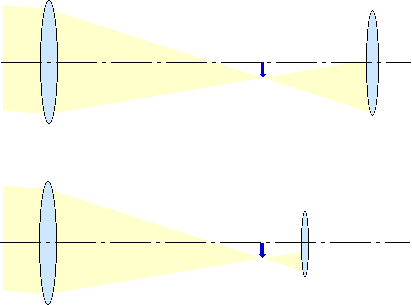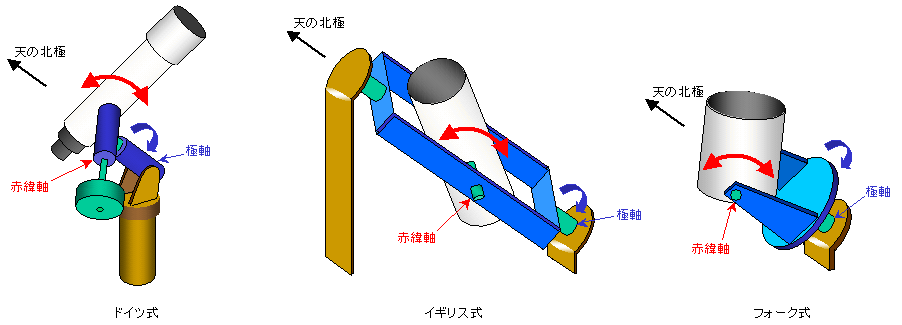雑科学ホーム
hr-inoueホーム
● 天体望遠鏡の話 ●
天体望遠鏡と地上望遠鏡
天体望遠鏡の話をするに当たって、まず地上望遠鏡と対比させてみましょう。
光学機器の話で望遠鏡のことには触れていますが、この時は、特に「天体望遠鏡」、「地上望遠鏡」、という区別はしませんでした。
光学機器の話の中に出てくる望遠鏡の図は、すべて像が逆さまの「天体望遠鏡」です。それでは、なぜ天体望遠鏡では、わざわざ像を逆さにするのでしょうか・・・。実は、わざわざ逆さにしているのではなく、性能優先で考えると自然に倒立像になるのであって、地上望遠鏡の方が、それをわざわざ正立像に戻しているのです。
どんなに優秀なレンズでも、光の透過率が完全に100%にはなりません。必ずいくらかは吸収されたり反射されたりしてロスします。レンズ表面にゴミなどが付いていればなおさらです。特に、ごく弱い光を集めなければならない天体望遠鏡では、光のロスは重大問題ですから、不必要にレンズを増やすことは避けたいところです。そうなると、一組の対物レンズと接眼レンズとを組み合わせた最もシンプルな形が最も望ましい、ということになります。この形では像が逆さまになりますが、元々空の星に上下の向きはありませんから、これでいいのです。
昔、ガリレオ・ガリレイが作った望遠鏡は、対物レンズが凸レンズ、接眼レンズが凹レンズの、正立タイプのものでした。シンプルというのならこれで十分シンプルで、しかも正立像。他に問題がないのであれば、こっちの方がよさそうです。ところが、重大な問題があるのです。それは、見える範囲、つまり視野の広さです。図1を見てください。上が対物、接眼共に凸レンズのタイプ(ケプラー式と呼びます)、下が接眼レンズが凹レンズのガリレオ式のものです。ケプラー式の望遠鏡では、対物レンズにまっすぐに入って来た光(図の緑の光)も、斜上や斜下から入って来た光(図の赤と青の光)も、接眼レンズを出た後に必ずある円の中を通ります。この円を射出瞳と言い、ここに目を持って来れば、全ての光を同時に見ることができます。ところがガリレオ式の望遠鏡では、光が集められる前に接眼レンズに入ってしまい、接眼レンズを出た後も広がる一方です。そのため、目を中央に置くと、斜めから来る周辺の光は見ることができません。その結果、視野の周辺が暗くなり、見える範囲が狭くなるのです。倍率が高くなるほど、接眼レンズの後ろの光の広がりは急角度になりますから、余計にこの症状は重くなってしまいます。このような理由で、ガリレオ式の望遠鏡はオモチャの望遠鏡やオペラグラス程度にしか使われないのです。
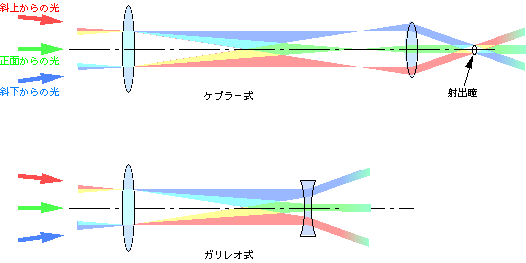
図1 ガリレオ式の望遠鏡は視野が狭い
それでは、ガリレオ式ではない地上望遠鏡はどのようになっているのでしょうか。これには2つのタイプがあります。一つは正立レンズを用いるもの、もう一つは正立プリズムを用いるものです。正立レンズを用いるタイプは図2(a)のような構造になっています。これは大雑把に言えば、2個の望遠鏡をつなげたもので、一つ目の望遠鏡で作った倒立像を、2個目の望遠鏡でもう一度ひっくり返しているのです。このタイプの望遠鏡で面白いのは、正立レンズと接眼レンズがはめ込まれたドローチューブを抜き出すと、ちょっとした顕微鏡になる、ということで、このような商品が売られているのを見たことがあります。
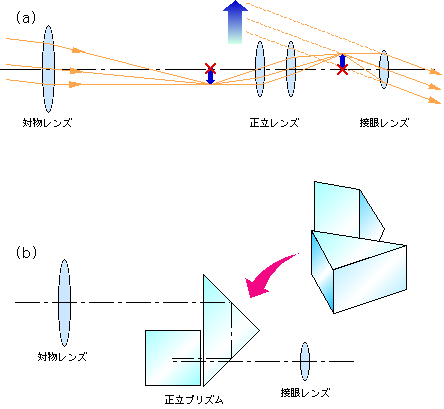
図2 地上望遠鏡の2つの型
(a) 正立レンズ型、 (b) 正立プリズム型
正立プリズムを用いたものが、図2(b)です。この他にもいくつかのプリズム型がありますが、いずれも鏡の反射を利用して像をひっくり返す点は同じです。双眼鏡によく使われており、バードウォッチング用のフィールドスコープにも、このタイプのものがあります。
これらの地上望遠鏡は、対物レンズと接眼レンズの他に、余分なレンズやプリズムが入っていますから、弱い光を対象にした天体望遠鏡には向かないのです。
屈折と反射とカタ・ディオプトリック
天体望遠鏡には屈折型と反射型があることはご存知ですね。それぞれの特徴についてはいろいろな本や雑誌に載っていますから、ここでは簡単にまとめるだけにしておきましょう。
表 屈折望遠鏡と反射望遠鏡
|
屈折 |
反射 |
| 対物 |
凸レンズ |
放物面鏡 |
| 大口径化 |
困難 |
容易 |
| 対物焦点距離 |
一般に長い |
一般に短い |
| 得意な対象 |
惑星など |
星雲など |
ところで、天体望遠鏡の型は屈折と反射で終わりかというと、実はもう一つあります。シュミット・カメラに代表される、カタ・ディオプトリックというタイプです。「カタ」は「反射」、「ディオプトリック」は「屈折」、の意味ですから、「カタ・ディオプトリック」は「反射・屈折合成系」と言われたりします。何のことはない、鏡とレンズとを両方持った光学系のことです。シュミット・カメラの光学系を図3に示しました。
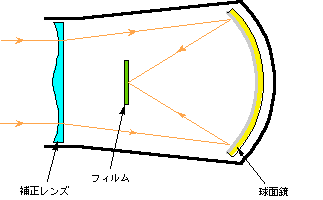
図3 シュミット・カメラ
シュミット・カメラの主鏡は放物面鏡ではなく球面鏡です。放物面鏡は斜めから入ってくる光に対して像がボケやすいという性質があり、あまり視野を広げると、周辺がボワッと広がって実用になりません。球面鏡にするとこの問題がなくなり、広い視野を確保できるので、広い範囲の星空の写真を撮るのに適しているのです。ところが、球面鏡というのは、それだけでは光を一点に集めることはできません。図4に示すように、中心付近の光は遠くに、周辺の光は近くに集まってしまいます。そこで、周辺に行くほど外に向かって広がるように光を曲げてやれば、うまく一点に集めることができるようになります。この働きをするのがシュミット・カメラの補正レンズ(シュミット・レンズ)です。シュミット・レンズは、図のように中心部が度の強い凸レンズ、そこから外に向かって度が徐々に弱くなり、周辺では逆に凹レンズになっています。中心付近の光は、度の強い凸レンズで既に少し集められていますから、球面鏡で反射すると元よりも近いところに集まります。ちょうど、遠視の人が凸レンズのメガネ(老眼鏡)をかけるのと同じですね。一方、周辺の光は凹レンズで広げられますから、球面鏡でも容易には集められず、(近視のメガネのように)焦点が遠くに移動するのです。
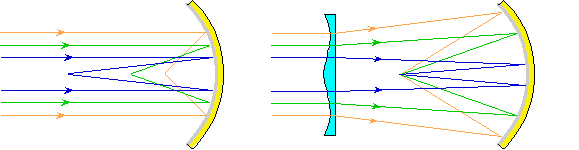
図4 シュミット・レンズの働き
このようなシュミット・カメラの仕組みを利用した望遠鏡もあります。シュミット・カセグレンと呼ばれるタイプの望遠鏡で、球面鏡で反射した光を、シュミット・レンズの裏側に付けた凸面鏡でもう一度反射して、球面鏡の中心に開けた孔から外に引き出します。図5がその光学系で、実は私もこのタイプの望遠鏡を使っています。
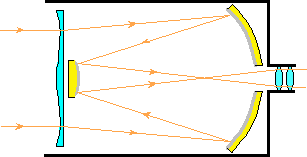
図5 シュミット・カセグレン
また、補正レンズ全体が凹レンズ型で、周辺に行くほど凹レンズの度が強くなるマクストフ・カセグレンもあります。一眼レフカメラの望遠レンズの中にも、このようなカタ・ディオプトリック構造のレンズがあるので、目にしたことがある方もいるでしょう。
補正レンズは構造が複雑で、作るのは難しそうですね。実際に普通の研磨でこの形を削りだすのは大変で、精密なものは非常に高価です。しかし、比較的安価なものでは、うまい方法が使われています。元になるガラスの平板を型の上に載せ、吸引機で裏から吸い付けると、ガラス板が型の形状に変形します。この状態で表側から平らに研磨し、吸引を止めて取り外すと、所望の形状になっている、というわけです。
望遠鏡の最大のポイントは口径
光学機器の話や
カメラの話でも触れていますが、望遠鏡の性能を決める最大の要素は対物レンズ(または対物鏡)の直径です。実際にはレンズを固定する枠などがありますから、実質的な直径はそれよりも小さくなる場合が多いので、この実質的な直径を「口径」、あるいは「有効径」などと呼びます。接近した2点を見分ける能力(分解能)も、光を集める能力(集光力)も、口径で決まります。
これに対して、よく話題になる倍率というのは、対物の焦点距離を接眼レンズの焦点距離で割った値ですから、焦点距離の短い接眼レンズを使えば、いくらでも大きくできます(焦点距離の短い接眼レンズを作るのは、焦点距離の長い接眼レンズを作るのよりも簡単で、値段もずっと安いのが普通です)。しかし、先の分解能の制限がありますから、むやみに倍率を上げても、像がボケるだけで使いものにはなりません。一般的に、mm単位で表した口径の2倍が限界、とされています。これ以上倍率を上げると、分解できていない2点が、分解されないままに拡大され、人間の肉眼で、その分解されていない事実が認識できるようになってしまう(つまり、離れているはずの2つの丸が、くっ付いて雪ダルマに見える)のです。
ここで一つ疑問が出てくるかもしれません。口径が全て、というのであれば、口径が大きいものが作りやすい反射式の方が圧倒的に有利なはずです。事実、世の中の大望遠鏡はほとんど反射式です。なのに、店をのぞくと、屈折望遠鏡がたくさん売られていますね。なぜでしょう?
反射式の望遠鏡は放物面鏡を使うので、周辺に行くほど象がボケる「コマ収差」という宿命があるのです(屈折望遠鏡にもありますが、程度が軽い)。だからといってシュミット・カメラのタイプにして完全に収差を補正するのも、一般向けの望遠鏡のレベルではとてもムリ。つまり、反射望遠鏡もシュミット・カセグレンなどの望遠鏡も、ピントが甘いのです。その点、屈折望遠鏡は、最も問題となる色収差さえ補正すれば、非常にシャープなピントが得られますから、特に惑星の写真などでは有利なのです。これが一般向けで屈折望遠鏡が重宝される理由です。一方プロの世界では、美しい写真を撮ることよりも、いかに微弱な、遠い銀河などからの情報を集めるかが重要ですから、できるだけ口径の大きな反射望遠鏡が主流になるのです。
倍率の話が出たついでに、もう一つ、「有効最低倍率」の話をしておきましょう。望遠鏡の役割は、たくさんの光を集めることと、拡大することです。拡大の方は、例えば惑星や月の表面を観察する場合に重要です。しかし、拡大しても意味のない対象があります。その一つは恒星で、あまりに遠すぎて、いくら拡大しても「点」のままです。これを望遠鏡で見る意味は、肉眼では見えないような暗い星まで見える、ということと、星の位置の正確な測定に有利、ということでしょう。拡大してもあまり意味のないもう一つの対象は星雲です。星雲はもともと光が淡く、ボンヤリしていますから、あまり拡大すると余計に薄まって見づらくなるのです。また、星雲の中には、かなりの面積を持ったものがたくさんあります。例えば有名なアンドロメダ星雲は、満月の5倍もあるのです。こんな大きなものを、わざわざ拡大して見づらくする必要はありません。できるだけ倍率を下げ、口径の大きな望遠鏡で多くの光を集めるのがよいのです。
倍率を下げるには、対物レンズの焦点距離が短い望遠鏡で、焦点距離の長い接眼レンズを使えばよいのですが、倍率をいくらでも下げてよいかというと、そうは行きません。倍率が低くなると、接眼レンズから飛び出してくる光の束がどんどん太くなってきて、ついには図1の射出瞳が人間の目の瞳よりも大きくなってしまいます。こうなると、せっかく集めた光の一部しか目に入りませんから、倍率を下げる意味がなくなってしまうのです。これが有効最低倍率の考え方で、その値は、口径を7mm(人間の瞳の最大直径)で割ったものになります。例えば口径80mmの望遠鏡では、有効最低倍率は11.4倍です。
以上のように、望遠鏡の性能はまず口径。そして、倍率に関わる対物の焦点距離は、月や惑星を見るのであれば長めのもの、星雲を見るのであれば短めのものがよい、ということになります。屈折望遠鏡は一般に焦点距離が長めなので、月や惑星向き、ということになりますが、星雲などにも適した焦点距離の短いものも売られています(ただし、値段は少々高め)。また、望遠鏡の焦点距離を長くしたり短くしたりできるアダプターも出回っています。図6のように、長くする場合は凹レンズ、短くする場合は凸レンズを付ければよいわけです。
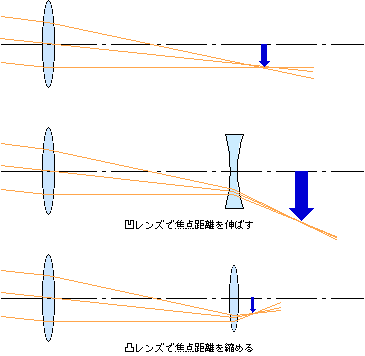
図6 焦点距離を変換するアダプター
焦点距離を長くするアダプターとしては、眼視用のバーローレンズが有名ですが、主として写真用のもの(テレコンバーター、テレエクステンダーなど、メーカーによって呼び名はまちまちです)もあります。また焦点距離を短くするアダプターとしては、テレコンプレッサー、レデューサーなどと呼ばれるものが出回っています。
ところで、望遠鏡の性能は口径で決まる、ということですが、世の中にはどのくらいの大きさの望遠鏡があるかご存知ですか。一枚鏡の反射鏡では、日本が1999年にハワイに作った口径8.2mのすばる望遠鏡が最大です。多数の鏡を組み合わせたものとしては、同じハワイのケック天文台にある10mのものが最大のようです。その前は、というと、おそらく1976年の旧ソ連、ゼレンチェクスカヤ天文台の口径6mの望遠鏡ではないかと思います。しかし、古くからの天文ファンの間では、やはりアメリカ、パロマ山天文台の5mヘール望遠鏡に対する思い入れが強いのではないでしょうか。約30年にわたって世界最大の望遠鏡として君臨し、いろいろな本や雑誌に天体写真を提供していましたから、それらの写真は、星好きな人なら必ず見たことがあるでしょう。私にとっても子供のころからの憧れの望遠鏡で、大人になってアメリカに行った際に、わざわざ見に行ってしまいました。ちなみに、日本で最大のものは、岡山 竹林寺山の188cmで、これも見に行きました。(注:2004年秋に兵庫県の西はりま天文台に口径2mの望遠鏡が完成しています)
屈折望遠鏡の敵 色収差
前記のように、ピントのシャープさで有利な屈折望遠鏡ですが、最大の難関は色収差の解消です。必要ないかもしれませんが、一応説明しておくと、光の屈折率は波長(つまり色)によって違うため、波長の異なる光を同じ一点に集めることができない、という現象で、色収差の大きい望遠鏡をのぞくと、像の周辺が虹で縁取られたように見えます。
色収差を少なくする最も簡単な方法は、収差の出方が逆になる凸レンズと凹レンズを組み合わせることです。この時、両方のレンズに同じガラスを使ったのでは、色収差をなくすために凸レンズの度と凹レンズの度を同じにしなければならず、これでは光を集めることができません。そこで、凸レンズの方には、屈折率は大きいが、色による屈折率の差(分散と言います)は小さいガラスを、凹レンズの方にはその逆の性質のガラスを使います。これがアクロマート・レンズです(図7)。「ア」は「無」を意味し、「クロマート」は「色」を意味する言葉ですから、「アクロマート」は、「色無し」、「色消し」、という意味になります。(
ガラスの話参照)
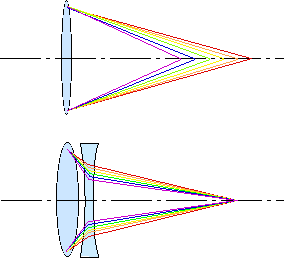
図7 色収差とアクロマート・レンズ
波長による屈折率の違いは実際にはかなり複雑なので、アクロマート・レンズですべての波長の収差を消すことはできません。そこで、特に目立つ2つ(通常は赤と青)の光のずれをなくすように設計されています。ですから、アクロマート・レンズではそれ以外の波長の光には収差が残っています。そこで、さらに多くの波長の光について補正するために、レンズを3枚以上に増やしたり、蛍石(フッ化カルシウムの結晶で、フローライトと呼ばれます)などの特殊な材料のレンズを使ったりします。このようにして3つの波長で収差をなくしたレンズをアポクロマート・レンズと呼びます(「アポ」とは、「遠く離れた」という意味)。ただ単に3枚のレンズを使っただけのものはアポクロマートとは呼べません。(厳密に言うと、アクロマートやアポクロマートでは、色収差以外に球面収差やコマ収差の補正も条件として入っていますが、ややこしくなるので、ここでは省略しました)
蛍石などを使ったアポクロマート・レンズでは収差が非常に小さいので、焦点距離の短いレンズでも問題なく作ることができます。先にちょっと触れた、焦点距離の短い屈折望遠鏡はこの手のもので、同じ口径の普通のアクロマートと比べて、値段が一桁程度高くなっています。ただ、見え味の差は歴然で、高価なだけのことはあります。
だんだん大きくなった接眼レンズ
望遠鏡の心臓部はやはり対物レンズなので、その話をして来ましたが、もう一方の端にある接眼レンズについても簡単に見ておきましょう。光路図ではレンズ1枚で表していますが、実際は1枚レンズの接眼などは(オモチャを除いては)ありません。接眼レンズのレンズ構成や種類については、専門書やメーカーのカタログに詳しく載っているので、ここでは触れないことにして、少し別の話題を取り上げましょう。それは、接眼レンズの大きさについてです。
一昔前までは、天体望遠鏡の接眼レンズといえば、外径24.5mmのものに限られていました。ところが、月や惑星だけでなく星雲などを対象にするようになると、焦点距離が長く、広い視野のレンズが要求されるようになります。接眼レンズの焦点距離が長くなると、図8のように対物レンズが作る実像からの距離が遠くなりますから、接眼レンズの径を大きくしなければ、光を有効に取り込むことができません。また、広い視野を確保する上でも、大口径の接眼レンズが必要になります。
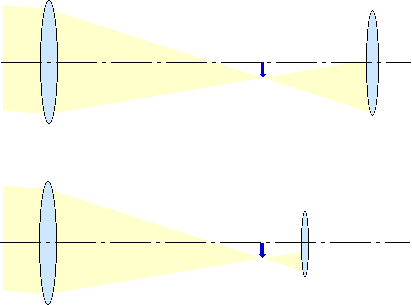
図8 焦点距離の長い接眼レンズは大口径が必要
というわけで、昔の24.5mm径では限界があり、望遠鏡に標準としてさらに大口径の接眼レンズが装着できるようになって来ました。現在では、31.7mm、36.4mm(ネジ込み式)、50.8mm、というラインナップができています。50.8mmなどは、ちょっとポケットに入れて、というわけには行きませんね。レンズ自体も当然大きいので、お値段の方も結構高くなるのは仕方がありません。
赤道儀と経緯台
最後は、望遠鏡を載せる架台の話です。天体望遠鏡の架台には、赤道儀と経緯台があることはご存知でしょう。赤道儀は、地球の自転軸と平行に設置された極軸と、それに垂直な赤緯軸から成り、一旦星を捉えれば、あとは極軸周りに回転させるだけで、地球の自転によって動く星を追いかけることができます。図9のように、大きく分けてドイツ式とイギリス式があり、イギリス式の変形としてフォーク式があります。
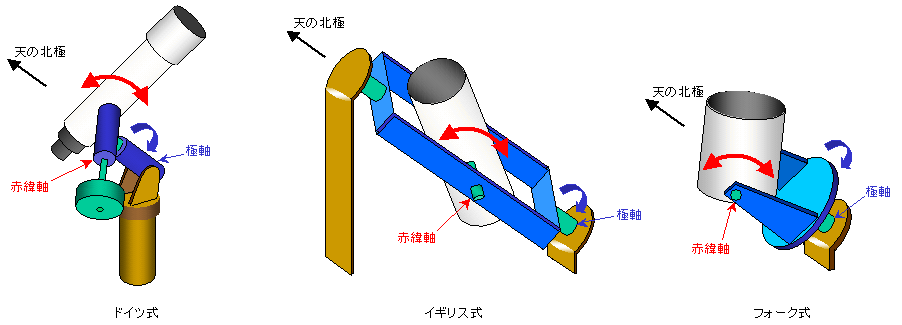
図9 赤道儀の基本型
ドイツ式は赤道儀本体がコンパクトですから、個人用の小型の望遠鏡に最も普通に使われています。また、長い鏡筒でも問題ないので屈折望遠鏡には適しており、口径が1m程度の世界最大級の屈折望遠鏡も、ドイツ式架台に載っています。これに対してイギリス式は短い鏡筒向きで、主に大型の反射望遠鏡に用いられます。また、イギリス式の架台の半分を取り去った形のフォーク式赤道儀も多く使われています。これらは以前は専ら大型望遠鏡用だったのですが、鏡筒が極端に短いシュミット・カセグレン望遠鏡の場合はフォーク式にしてもさほど架台が大きくならないので、個人用にも使われるようになっています。
経緯台は、単に水平軸と垂直軸から成る架台ですから、特に説明は不要でしょう。これで星を追いかけようとすると、2つの軸を同時に動かさなければならず、また、それにつれて、視野の中で像が回転して行きます。秒単位で撮影が終わる月などならばともかく、数分、数十分の露出が必要な星雲などの写真を撮るのはとても無理です。
さて、一般に経緯台は安価で手軽な初心者向き、赤道儀は高級で上級者向き、と言われています。確かに赤道儀は、セッティングなどに多少の知識を要し、重量もあり、天体写真も撮れますから、間違った解釈ではないでしょう。プロが使う天文台の望遠鏡も全て赤道儀・・・でした。ところが最近はちょっと違います。日本が誇るすばる望遠鏡は経緯台。旧ソ連のゼレンチェクスカヤ6m望遠鏡も経緯台。ケック天文台の10m望遠鏡も経緯台。パロマ山の5m望遠鏡は赤道儀ですが、それ以降の大型望遠鏡は全て経緯台なのです。その訳は、・・・コンピューターによる制御技術の発達です。つまり、コンピューターによって2軸を精密制御することで、赤道儀なしでも完璧な追尾ができるようになったのです。もちろん、視野の中の像の回転も補正されます。こうなって来ると、大型で建設費の嵩む赤道儀はもはや必要ない、という訳です。
個人用の赤道儀にも、コンピューター制御の装置が搭載される時代になりました。そのうちに、コンピューター制御の個人用経緯台が普及することになるかもしれませんね。
雑科学ホーム
hr-inoueホーム