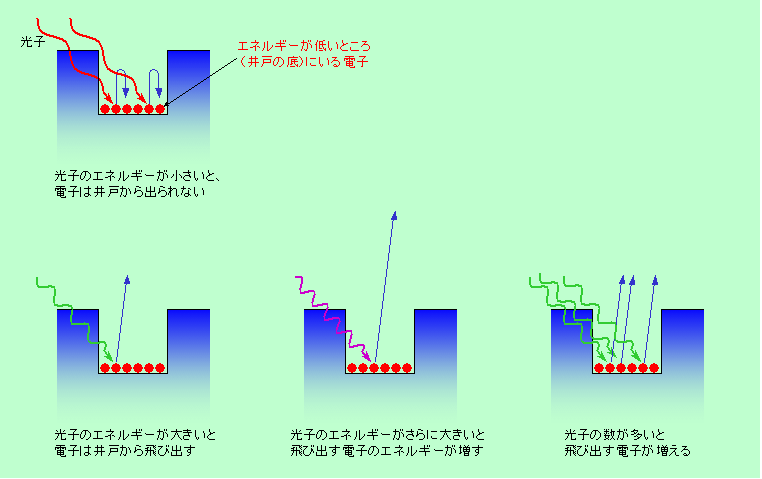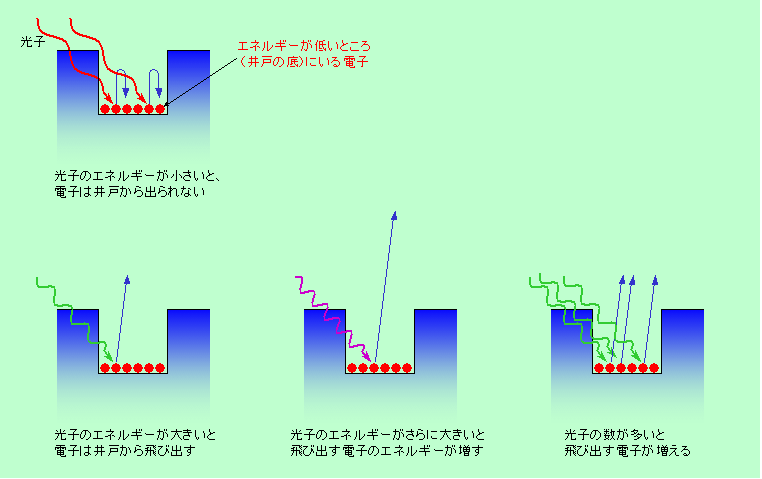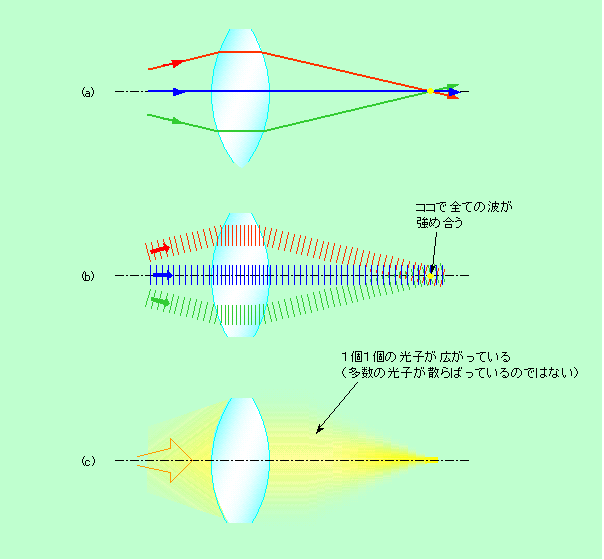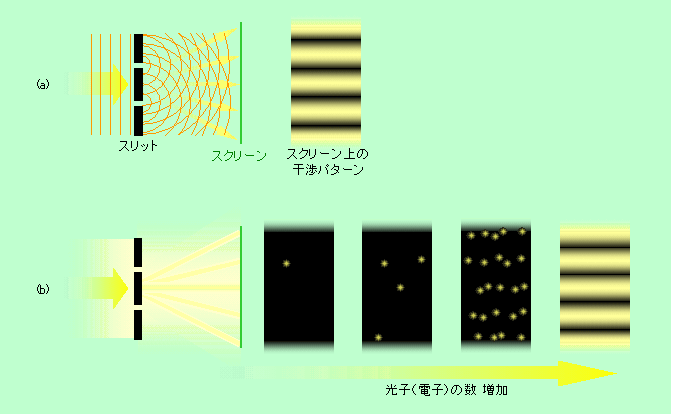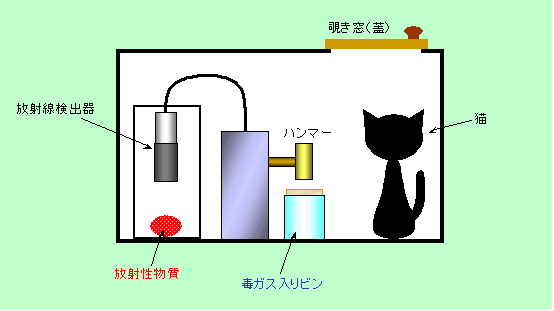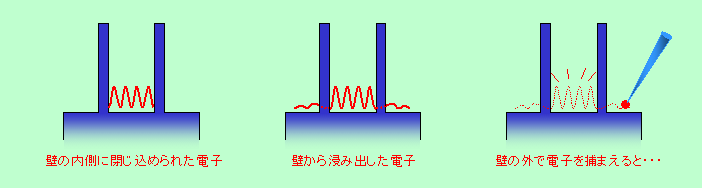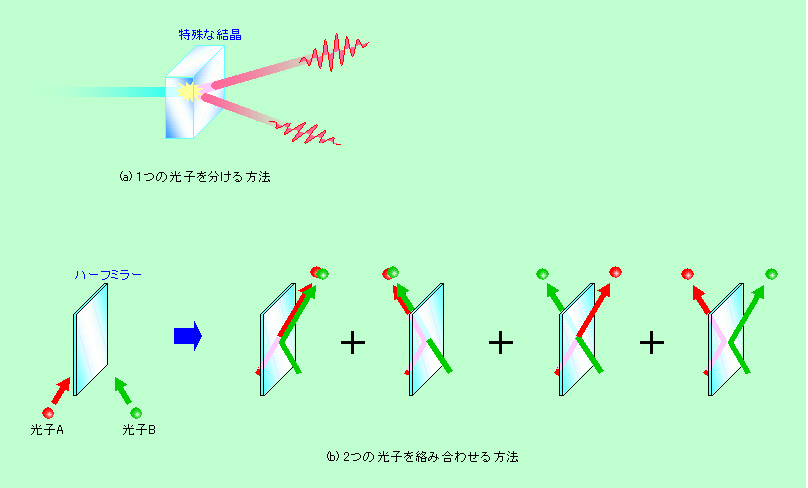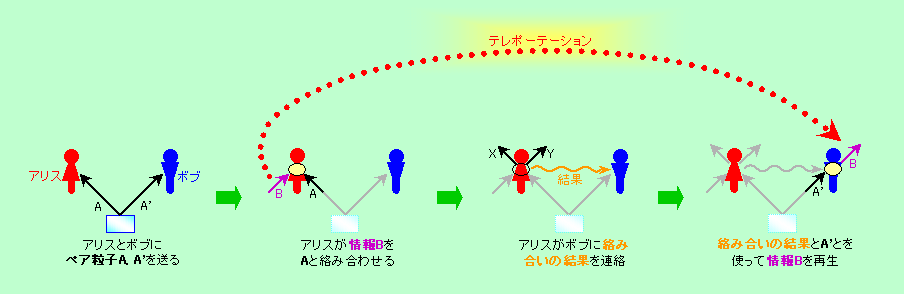雑科学ホーム
hr-inoueホーム
● 量子論の話 ●
雲をつかむような話
ある量に対して、それ以上は細かく分割できない基本となる単位の量がある場合に、その単位量を「量子」と言います。例えば電気の基本単位である電気素量。これは電子1個の電気量で、その半分とか3分の1とかの電気量はありませんから「量子」です。そして普通に目にする電気量は量子の整数倍、つまり電気素量の2倍、3倍・・・・1億倍・・・という飛び飛びの値で表されるのです。このことは、電子という粒子が基本になっていることを考えれば至極当然で、誰でもすんなり理解できると思います。ところが、波であるはずの光のエネルギーとか、原子や分子が振動するエネルギーにも基本になる単位、つまり「量子」があり、全体のエネルギーはその量子の整数倍の飛び飛びの値しか取れない、というから話がややこしくなります。波のエネルギーは振幅(の2乗)で表され、その振幅は連続的にどんな値でも自由に取れるはずでした。ところが実際の光には、基本になる単位のエネルギーを持った粒のような性質があるというのです。同じように、電子そのものは(量の基本単位という意味での)量子ではありませんが、その電子がとることのできるエネルギーは飛び飛びの値しか許されません。しかも粒だと思っていた電子自体も実は波のような性質を持っている。何とも不思議な感じですが、これが「量子論」の世界。「なぜ?」と聞かれても、「それは神様に聞いてくれ」としか答えようがないのです。
量子論と言えば、行列式や波動関数がズラッと並び、ラプラシアンやハミルトニアンなる演算子が飛び交う数式のオンパレードになることが多いのですが、もちろんこのサイトではワラビ(∫)や軍配(Ψ)は禁止されているので使いません。その辺のことは例によって専門書に任せて、ちょとしたトピックスに絞って話を進めます。とは言っても我々の実体験とはおよそかけ離れた現象が次々に出てくるので、本当に「雲をつかむような話」に聞こえるかもしれません。でも、それはそれでいいのであって、敢えて「雲」を「綿」のようにして解釈する必要はないのです。「綿」はあくまでも理解しやすいようにした例え話に過ぎず、モワッとした「雲」が本当の姿なのですから。ここは敢えて、雲は雲のままで「そういうものなのだ」と納得することにして(私自身の理解もそんな程度です)、量子論の世界をちょっと覗いてみましょう。
波と粒、超現実的な現実
量子の世界で常に話題になるのが、粒の性質(粒子性)と波の性質(波動性)という考え方です。我々が直接見ることができる大きさ(ミリメートルとかキロメートルとか)の世界では、物は全て実体のある「物体」であって、実体のない純粋な「波」と言えば光(電磁波)ぐらいでしょう(海の波や音波などは「物体」が連動して動いているだけですから)。「物体」は居場所がはっきりわかる「粒」であり、それぞれ大きさや重さや速さを持っています。一方「光」は「波」であり、大きさや重さはよくわかりませんし、居場所もはっきりしませんが、とにかく何らかのエネルギーを持っていて、干渉や回折、といった独特の性質を示します。たいていの現象は、このような割り切り方で問題なく説明できていました。ところが、これではどうもうまく行かないことが出て来ました。その一つが、
発光の話でも説明した黒体輻射です。ここで初めて、光のエネルギーは連続ではなくて、基本単位を整数倍した飛び飛びの値になっているらしい・・・ということが示されたのです。
光が波だとすると、その強さは振動の振れ幅、つまり振幅で表されますから、ゼロから大きな値まで連続的に強度が変化できるはずです。振幅10の光もあれば振幅11もあり、その間の10.1とか10.000028とか、いくらでも好きな値をとることができるはずなのです。ところが実際はそうはなっていなかった。波長が決まった光には、それ以上分割できない基本の強度がちゃんとあったのです。これが光の量子、「光量子(または単に光子)」です。干渉とか回折とかを起こすという点で光は紛れもなく「波」の性質を持っているのですが、強度(エネルギー)に基本の値があるという意味では「粒」的な性質を持っていたわけです。強い光というのは波の振幅が大きいというよりも粒の数が多いと考えるのが適当だったわけです。
この考え方を決定的にしたのが、アインシュタインが提唱した光電効果の説明です。物体に光が当たると、光のエネルギーをもらった電子が外に飛び出したり、低いエネルギー状態にいた電子が高いエネルギー状態に飛び上がったりします。これが光電効果ですが、この時に奇妙な現象がありました。光電効果が起こるには、光の波長がある値よりも短いことが必要で、波長が長いと、どんなに強烈な光を当ててもダメなのです。また、飛び出して来る電子の数やそのエネルギーにも特徴がありました。光の波長を短くすると、飛び出す電子のエネルギーが大きくなるのですが、同じ波長の光を当てた場合には光を強くしても1個1個の電子のエネルギーは同じで、電子の数が増えるだけなのです。この現象は、「光は波長で決まる単位のエネルギーを持った粒(光子)である」と考えるとうまく説明できます(図1)。
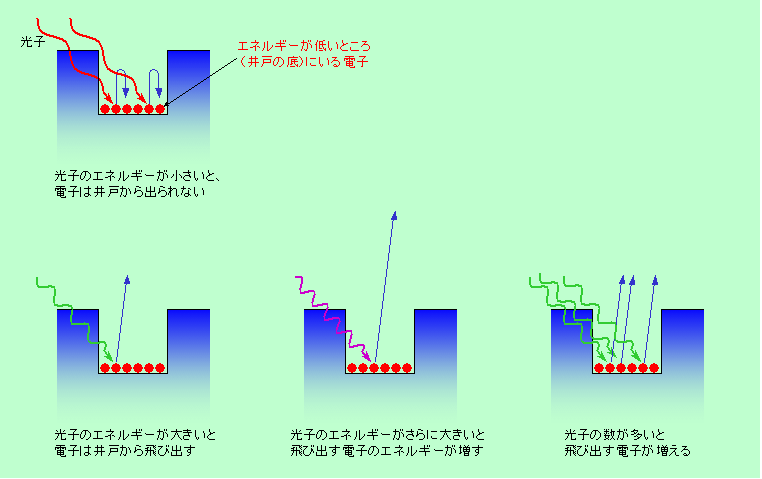
図1 光の粒がぶつかって起こる光電効果
電子は初めはエネルギーの低い(安定な)井戸の底にいます。光が波であるならば、広い範囲にボワッと光が当たることになりますが、光を光子という粒であると考えると、それがぶつかることができるのは特定の1個の電子になります。1個の光子が1個の電子にぶつかることでエネルギーを渡し、その電子を外に叩き出すのです(1個の電子に2個以上の光子が全く同時にぶつかる、ということはほとんどないので無視)。この時、エネルギーの小さい光子では、電子を叩き出すことはできません。エネルギーが足りなくて、電子が井戸の壁を登りきることができないからです。この状況は光を強くしても同じことです。光を強くするということは光子の数を増やすということなので、個々の光子が力不足では、いくら強烈な光を当ててもダメなのです。ところが光子のエネルギーが十分に大きければ、1個の光子で1個の電子を叩き出すことができます。光子のエネルギーが大きいほど、叩き出された電子の勢いはよくなりますし、同じエネルギーの光子の数を増やす(つまり光を強くする)と、多数の同じ勢いの電子が飛び出すことになるのです。この光電効果は光を検出する手段として有効で、
表面分析の話で出て来た光電子分光や、ノーベル賞で有名になったカミオカンデの光電子増倍管などに使われていますし、
太陽電池で起こっているのも同じような現象です。光による化学反応でも光子がぶつかることで電子のエネルギーが高いところに飛び上がることに基づいており、1個1個の光子のエネルギーが、反応が起こるかどうかを決めるポイントになっています。この例としてよく引き合いに出されるのが、紫外線による日焼けです。ストーブやコタツでは何時間かけても日焼けはしませんが(ヤケドは別)、紫外線を含んだ太陽の光を浴びると簡単に焼けます。ストーブやコタツの赤外線では光子のエネルギーが不足で、肌の組織に変化を起こさせることはできないのです。
光と同じことが電子にも言えます。電子は一見すると粒のようですが、これにもちゃんと波の性質があります。例えば電子の集まりである電子線を細いスリットに通すと、一部は陰の部分に回り込みます(回折)。さらに2本の電子線を交差させると、干渉して縞模様が現れます。これらは普通の粒ではあり得ない現象であり、電子にも波の性質があると考えなけば説明がつかないのです。
電子顕微鏡はこのような電子の性質をフルに活用したものと言えるでしょう。電子だけではありません。原子核を構成する陽子や中性子も同類です。こうなって来ると、原子核と電子でできている世の中の全てのものは波の性質と粒の性質を両方持っている、と言えそうです。事実その通りで、ボールでも石ころでも、人間の体でも、例外ではありません。ただし、量子の世界の波はごく小さな範囲でユラユラしているだけですから、我々が目にするようなサイズの物体では、波の性質が見えて来ることはまずありません。駅の改札口からドッと出て来た人の群れが干渉を起こして縞模様を作る、なんてことはないのです。
ところで、量子の考え方ではあらゆるものが波の性質と粒の性質を持っている、と言って来ましたが、この2重人格のような言い方にはちょっと違和感がある気がします。量子という人格は元々一つであって、それが示すいろいろな行動を、これは波的、これは粒的、とマクロの世界の勝手な基準で振り分けているだけ、というのが本当なのかもしれません。超現実的に見えますが実はこれが現実であって、サイズの大きな人間の頭がなかなかついて行けない、ということだと思います。もしも人間のサイズが(ガモフの「不思議の国のトムキンス」のように)原子が見えるぐらいに小さかったら、量子の振舞いも何の抵抗もなく受け入れられるのでしょう・・・・たぶん。
捉えどころのないもの
光や電子などに波と粒の両方の性質がある、ということを頭において考えると、例えばレンズで光を集める、というような簡単な現象でもいろいろと面白いことが見えて来ます。図2を見てください。
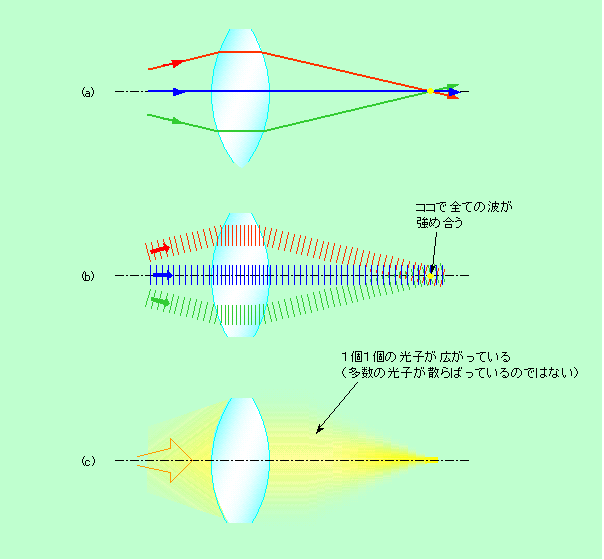
図2 凸レンズで光を集める現象も見方を変えれば・・・・
図2(a)は単純に光の進行方向を直線で表した光路図です。ここでは波とか粒とかは関係なく、同じ媒質(真空とか空気とかガラスとか)の中では光はまっすぐ進むということ、そして違う媒質との境目では屈折率に応じて進路が曲がる、ということを考えれば事足ります。ただこれは単に実際に起こる現象に基づいて法則を決めただけの話であって、そもそもなぜ屈折が起こるか、などということは気にしていません。そこで光が波であることを意識して、もう少し詳しく見たのが図2(b)です。光は空気中からガラスなどの中に入ると速度が落ちます。この時、波の周波数はそのままですから、レンズの中では波がギュッと押し縮められて波長が短くなっています。レンズの中心を通る光はただ波長が変化するだけでまっすぐに通り抜けます。しかしそれ以外の所では空気とガラスの境界に対して斜めに光が入りますから、早く境界に達した部分から順次波長が変化して進行方向が変わることになるのです。これが屈折現象です。さらに、光が集まる部分では、もっと波らしい現象が起こります。波の山どうし、谷どうしが重なって、特定の場所でだけ光が強められるのです。凸レンズで光が1点に集まるのは、いろいろな方向から来た光がこのような干渉を起こした結果と見なすことができるのです。
ここまでは量子の話とは関係ありません。問題はここからです。先に光は粒の性質を持っていると書きました。それでは粒として見た光は、どのようにレンズを通るのでしょう。たくさんの光子がレンズに入るとすると、レンズの中心を通った光子はそのまま直進し、周辺部を通った光子は進路が曲がって1点に集まる・・・・のでしょうか。
光子が大量にあるのならば、このような解釈もできなくはなさそうです。それでは、光子が1個だけだったらどうでしょうか。最終的には同じ場所に来るとしても、その光子はいったいレンズのどこを通ってきたのでしょうか。答は、図2(c)のように「レンズのあらゆる場所を通って来た」です。もっと言うと、レンズのない部分も通っていて、その場合は1点には集まりません。・・・・・さあ、わけがわからなくなってきました。光子はいったいどこにあるのでしょう。実はこの忍者のような状態こそが、量子論に出て来る粒子の真骨頂なのです。
図2(c)のどこかに光の検出器を置いてみましょう。どこに検出器を置いたら光が捕まるかというと、どこでも捕まる可能性があります。ただし、100回検出を試みた場合に何回うまく捕まえることができるか、という確率は場所によって違っています。たぶん中心線附近は確率が高く、周辺部は低いでしょう。このような状況を表すには粒のような書き方では無理で、波のような表現をするしかありません(広い範囲に広がっていて、濃いところや薄いところがあるのですから)。ところが運よく検出器で捕まった時には、検出器は光子丸々1個分のエネルギーを示します。つまり、捕まるまでは波のように広い範囲にボワッと広がっていたのに、捕まった瞬間に、その一箇所に粒として集中するのです。初めに光子の居場所が特定できないのは、決して検出する技術が未熟だからではありません。捕まえるまでは居場所を特定できない(あるいはどこにでもいる)、そういうものなのです。
光子が大量にある場合も同じで、ある光子はここで、別の光子はそこ、というように散らばっているのではなくて、全ての光子がボワッと広がってどこにでもいます。そしてこのような性質を持った捉えどころのない光子を捕まえるには、とにかく適当に検出器を振り回すしかないのです。無責任なようですが、当たるも八卦、当たらぬも八卦の確率の世界、それが量子の世界です。
次に、波の代表的な性質である干渉を考えてみましょう。
電子顕微鏡の話や
立体映像の話のホログラムのところで説明したように、2個のスリットを通った光や電子線は干渉を起こして、図3(a)のようにスクリーン上に縞模様を作ります。
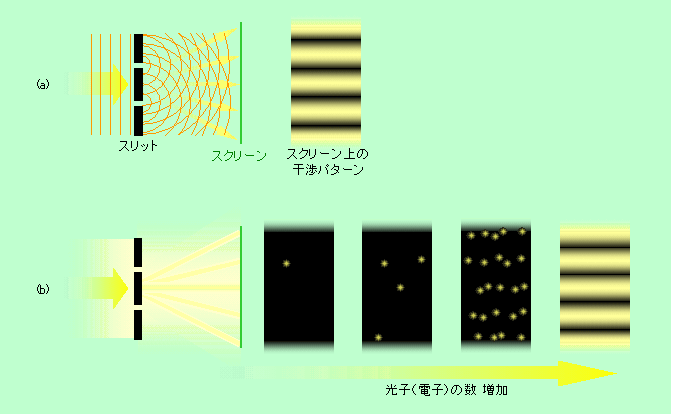
図3 干渉現象も見方を変えれば・・・・
ここでレンズの時と同様に、波のようにボワッと広がった光子(電子)を考えてみましょう。それぞれの光子(電子)は、図3(b)のようにスクリーン上の広い範囲に到達する可能性があります。多数の光子(電子)がパラパラと広い範囲に散らばっているのではありません。1個1個の光子(電子)が広がっていて、どこにでも現れる可能性があるのです。ただし、どこでも同じ確率で現れるわけではなくて、波の性質から来る干渉の効果で、濃い(現れる可能性が高い)ところと薄い(現れる可能性が低い)ところがあり、この確率の濃淡は干渉縞の濃淡と一致しています。それでは、光子(電子)が1個しかなかったらどうでしょう。光子(電子)1個でも干渉縞はできるのでしょうか。個々の光子(電子)が波のような性質を持っているのですから、干渉縞ができてもよさそうに思えますが・・・・。この答は「NO」です。スクリーンで捕らえた瞬間に、光子(電子)は1箇所に集中してしまう、つまり粒としての性質を見せるのです。その様子が図3(b)のスクリーンの図に示されています。
1個の光子(電子)は、確かに広い範囲にボワッと広がってスクリーン上にやって来ます。干渉縞の明るくなるはずの部分に来る可能性が高いのですが、そのどこに来るかは捕まえてみなければわかりません。そして実際に捕まえると、左端のスクリーンの図のように、どこか一点だけが明るく光るのです。光子(電子)の数を増やして行くと、このような明るい点がどんどん増えて来て、最終的には右端に示したような干渉縞ができ上がります。同じようなことは、光子(電子)1個をスクリーンに当てる操作を繰り返し、それを記録して行った時にも起こります。光子(電子)1個がぶつかるたびに、スクリーン上のいろいろな所に明るい点が記録され、最後はやはり同じ干渉縞が得られることになるのです。1個だけではどこに来るかわかりませんが、たくさん集まると一定の結果に落ち着く、という正に確率の考え方そのものなのです。サイコロを1回や2回振っただけではデタラメな目が出るだけですが、何百個も同時に振ったり、1個のサイコロを何回も振ったりすれば、それぞれの目はちゃんと6分の1の比率で現れる、というのと同じことです。
広い範囲にボワッと広がった状態というのは、原子の中の電子にも見られます。一番簡単な原子模型では、太陽の周りを惑星が回るように、原子核の周りを粒としての電子が回っています。しかし実際の電子は、原子核の周りを円や楕円の軌道を描いて粒として回っているわけではなく、周りの空間にボワッと広がっています。ただしこの場合でも広がり方は一様ではなくて、電子が捕まる可能性が高いところと可能性が低いところが規則的にできて、波のような状態になっています。さっきのレンズや干渉の例と同じですね。
電子が原子の中で同じ状態を安定に保つには、ぐるっと一回りした時に波の山の部分(例えば電子の存在確率が高い部分)がいつも同じ位置に来なければなりません。例えば、ある場所に山があり、90度回ると谷に、さらに90度(計180度)回るとまた山に、そしてさらに90度(計270度)で谷になり、一周(360度)回るとまたピタッと山になる、という感じです(かなり乱暴な例えですが)。このような条件が付くために、電子が取ることができる波の状態というのはいくつかの決まった形に制限されてしまいます。この波の状態でエネルギーが決まりますから、結果として、原子の中の電子は飛び飛びの決まったエネルギー状態にしかいられなくなるのです。
ピタッと決まらない世界
レンズを通る光子も、原子の中の電子も、波のように広がっている時にどのくらいの勢いで飛んでいるのか、どのくらいのエネルギーを持っているのか、ということはわかっても、どこにいるのかは捕まえてみるまでわかりません。「わからない」というのは気持ちが悪いので、とりあえず捕まえてみましょう。例えば電子がボワッと広がっているところに波長の短いガンマ線などを当ててみます。適当に振り回したガンマ線が運よく電子に当たれば、電子はその瞬間に粒のように一箇所に集中して、ぶつかったガンマ線が跳ね返りますから、それで電子の位置を決めることができます。これでめでたしめでたし・・・・とは行きません。ガンマ線が当たることで電子は弾き飛ばされてしまいますから、最早、以前の状態ではないのです。つまり、位置が決まった瞬間に飛んでいる速さや方向が変わってしまうのです。そこで電子があまり大きく弾かれないように、ガンマ線をやめてもっと波長の長い低エネルギーの電磁波を使ってみます。これで電子の動きにはあまり影響を与えないで済むでしょう。ところが、電磁波にはその波長程度の位置のボケがつきものですから、今度は電子の位置を決める精度が悪くなってしまいます。あちらを立てればこちらが立たずで、八方塞がりの状態。なにかいい方法はないのでしょうか。
実は、「いい方法はない」というのが結論です。全ての状態をピタリと決めることはできない(正確には、位置と運動量、または時間とエネルギーの両方を正確に決めることはできない)。これが有名なハイゼンベルクの不確定性原理です。「無理に位置を決めようとして変な手段を使ったからいけないのではないか」、と言いたいところですが、どんな手段を使おうと必ず相手に変化を引き起こしてしまいますから、どうしようもないのです(上に挙げた話以外にも、たくさんの例が出されています)。これは技術的に未熟だからではなく、どんなに技術が発達しても原理的に両立不可能な自然の本質、とされています。
「それならば手を出さなければよい」というのはどうでしょう。「無理に人間が測定なんぞしなくても、位置も運動量もどこかでちゃんと決まっているはず・・・」。これに対してはいろいろな考え方があるようです。一方の極端な考え方は、測定していないことには意味はない、というものです。手を出さないことには意味がないのですから手を出さざるを得ず、手を出せば不確定性が現れる、というわけです。(この考え方をさらに大きく広げて、世の中の全ての現象は人間が認識して初めて決まる、と考える人もいるようですが、ここまで行くとちょっと・・・・) これとは別の立場として、自然は元々不確定な要素を持っているのであって、測定の仕方によって違った現れ方をする、という考え方があります。先に「光子や電子は元々一つの人格であり、それが示すいろいろな現象を波だ粒だと勝手に分けているだけ」という見方を紹介しましたが、それと同じ立場です。「全てがはっきり決まるべき」という前提自体が成り立たないのであり、測定のやり方によって、はっきりする部分やぼやける部分がいろいろと変わってくる、というわけです。私としてはこっちの方が理解しやすい気がするのですがどうでしょう。なんとなくしっくり来ない? それはそうでしょう。あのアインシュタインでさえ最後まで納得しなかったそうですから。
ただし、はっきり決まらないと言っても、その不確定の幅はものすごく小さなものです。我々が日常目にするマクロな世界で簡単に検出できるような量ではありません。実験の精度が悪いのは不確定性原理のせい、などという言い訳は通用しませんから、念のため。
光子や電子の居場所は確率でしか言い表せないとか、不確定性原理だとか、量子論の世界はとかくスッキリ決まらない世界です。スッキリしないついでにもうひとつ、有名なパラドックスを紹介しておきましょう。「シュレディンガーの猫」の話です。これには図4のような実験装置を使います。(本当にやるのではなくて、頭の中で考えるだけです。動物愛護。)
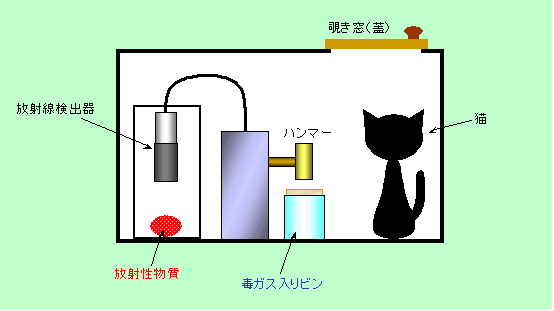
図4 猫は生きているのか死んでいるのか?
放射性物質からは一定の確率で放射線が出て来ます。その放射線を検出器が受けると信号が送られて、ハンマーが毒ガスの入ったビンを壊すようになっています。つまり、放射線が出ることで猫がご臨終となるように組まれているのです。ここで、例えば1時間に1個の放射線が出る確率がちょうど50%になるように、放射性物質の量を調節しておいたとしましょう。この場合、1時間後に装置の蓋を開けて中を見たら、猫は生きているでしょうか、死んでいるでしょうか?
1時間以内に放射線が出る確率が50%ということは、何回も測定すれば、半分は放射線が検出され、半分は検出されない、ということです。あるいは、同じ装置をたくさん並べて調べれば、全体の半数で放射線が検出される、ということです。ですから、猫を入替えて何回も調べれば、あるいは装置をたくさん並べていっぺんに調べれば、半数の猫は死んでおり、半数の猫は生きている、ということになるでしょう。これで一件落着・・・とは行きません。多数の測定結果全体を眺めるのではなくて、1台1台の装置で何が起こっているかが問題なのです。
放射線が出るかどうかは正に量子論的な確率の問題です。放射線が出たかどうかは、実際に検出してみて初めてわかることであって、検出するまではどっちも半分づつ、と考えなければなりません。レンズを通る光子の例を思い出してください。光子がどこを通ったかは、途中で光子を検出した瞬間に初めてわかるのであって、それまではレンズ全体のどこにでもいる可能性があります。それと同じように、結果を見る前というのは、放射線が出た状態と出なかった状態を半分ずつ持った不思議な状態なのです。
話が放射線の検出に留まっていれば、これでも何とか納得できるかもしれません。ところが図4には猫という生き物が登場します。中をのぞいてみれば、猫が生きているか死んでいるかははっきりするでしょう。しかし中を見るまでは、猫は半分生きて半分死んでいる、と考えるしかないのです。これは決して「半死半生の死にかかった状態」ではありません。完全に死んでいる状態と、完全に元気な状態とが「半々」だと言っているのです。ついでに言うと、ハンマーも、動いた状態と動かない状態とが半々、毒ガスのビンも、割れた状態と割れていない状態が半々です。化け猫じゃあるまいし、そんな状態は考えられない? 確かに具体的に想像することはできないかもしれませんが、想像できないからと言って「あり得ない」と言うことはできません。だいたいこれまでの話だって、ほとんど想像できないようなことばかりですから。
それはおかしい、という意見があるかもしれません。放射線を検出するという行為は、検出器が捕らえた時点で既に終わっている。そこで放射線が出たかどうかは決まっているのだから、猫の生死はそれに応じてどちらかに決まるだけ・・・・。 確かにそういう考え方もあります。放射線を検出した信号を誰かが確認して、その後でハンマーを動かすスイッチを入れるのならば、何の問題もないでしょう。2つの状態が合さった不思議な状態は放射線のところで終わり、ハンマーやビンや猫にまでは及びません。放射線を検出した時点で、猫ははっきり「生きている」か「死んでいる」かのどちらかに決まってしまいます。しかし・・・・。装置の蓋を開けなければ中の様子がわからない場合、検出器の部分とそれ以後の部分の間に線を引く明確な理由があるでしょうか。検出器だってハンマーだって猫だって原子核や電子が集まったものであることに変わりはありません。放射線はミクロで、それ以後はマクロ・・・・・と言っても、ミクロとマクロの境目も曖昧です。さらに言えば、装置を開けた瞬間に全てがわかるのではなくて、人間の目が猫から出た光を捕らえ、その信号が脳に伝わり、脳が猫の生死を認識したところでようやく完結です。また、この実験が部屋の中で行なわれている場合、部屋の外で待っている人にはこの時点でもまだ結果がわかりません。部屋の中で猫の生死を見届けた人が、「猫は生きていました」とか「猫は死んでいました」とか書かれた垂れ幕を持って駆け出して来て初めて結果がわかるのです(実際に見るまでは垂れ幕に何が書いてあるかも決まっていない)。こうなると、ここまでが不確定状態でここからが確定状態、という線引きをするのは難しそうですね。やはり中を見る前、あるいは結果を知らされる前の猫は「生死半々」と考えるしかないのでしょうか。しかも状態が確定するタイミングは立場によって違うのです。
実のところ、シュレディンガーの猫については、まだ完璧な説明はされていないようです。ちょっと面白いところでは、生きている猫を見た人と死んでいる猫を見た人とは違った世界に飛んで行ってしまう、という考え方があります。猫は生死のどちらかに決まるのではなく、猫が生きている世界と死んでいる世界の2つの世界に分かれる、と言うのです。この考え方ですと、猫の件に限らず、光子や電子が捕まった瞬間に一箇所に集中する、という事実にも別の解釈ができることになります。つまり、光子や電子は一箇所に集中するのではなく広がったままであり、ある場所にいる光子/電子を見る人と、別の場所にいる光子/電子を見る人とは違った世界にいる、ということです。粒子が集中するのではなくて世界の方が次々に枝分かれする。どうです? ちょっとぶっ飛んでますか?
壁抜けの術
居場所の定まらない光子や電子は、時として、いるはずのない場所に現れることもあります。例えば図1のような井戸の底にいる電子。図1では電子を粒のように描いていますが、実際には井戸の底全体にボワッと広がって存在しています。その存在確率は場所によって違っているでしょうから(この違いは原子核の配置などによって決まります)、とりあえず図5のような波型で表しておきましょう。この電子は、外からエネルギーをもらわない限り、高いエネルギーの壁を乗り越えることはできないはずです。ところが忍者のような電子は、井戸の底のどこにでもいるというだけではなくて、何と井戸の外側にもいることがあるのです。これが壁抜けの術、トンネル効果です。
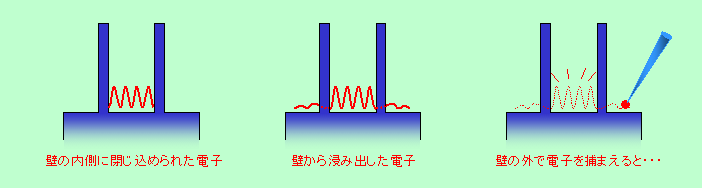
図5 量子の世界では壁抜けは日常茶飯事
実際の世界では、(壁が薄い場合)右側の図のように電子の波は壁の外にも浸み出しています。このことは、電子は壁の外側でも捕まる可能性がある(壁の外にも存在確率がある)、ということを示しています。このままの状態であれば、電子は壁の内側にもいるし外側にもいる(もちろん内側にいる確率の方が高い)、ということで話は済むでしょう。しかし、もし壁の外側でこの電子を捕まえたら、その瞬間に電子は捕まった場所に集中しますから、内側には電子がなくなってしまいます。つまり、電子は完全に壁を通り抜けたことになるのです。
走査トンネル顕微鏡という分析装置があります。微小な針を試料の表面で動かして表面形状を原子レベルで測定する装置で、1981年に発明されてノーベル賞の対象にもなりました。この装置では、試料に余計なダメージを与えないために、針は試料表面に接触しないギリギリの距離で動かします。普通に考えれば、これでは試料からの情報が針に届きませんから測定ができませんし、第一ギリギリの位置に止めることも不可能なはずです。にもかかわらずちゃんと測定できるのは、電子が針と試料との間の空間(ここは電子から見れば通過できないエネルギーの壁です)を通してトンネル効果で移動する(つまり電流が流れる)からです。電子だけではありません。原子核を構成している陽子や中性子でも同じような現象が見られます。例えば、放射性物質の崩壊で出て来るアルファ線。これは原子核から陽子2個と中性子2個がくっついたアルファ粒子が飛び出したものですが、原子核の周りには高いエネルギーの壁があるので、普通はこんなことは起きないはずです。壁をすり抜けるトンネル効果があって初めて起きる現象なのです。これ以外に、半導体素子などでもトンネル効果は普通に見られる現象で、ミクロの世界では日常茶飯事と言ってもいいのです。
それではマクロの世界ではどうでしょう。オバケのように壁をするりと通り抜ける、というようなことは起こり得るのでしょうか。実は可能性が全くないわけではありません。人間の体は原子核や電子の集まりですし、ブロック塀だって同じです。ブロック塀の原子核や電子が作るエネルギー障壁を、人間の体を作る原子核や電子がすり抜ける、という確率は、とんでもなく低いですがゼロではないのです。ちなみに、どれくらい確率が低いかと言うと、0.00.......001で、ゼロの数が少なく見積もっても1兆の1兆倍個くらい。壁の高さや厚さがちょっと大きくなれば、そのまた1兆倍の1兆倍の1兆倍の1兆倍の1兆倍の1兆倍の1兆倍個(10100個以上)ぐらいには簡単になってしまいます。想像できます? ゼロ1個の幅を1mmとして、ゼロが1兆の1兆倍の10万倍個(1029個)も並べば宇宙の大きさくらいになるのですから(1029mm=100,000,000,000,000,000,000,000,000,000mm=100億光年)、この数字がとてつもなく小さいということだけはわかるでしょう。
超能力? 量子テレポーテーション
量子論の世界では実際に観測してみるまで状態が決まらない、ということは何回も書いて来ました。これが1個の光子や1個の電子の話ならば、とりあえずそういうもの、として納得することはできるでしょう(できたとしましょう)。ところが、世の中には2個ペアになった光子や電子が存在します。この場合、その一方だけを捕まえて状態を決めたら、もう一方はどうなるでしょうか。実は、どんなに遠く離れていても、もう一方の状態も同時に決まってしまうのです。
これを実現するには、ペアになった一組の粒子(光子、電子、原子)を準備する必要があります。実験的に最も扱いやすい光子の場合、よく使われる方法の一つは、図6(a)のように1個の光子を2つに分けるものです。ある種の特殊な結晶に光を通すと、波長が2倍の光が出る場合があります。光子で言えば、1個の光子が、エネルギーが半分の2個の光子に分かれるのです(光子は分割できないはず、と言ってはいけません。分割できないのは波長、つまりエネルギーが一定の場合であって、エネルギーが半分になるのならば2個に分かれてもいいのです)。分かれてできた2個の光子は元の1個の光子の特性を分け合うことになりますから、飛び出す方向は左右対称になりますし、偏光の状態は対になるのです。(厳密に言えば偏光方向の違う光は結晶の中を伝わる速さが違う場合があるので、完全なペアにするためには微調整が必要ですが、ここでは省略)
「偏光」とは振動方向に規則性がある光のことで、例えば直線偏光は振動の方向が一つの方向に偏っています。普通の光にはいろいろな方向に振動する成分が混ざっていて、偏光板と呼ばれる特殊な板を通すと、特定の方向に振動する成分だけが通過する、というのが一般的な解釈です(
立体映像の話、
顕微鏡の話参照)。ただし量子の世界の解釈ではこうはならないことは既におわかりでしょう。そうです。光子が1個しかない場合はどうなるかを考えるのです。当然、答は「1個の光子があらゆる方向に振動している」となります。そしてこれを偏光板に通した瞬間に、振動の方向が決まるのです。もし振動方向が偏光板の方向と同じならば丸々通過しますし、違っていればシャットアウトされてしまうわけです。
ペアになった光子の場合、一方が縦方向に振動する偏光状態ならば、もう一方は横方向に振動する偏光状態のはずですし、一方が右回りの偏光ならば、もう一方は左回りの偏光のはずです。このように偏光状態が逆なのは確実なのですが、実際の偏光状態がどうなっているかはもちろん決まっていません。測ってみるまでわからないのです。
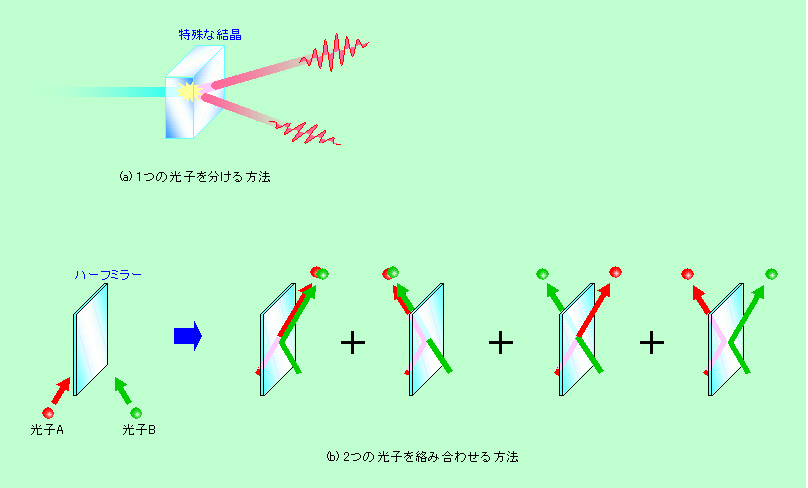
図6 ペア粒子の作り方
ペアを作るもう一つの例は、元は別々であった2個の光子を図6(b)のように絡み合わせる方法です。これには、光を半分反射して半分透過させるハーフミラーという鏡を使います。この鏡に、両側から同時に光子を当てたとしましょう。それぞれの光子は、反射と透過が半々の状態になります。出て来た側から見ると、鏡の右側だけに2個の光子が出る状態と、その逆に左側だけに2個の光子が出る状態、そして両側に1個ずつの光子が出る状態(2通りあります)の4つの状態があり得ます。この場合、ある時は右に2個、またある時は左右に1個ずつ、というのではなくて、例によって4つの状態が対等に混ざり合っています。2個の光子は区別できず、右に2個でもあり、左に2個でもあり、左右に1個ずつでもあり、全体として1つの状態になっているのです。
全体として1つの状態ということは、出て来た2個の光子は当然ながら1つの状態を2つに分けたペアになっている、ということです。つまり、一方が縦方向の偏光ならばもう一方は横方向の偏光になるわけで、1個の光子を2つに分けた図6(a)と同じような状況が、元々関係のなかった2個の粒子の間にも作られているのです。ただし、実際にペアを作るのは簡単ではありません。キッチリ半分ずつ反射・透過できるハーフミラーに、寸分の狂いもなく位置も角度も時間もピッタリ合わせた2個の光子を入れなければなりません。ちょっとでもズレると2個の光子が区別できてしまいますから、全体が1つの状態にはならないのです。
このようにして作ったペアはどこまで行ってもペアで、お互いの関係は変わりません。何キロ離れようが、何万光年遠ざかろうが、状態は同じです。そこで、ある時点で一方の光子の偏光状態を測定したとしましょう。測定した瞬間に、その光子の偏光状態が決まります。すると、それと同時に、はるか遠くに離れたもう一方の光子の偏光状態も(それとは逆であることが)決まってしまうのです。何万光年離れていても、です。この考え方が出た時点では、このように光よりも速く情報が伝わることなどあり得ない、という意見もあったようですが(と言うか、普通に考えればそうでしょう)、今では実験的にも確認されています。
ところで、これだけのことでしたら、例えば偏光の方向がどちらに決まるかなどは偶然の産物でしかありません。せいぜいサイコロの代わりぐらいしか利用価値はなさそうです(ムチャクチャに高価になりそうですが)。しかし、これを本当に情報伝達に利用しようということが試みられています。その方法は、図7のようなものです。
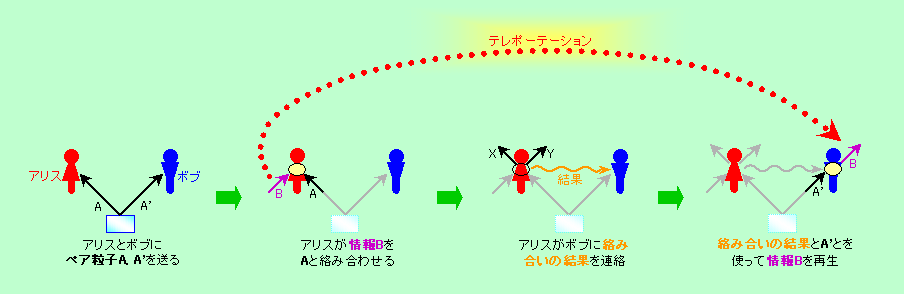
図7 量子テレポーテーションを使った、絶対に盗まれない通信
情報の送り手をアリス、受け手をボブとします(この呼び名は最初の論文で使われて、その後慣例になったようです。もちろん花子さんと太郎さんでもかまいません)。初めに、AとA'というペアの粒子を1個ずつ、アリスとボブに送ります。アリス側では、送りたい情報を持った粒子Bを別に用意しておき、BとAとを、図6(b)のような方法で絡み合わせますが、ここで出て来た粒子XやYの状態を一つに決めてしまうような測定はしません。混ざった状態だけを調べて、その結果をボブに連絡するのです。この情報はAとBとの絡み合いから作られたものですが、ボブが初めにもらったA'はAの片割れですからAの運命を引きずっています。そこで、アリスから受け取ったAとBとの絡み合い情報と、Aの運命を引きずるA'とを使って、ボブの所でBを再現することができるのです。
この方法のポイントは、アリスの所でAとBとを絡み合わせた時点でBの情報は壊れてしまっている、ということです。アリスの手元にBは残らず、残っているのはBが絡んだ中途半端な状態だけ。これを処理することでボブの所でBが再び現れるわけですから、肝心の情報Bはアリスの所からボブの所に「移動」したことになるのです。これが「テレポーテーション」と呼ばれる所以です。アリスからボブに測定結果を送るのには電話だとかEメールだとかの手段を使うことになりますから、量子テレポーテーションは特別に高速な通信手段というわけではありません。でもこれには、他の方法にはない決定的な長所があるのです。それは、「通信経路の途中で情報を盗むことは絶対にできない」ということです。
情報を持っているのは粒子Bですが、B自体は通信経路には乗りません。乗っているのはAとBとが絡み合った結果です。しかし、これを盗んでもA'がなければBの情報を取り出すことはできませんから無意味です。それでは絡み合い情報と粒子A'とを両方盗んで、ボブと同じ操作をしたらBが取り出せるでしょうか。これもダメです。A'を盗むということはA'を捕まえる、ということであり、捕まえた瞬間にA'は1つの状態に確定してしまいますから、既に元のA'ではありません(もちろん片割れのAの状態も確定してしまいます)。あくまでも状態が決まっていないA'が必要なのであって、盗んだとたんにそれが壊れてしまうのです。このように、量子テレポーテーションを使った通信では、(途中の粒子を捕まえるなどして)通信の邪魔をすることはできても、情報を盗むことは絶対に不可能なのです。究極の暗号技術と言えるでしょう。
「テレポーテーション」と言えば、離れた所に瞬時に移動する技としてSFの世界でおなじみですね。このようなSFのテレポーテーションは物質そのものが移動するのに対して、こちらの方は情報だけが伝わる点で少し違っています。とは言え、既に原子を使った量子テレポーテーション実験も行なわれており、将来、物質の移動が実現しないとも限りません。ただし、生物を送るとなると別の問題が発生しそうです。図7で説明したように、量子テレポーテーションでは元の情報が送り手側で破壊され、受け手側で再生されます。これを生物に当てはめると、送り手側で一旦死んで、受け手側でそっくり同じものが再生される、ということを意味します。その時、生物の意識や記憶はどうなるのでしょう。送り手のところで一旦眠って、目が醒めたら違う場所にいた、というふうに感じるのでしょうか。それとも・・・・・。
桁違いに高速な量子コンピューター
量子論の話の最後に、量子コンピューターのことにもちょっとだけ触れておきましょう。普通のコンピューターは1か0のデジタル情報を半導体素子の中の電圧の高低として処理するようになっています。電圧を発生するのは、素子の中に蓄えられた電荷、つまり電子の集団です。最近ではたった1個の電子で動く素子も作られていますが、それでも電子1個で扱える情報は0か1かの一組に限られます。1個の素子では一度に1個の情報しか処理できないわけです。ところがこれまでに見て来たように、電子や光子というのは量子論的にはいろいろな状態の重ね合せです。捕まえてしまえば1つの状態を見せるのですが、自由に泳がしておけば、いろいろな状態を併せ持ったままなのです。そこで、電子や光子を途中で捕まえることをしないで、いろいろな状態を持ったままで処理し、最終的に出て来る状態(処理前とは違っていますが、これもいろいろな状態の重ね合わせ)を調べてやれば、たくさんの処理をいっぺんにできることになります。これが量子コンピューターの考え方で、同時にたくさんの処理ができることから超高速コンピューターとしての期待が高まり、一部では原理実験にも成功しています。
1個ずつ処理するから時間がかかると言うのならば、たくさんの素子を並べて使えばよいではないか、という考え方が当然出て来ますね。こういうやり方は実際に使われていますが、量子コンピューターに追い付こうとすると、エライことになります。例えば10個の電子があって、それぞれが右回りの状態(1)と左回りの状態(0)を持っているとしましょう。全体では210=1024通りの状態が重なっていることになります。量子コンピューターではこれをいっぺんに処理できますが、同じ性能を今までの方法で実現しようとすれば、1024個の素子が必要になるのです。このくらいならば何とかなりそうですが、これが電子20個になったら、必要な素子の数は何と100万個以上に跳ね上がってしまいます。30個だったら10億個以上。40個だったら1兆個以上です。逆に1個の素子でチマチマと処理を続けたら、電子40個を使った量子コンピューターが1分でできる計算に200万年もかかることになるのです。
量子コンピューターが注目されるきっかけになったのは、現在のコンピューターで解読に何億年もかかる暗号が数秒で解けてしまう、ということが発表されたことでした。これが本当に実現されたら穏やかではありません。インターネットを使った情報交換など、危なくてやっていられなくなってしまいます。目には目を、ではありませんが、量子コンピューターが実用化されるころには、暗号通信は量子テレポーテーション方式に頼るしかなくなるかもしれません。
量子コンピューターでは計算の途中で測定をしてはいけないわけですが、測定しようとしなくても、電子が容器の壁にぶつかって姿を現したり、外から入ってきた光や放射線の影響で状態が変わったりしたらオシマイです。しかも最後にはちゃんと結果を読み出さなければなりません。このような難しい要求を満たすために、真空容器の中に気体を閉じ込めて光を照射する方式にしたり、液体の中の電子の自転を測る装置を使うなど、いろいろと工夫がされています。今のところ、コンピューターというよりは物理や化学の大型実験装置、という感じですが、未来の量子コンピューターはどんな姿になっているのでしょうか。
雑科学ホーム
hr-inoueホーム